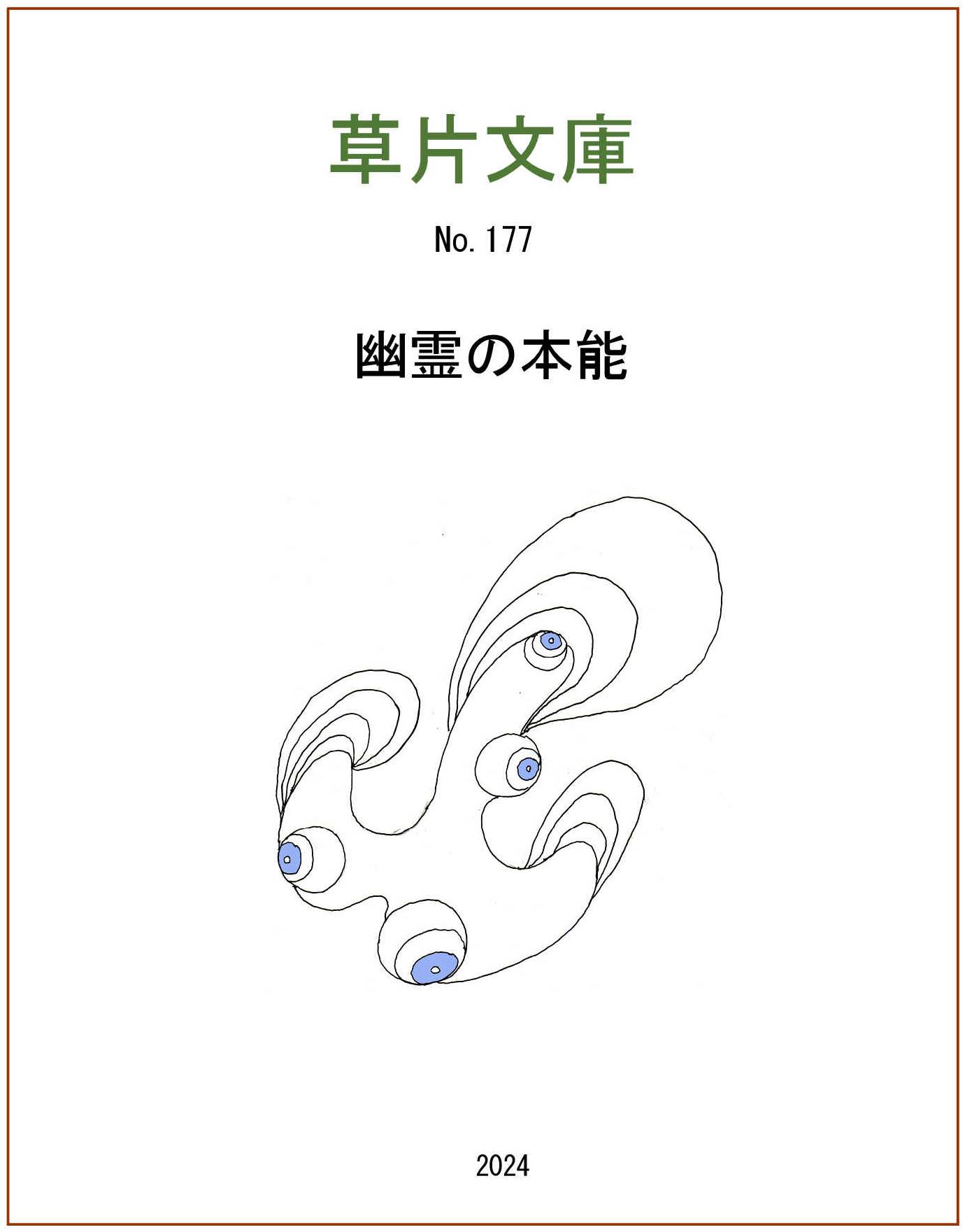
幽霊の本能
幽霊にできるのは、恨むところに行って、恨む者にうらめしやと言って、その後成仏して冥土に旅たつか、相手が死ぬまで言い続けるかのどちらかである。
ここに変わった幽霊がいた。人間にもどりたいというやつである。死人が生き返ることになる。
ところが、死体は荼毘に付され、灰は海に撒かれてしまった。
幽霊は海にいって、海の水に飲み込まれた自分の粉末を探すことになる。海は広い。
まず、どこで撒かれたか。
自分としては、死んだときには育った海に撒いてくれと言ったような気がした。
それで俺はどこで育ったのか思いだそうとした。
困ったことに、幽霊の頭は小さい。頭の中にあった脳は、死んだときにかすかすになってしまうものだ。しなびた脳をもとにもどすには、娑婆のエネルギーを吸い取らなければならない。
幽霊は一番エネルギーがほとばしり出ていると娑婆はどこかと考えた。脳がないので思いうかばない。
夜な夜な、出かけて夜遅くまで明かりのついている一軒一軒のぞいていったのだが、なんてことはない、ただ酔っ払いがいるだけだ。あんな連中は酒のエネルギーを借りているだけだ。そこで団地の家々をのぞいてみた。どの家の人間も、本能行動をしているだけである。食べて、まぐわって、眠ってだ。幽霊はいつもがっかりして夜が明ける。お天道様の光は幽霊の目に悪い。暗がりに行ってお天道様が沈むのを待つ。
まだ若く成人になっていない連中は、すべてではないが、受験勉強や何かの試験勉強をして脳のエネルギーを発散させている。車を飛ばしたりエレキギターを思いっきり音を上げてかき鳴らしたりしているのもいる。それなりのエネルギーがあるが、そいつ等のエネルギーをとっちまうのは幽霊憲章に違反して、それこそ一生涯幽霊でいなければならなくなる。幽霊は意味なく若い連中の未来を奪うことはできない。
ある日、幽霊はとあるマンションの一室一室をのぞいていった。ほとんどが寝ているか、まぐわっているかであったが、その中の一室で、脳のエネルギーを発散させている女性がいた。
男の幽霊がエネルギーをすいとると女がどうなるかわからないが、相当強い脳のエネルギーをもっている。
その女は作家の卵だった。処女出版をはたし、かなりの評判になって、二作目を書いているところだ。
脳のエネルギー発散は、いかに頭脳を使う行為に集中しているかに比例している。集中力の強いときには、発散されるエネルギーが強い。とても香ばしい。
幽霊は毎晩その女性のところにかよった。一回のエネルギー吸収では、幽霊の脳は回復しない。毎日毎日通って、幽霊が死んだ年と同じ年月がかかる。
男の幽霊は三十五で死んだ。一緒に住んでいた女に殺された。女は愛人ができて、男の貯金をねらい、男を毒殺した。古くさい殺人方法だが、毎晩飲むウイスキーにほんの少しのトリカブトの毒をしこむだけで、一年経ったら効果が出て、寝ているときに心臓麻痺で死んだ。女は男の貯金をすべてもって別の男のところにいった。
警察にも疑われず、女はその男と暮らしていた。幽霊になった男は、毎晩女の夢に現れ、それはトリカブトの毒と同じように、じわじわと効いて、一年後、分裂症と診断された女は精神科に通うことになった。相手の男は女をおいて逃げた。思いを晴らした幽霊は、冥土にいかず、生き返ろうと思ったわけである。冥土に夫婦生活はない。
男の幽霊は地味な一生を夢見て生きてきた男である。そういった女と一生を送りたかった。人間に戻ってやり直したい。
海にまかれた灰を少しでもみつけることができればこの世に戻れる。
幽霊は若い女の作家のところに毎晩通った。
女は書くのが行き詰まると、風呂に入った。湯の中でふと頭に何かが浮かぶと、あわてて飛びだし、はだかのままでデスクに座って話を書き始めた。
どのような小説を書いているかわからないが、ときどき女は自分の足の間に指を忍ばせて、こすり、恍惚の顔になる。その場面をかいているようだ。
大きな乳房を自分の手でもみほぐすこともある。
幽霊はその作家の脳からほとばしりでるエネルギーを吸うことも忘れて、女の行為に見ほれてしまった。生き返れば女の匂いもかぐことができて、触れることもできる。
均整のとれた、ふくよかなからだをみているうちに、海にまかれた遺灰をさがしながら、生き返ったらこの女のところに戻ろうと思うようになった。最初に思っていた地味な一生を送りたいという願いとは正反対の生涯になることは十分に想像できた。
一年ほど女のところにかようと幽霊の脳もだいぶ膨らんできた。
思い出してきた。俺は和歌山の御坊のうまれだ。両親が和歌山にいる。両親が俺を殺した女から遺灰をうけとり、俺が女に言ったことを聞いて、和歌山の海に撒いたのに違いない。
幽霊は和歌山の海にいった。自分の死んだ日、荼毘に付された日、それに海に撒かれた日をはっきり思い出した。
和歌山の海にいき、その日に遺灰が撒かれたときにいた魚をさがした。海の底で蟹や海老にも聞いた。海の上を漂っているクラゲにも聞いた。
それも時間がかかった。
海の中を漂っていたある日、真っ赤な鯛に出会った。きれいな均整のとれた鯛だと見ほれていると、鯛のほうから声をかけてきた。
「もしや、あたいが食べた遺灰の幽霊じゃないかい」
「おお、きっとそうだ、やっと会えたぜ、俺の遺灰を食べたやつに」
「なんで探しているのさね」
「娑婆にもどるのさ」
「そうかい、娑婆に戻りたいなんて珍しい幽霊だわさ、でも恨みはどうしたい」
「おう、もう、目的は達した。それでもう一度人間をやってみようと思ってな」
「物好きな幽霊だね、それでどうすりゃもどれるんだい」
「遺体があればそこに潜り込んで戻れるんだがな、俺の場合はそうはいかない、荼毘に付されて灰になった」
「灰じゃあ、だめだろうに」
「いや、水でねって人形ができればいいんだ」
「でもさ、わちきが食べたのは、灰のほんの少しだけだが、それじゃ人形も作れないねえ」
「そうだなあ、きいたところによると、骨が残っていれば、完璧にもとに戻れるそうだが、少しばかりの灰じゃだめだろうな」
「そうかい、ともかく、あたしゃかまわないよ、鱗のひとかけらでも、やろうかね、灰の少しははいっているだろうよ、それにもぐりこんでごらんよ」
鯛は目の脇の赤い鱗を一枚、海の中におとした。
「ありがとよ」
幽霊は真っ赤な鯛の鱗にのりうつった。
鱗はあっという間に、きれいな真っ赤な鯛になった。
「おや、おどろいたね、幽霊が鯛になっちまった」
「人間に戻れなかったが、娑婆に戻れて鯛になった、こりゃおめでたい、幸先がいいぜ」
「目から鱗だねえ、鯛になっちまったのかい」
「鯛の姉さん、きれいだね、俺と夫婦になるかい」
「はは、人間だったくせに、あたしゃ卵をだすだけで、あんたは精子を振り掛けるだけ、がまんができるかい」
幽霊は、そう言われ、アパートで小説を書いている若い女を思い出した。
「ほらごらん、人の女を思い出したのだろう、うまくおやりな」
赤い鯛は泳いでいってしまった。
さて、鯛になった幽霊は、人間に戻るのにはどうしたらいいのかわからずに、海の中を泳ぎまわった。
そんなある日、ふとうまそうな餌が目の前に現れた。
腹が減るなどということは、幽霊には感じることがない生きている者の感覚だ。
赤い鯛になった幽霊は餌にくいついた。
と見る間に、海の中から持ち上げられ、空中にとびだした。
幽霊がもどった鯛はひらひらと体を動かし空を舞った。
とたんに、頭に何かが打ち付けられ死んでしまった。
「大きなきれいな鯛がつれた、あいつの祝いに一番の贈り物だ」
死んだ鯛は大きな皿に盛られ祝宴の会場に運ばれた。
それは、あの若い女の作家の本が泉鏡花賞を受賞した祝いの会場だった。
女が鯛を見た。
「鯛も幽霊になるのかしら」
その一言で、死んだ鯛はまた幽霊にもどった。
女の隣で鯛を釣った彼が微笑んでいた。
今度はどうやって恨みを晴らしてやろうか。
本能も幽霊にもどっていた。
幽霊の本能


