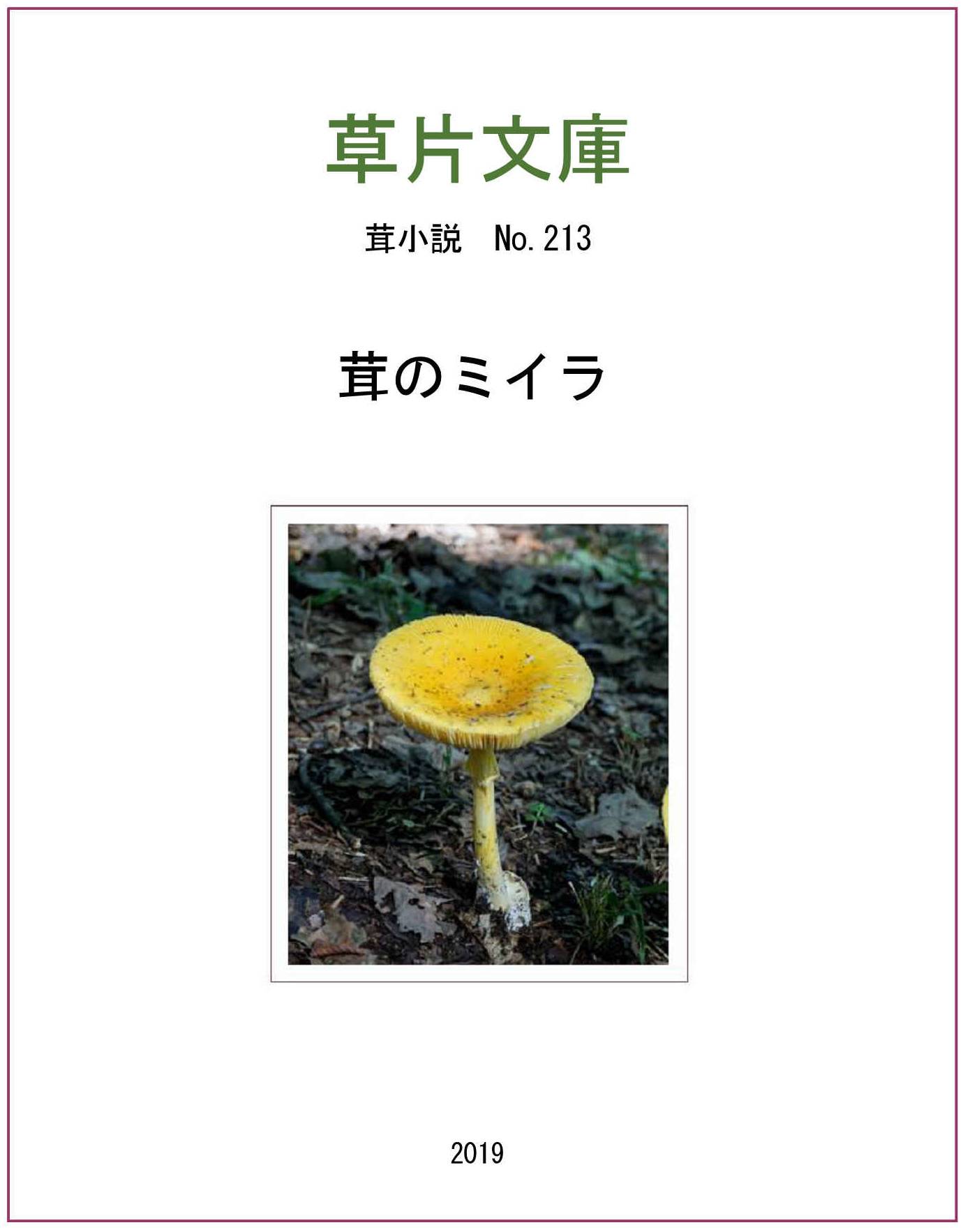
茸のミイラ
私は大学で宗教学と民族学の教鞭をとっている。宗教の始まりに興味を持ち、古代宗教をさぐるため、アフリカの部族間の自然信仰や原始宗教の違いを調べている。そのため、民族学についても知らなければならない。調査には発掘調査なども含まれ、考古学的、人類学的な知識も必要になる。
さらに、原人、古代人、現代人の脳の発達を無視して単純に解析できない。人食を平気とする脳と、同じ人間を傷つけるのを自然と避ける脳で、信仰のあり方は当然違ってくる。脳とからだの生命科学についての知識もとり入れなければいけないと思うのが私の考えである。
そのようなことから、大学では専門に近い考古学、人類学の先生はもちろんだが、生命科学の先生方と飲んだり、宇宙物理学の専門家と空想的な会話をしたりする機会がある。
その中の生物生態学の先生が興味のある話をもってきた。彼は緑石憲男という。
生態学の専門家は往々にして、ある動物、ある植物の一生を研究しているものであるが、彼は植物、動物、菌類、すべての生き物の生活を絡ませて、生態学をやっている人間で、発想が広くて話をしていても面白い。
彼は夏休みの終わり、家族をつれて信州原村のペンションにいった。山を散策するためである。植物、昆虫、茸、面白いものがたくさんあるという。
「三橋先生、信州に行ったとき、変なものをみつけましたよ、写真撮ってきたから見てください」
緑石先生がそう言って研究室に入ってきた。
「八ヶ岳の麓の原村のペンションに三泊してきました」
原村は八ヶ岳のふもとになり、そのあたりはその昔、縄文文化が花開いていたところである。遺跡がたくさんあり、土器、土偶を始め鉄製品などが出土している。隣の茅野市にはそこから出土した有名な国宝の土偶、縄文のビーナスと仮面の女神がある。
「茸でもみようと家族をのせて鉢巻道路を行きましてね、わき道に入ったあと、しばらく行ったところで車を止めて林にはいったらこんなものがあったんです」
そういって写真を広げた。そこには遺跡らしいものが写っていた。
彼はそれを見つけたときの様子を語ってくれた。
林の中の小道を子供たちに茸の説明しながら歩いていたそうである。目立たない山だが、そのあたりはどこに入ってもいろいろな茸を見ることができる。道があるということは、地元の人が茸採りや山菜採りによく来るところなのだろう。
「たくさん茸が生えているからよくごらん」
彼は奥さんと二人の娘を連れて奥に入っていったという。
「面白い茸があるよ、あそこの赤い茸は毒だよ」と彼が説明しながら林を歩いていたら、五歳と六歳の娘が父親の前を走り出した。
「転ばないようにね」と母親が注意したとたん二人ともぱたんと前に倒れた。足が何かに引っかかったのだ。
「ほら大丈夫か」と両親が駆け寄ったが、子供たちは元気に立ちあがった。
「ここに段差がある」、小道の脇が少し高くなっていて。それに足が引っかかったようだ。
林の中にもかかわらず、そこはちょっとした草原になっていて木が生えていない。
クローバやタンポポなどの丈の低い草が生えている。草原は木々に囲まれていて日当たりも悪くない。こういうところにも茸は生える。背の高いたくさんの唐傘茸が、草の中から頭をだしている。
彼が草原に入ったとき、やはりつまずきそうになった。意外と段差がある。どうも石のようなものが道と草原の間に埋めてあるようだ。
彼は奥さんに段差があることを教え、注意してあがるように言った。よく見ると場所によっては二十センチもありそうだ。草でわかりにくい。
子供と奥さんを唐傘茸の間に立たせて写真を撮った。
「唐傘茸は食べられるんだよ、採ってごらん」
子供たちは喜んで茸を採ると両手に持って掲げた。子供用の雨傘にできるほど大きな傘だ。二人は茸を持って走り出した。反対側にいくとまた二人ともころんだ。
両親はほらほら注意しなければと駆け寄って子供を抱きおこした。
「大丈夫かい」子供に怪我はなかったが、もっていた唐傘茸は壊れてしまった。
草原の周りに段差があり、歩いてみると、かなりきちんとした円形である。直径が二十メーターほどだろうか。
草原の縁を靴で踏んでみたところかなり堅い。やはり石が入っていそうだ。そう思って、枯れ枝で掘ってみたそうだ。草を取り去り、土を掘ると、丸っこい石の頭がでてきた。それが並んでいるようだ。所々チェックしたところ、草原の縁のまわりすべてを丸い石が囲んでいることがわかった。
なにかの遺跡である。掘り出した石の頭が自然のままのものではなく、人の手が加わっている。
見せてもらった石の拡大写真では、卵の頭の形をした同じ大きさの石が並んでいる。
「回りを掘ればもっと石は出てきたと思うが、時間もないし、そのままの方がいいと思ってやめた」
「面白いね、どうもありがとう、なんだろうな、この写真を境先生にも見てもらうよ、なんだかすぐ分かると思うよ」
境民雄は我々の大学の人類学、特に縄文時代に興味を持っている学者である。
「もし夏休み中に行くなら、一緒にいって場所を教えるよ」
「うん、学生も連れて行くから、そうなったらよろしくお願いします」
それからしばらくして、境先生が大学に出てきたとき、その写真を見せた。彼は目を輝かせた。
「すごいね、原村のあたりには縄文遺跡がたくさんあるよ、関係があるね、僕も仲間にいれてよ」
ということになり、夏休みが終わる前に、行くことのできる学生を誘って、緑石先生の見つけた遺跡を見に行くことにした。
一週間後、境先生も加わって、研究室のスタッフとともに車をしたて、緑石先生に案内をたのんで信州原村に出かけた。
中央高速にのれば大学から原村は遠くない。小淵沢からすぐである。
案内された場所は、草に覆われてはいるが、確かにきれいな円形の人工的に整えられている。直径は緑石先生の言うとおり二十メートルあった。周囲にはきれいに頭が丸くされた石が埋め込まれている。明らかに人工物である。
「確かに何かの遺跡だな、だけど縄文時代のものなのか,後世のものなのか、僕は始めてみるよ、こういうものは」
境先生もその場所がなんであるか分からないという。
つれていった学生に頼んで、回りに埋まっている石を一つ掘り出したてもらった。
でてきたものを見て、植物生態学者の緑石先生は、
「こりゃ、全く茸じゃないか」と驚いた。
思っていたものより大きく長いもので、取り出すのにかなり深く掘った。でてきたのは直径が二十センチの頭を持った茸形のものだった。長さは五十センチほどある。
境先生は、
「茸棒と呼ばれる、茸に似た縄文時代の出土品がこのあたりの遺跡からでている。石でできていて、祭祀に用いられたのだと、考えられているが、茸棒はこの遺跡のものよりもっと単純で、頭と下の部分で太さに変わりが少ないんだ、どちらかというと男性の陽物に近く、それじゃないかという研究者もいるんだよ、だけどこれは明らかに茸だね、傘の裏に襞まで彫ってある」
手にとって驚いている。
他の県の縄文遺跡から茸の焼き物が出土しているが、形から言えばそれに近い。ここのものは形や大きさが一定で、しかも石でできている。
「縄文人は茸をかなり大事な食料、もしくは薬として使っていたから、もし縄文人が作ったものなら、大きな発見になりますね」
境先生は驚きを隠せない。
「もし宗教がらみの施設なら、縄文時代の宗教ということになり、大変な発見ですよ、その頃の宗教については証拠があまりありませんから」
「そうですね、是非、我々の大学で発掘をしたいものだな、どうです、三橋先生、中心になっていただいて研究グループをつくりましょうよ」
「僕も仲間にいれてもらいたいな、縄文時代の茸にまつわる話はおもしろいですからね」
第一発見者の緑石先生も興味心身である。
ということで、
その日、全体図を詳しく書き取って、写真を撮った。掘り出した茸の石柱を元に戻し大学に戻った。
本格的調査のために、町の教育委員会に連絡をし、大学にも報告して、夏休みがあけてから、詳しい調査を始めることにした。
夏休みも終り九月の半ばになり、「円形茸遺跡の発掘」とタイトルをつけ、撮影した写真を添付した書類を、私自ら原村の教育委員会にもっていった。
原村地域の教育委員会は遺跡の調査には力を入れている。もちろん諸手をあげて協力をしてくれることになった。町にはよく知られた縄文時代の住居跡の復元などがあるが、その上をいく発見になる可能性があり、日本中がふたたび注目してくれるのではないかと期待された。教育委員会のほうから、県の教育課に連絡も行き、地元のアマチュア考古学者たちに声もかけてくれて、協力の段取りをとりつけてくれた。
アマチュア考古学者たちの活動力には専門家とは違った、余計なものにとらわれない自由で強いものがある。我々研究者は会議やら論文書きやら、研究費申請やら一般向けのイベントの準備やらあり、調査に割く時間がとても少なくなっている。アマチュアはともかく掘って、新たなものを掘り出す喜びを第一の目的でいどむ。われわれの集中力とは違ったエネルギーが渦巻いている。遺跡の多い原村には何人も野アマチュア研究者が居るという。
実際、この円形茸遺跡も彼らの協力があって、不思議なものの発見につながっていったのである。
それからすぐ、境先生と私の研究室の助手と大学院生、それに卒業研究生もつれて、三日の発掘を行う計画をたてた。村の教育委員会や県の法からの許可も下りた。総勢十五人ほどの小部隊である。卒業研究生の発掘の手法の勉強でもある。
工学部の村吉先生のところから、地上から地下に埋まっているものを探知できる機械を借り、操作できる大学院生も一人参加してもらうことにした。円形茸遺跡の地下に何かあるかどうか、調べてみる必要があるからである。
地中の中の構造を地上から探索できる機械が日本で開発された。我々の大学の村吉先生が開発に携わっていた。すでにエジプトの墳墓の探索にはその機械が用いられていて、砂漠の中に隠れていた太陽の船や新たな墓がみつかっている。
こうして二度目の調査が開始された。原村の近くの駅のホテルや宿に宿泊をし、9時から作業を始めた。少し寒いくらいの気候で、林の中には茸がたくさん生えている。茸の多い場所である。
最初の日の午前中は、地下探索機で直径二十メートルほどの遺跡の表面をスキャンしてもらい、地下の様子をコンピュータの画像に映し出してもらった。驚いたことに、端から直線でスキャンしたところ、端から五メータほど中に入ったところから、地下に石でてきていると思われる硬いものが映し出され始めた。それは地下五メーターほどのところにあり、全体をスキャンし終わると、石造りの円形物が埋まっていることが分かったのである。これにはみんなおどろいた。
教授の村吉先生に電話したところ、すぐデータが見たいということであったので、ネットで送った。それから一時間もしないころ、村吉先生から、埋まっているものは直径十メーターほどの円柱状のもので、おそらく中は空洞化、部屋のようになっているのではないかと言ってきた。
またまた、驚くことである。
スキャナーの結果が出てから、総出で発掘がはじまっていた。
表面から五メーターしたまで、境研究室の土壌サンプラーサンプラーで採取した結果、表面はそのあたりの林の中の土と同じ年を経た腐葉土だったが、その下したにはとてもきれいな均一な赤い土の層があらわれた。関東ローム層、すなわち富士山の噴火により堆積した土である。その下は石室まで黒っぽい土でやはり腐葉土が固まったもののようであった。
土には貴重な人の活動の証拠品が埋まっている可能性がある。丁寧に掘っていく必要がある。スタッフが一列になり、土を五十センチ四方にかきとり袋につめていく。そこに村吉先生からの石の円柱状の建築物が埋まっていることをつたえると、発掘をしている学生諸君をふくめ、おどろいて作業が早くなった。誰もが五メートル下の石の建造物を見たいと思ったのである。私は、
「丁寧に彫ってくださいね、円柱状の石の建造物は、これから石室と呼びます」
遺跡の表面を覆っている土は林の中のものと同じだが、一メートル下の土は赤土になってきた。
円柱状のものは五メートル掘らなければ現れない。とても三日では無理である。三日目、三メートルほど掘ったところで、ブルーシートをかぶせた。袋に入っている削り取った土は番号がふられているので、遺跡の脇に並べた。
終りにするにあたって、茸の形をした石を一本大学まで車で運ぶことにした。年代特定してもらうためである。同位元素の放射線量を測定してもらう。
茸の形の石の測定を依頼した研究所からはすぐに返事が来た。今から八千年ほど前のものだろうということである。ということは初期の縄文時代に遺跡が造られた可能性がある。その時代には古墳などはなかったと思われるので儀式にでも使われていた場所と考えたほうがいいのかもしれない。それには円柱状の石室の中を覗いてみなくてははじまらない。
本格的な発掘が始まる前に、周辺地域を調べていた一人の遺跡マニアが隣の山の中腹に同じような円形の丘をみつけたという知らせがあった。まわりを広く調べるべきだと主張していた男である。本人は原村でペンションを経営しているのだが、ほとんどを奥さんに任せて、遺跡探しに情熱を手向けているという。
とりあえず、境先生と原村の教育委員会に出向いて、その人と会った。
見つけたのは早川紀夫という、本格的な発掘マニアである。経済学出身でどちらかというと文学少年であったらしく、SFを読みあさった結果、異星人の足跡を探すことから考古学に目覚め、遺跡の発掘の楽しみを知ったという経歴の持ち主である。
「境先生のご本は読みました」
境先生の縄文人の本は研究書であるが、わかりやすく、マニアの人なら必ず呼んでいる。
「総括をしている民族宗教学の三橋です、すごい発見されましたね、現場に行きたいのですが、これからいいですか」
「あ、三橋先生、教育委員会からきいております、私は自分の車でいきますので、ついてきていただけますか」
ということで、境先生を乗せて、私の車で早川のくるまのあとについた。
円形茸遺跡のある丘の中腹の道を少し下り隣の山の中腹まで、車でほんの十分ほどのところに、その遺跡はあった。
車を降りて、雑木林の中をほんの五分もくだっていくと、円形茸遺跡とよく似た円形の草地があらわれた。周りには木々が生えているが、そこだけ草地である。南のほうの木の間から遠くが望めるような南向きの遺跡だ。ということは、最初に見つけたのと、地理的条件がよく似ている。
円形の草地も直径が二十メートルほどで、ほぼ同じ大きさ、早川さんが指差したところを見ると、おそらく茸形の石の頭だと思われるものがある。やはり遺跡をかこんでいるようである。
「二つあったら、もっと見つかるかもしれないですね」
見つけた早川紀夫は日に焼けた顔をほころばせて言った。年のわりにはきれいな歯並びをしている。
「そうかもしれませんね、これ大変な発見ですよ」
境先生も賞賛した。
「円形茸遺跡がいくつでてくるか、楽しみですね、二つあるということは、その当時、大事なものが複数あって、一つはここの中にあるということです、第二円形茸遺跡の、茸形の石の年代測定をしてもらいましょう」
「今掘り出しましょうか」
五十センチほどの長さだからさほど時間はかからないだろう。彼は折りたたみのスコップを持っている。
「おねがいできますか」
彼はてなれたもので、五十センチほどの茸形の石を簡単に掘り出した。
「最初の遺跡のものとほとんど同じですね、きっと同じ時期に創られた可能性もありますね、だけど、この第二の円形茸遺跡を発掘するには、最初の遺跡の解析がある程度すすんでからだから、だいぶ後のことになるとおもいますよ」
「そうですね」
「縄文時代には墓をつくらなかったのですよね」
「早川さんはよくごぞんじですね、縄文人は死んだ人を、そのまま住居の脇に埋めて石などをならべていたようです、石を並べるということは、死に対して悲しみや、恐れや何らかの感情をもっていたのでしょう、だけど、墓というものをつくっていないようですね」
境先生が答えた。
「このあたりには縄文人の住居跡は見つかっていませんね」
私が早川さんに聞くと、うなずいて、
「すぐ近くにはありませんけど、少しはなれたところにはあります、このあたりも縄文人は歩いていたことだと思います、狩猟や茸狩り、木の実の採取、いろいろあったとおもいます」
よく周りの状況を把握している。さすがに年季の入ったマニアである。
第二円形茸遺跡の茸形の石を持って帰り、また方位元素による年代測定をしてもらった結果では、ほぼ第一遺跡と同様の、八千年前のものということになった。
本格的な第一円形茸遺跡の発掘調査が始まったのはだいぶ後になってからである。もうすぐ十一月になろうとしているときである。
円形茸遺跡の上には大きなテントがかぶせられた。
ここの発掘のための研究費も県からおり、ボランティアにもいくらかの費用をわたせることになった。まず石室の上の土を採取していくことである。すでに関東ローム層の部分まで露出されている。あと二メートルほど掘れば石室に達する。そこから前と同じ手法で、それぞれが、五十センチ四方に堀って、土をビニール袋に保存した。
午前中、関東ローム層の赤土もとりのぞかれ、その下の黒い土もとりのぞかれた。とうとう石室の屋上が現れた。石が組まれてできている。
ここで休憩、ボランティアの人たちは木陰でお茶を取り出している。境先生が学生に声をかけた。
「石室の上にあつまって、石の組み方などをよくみておいてね」
「何の石ですか」
「もう少しきれいにしないと分からないけど、御影石かもしれない、御影石は鉄より硬いとも言われているけど、重いんだ」
そのとき後ろのほうに居た女子学生が手を上げて言った。
「先生、ここに白い石がたくさんあります、なんでしょうか」
「なに、ちょっと拾って持ってきて」
境先生にいわれ、その女子学生は屈んで、それを拾うと、
「歯みたいです」
といってもってきた。私も見ると、確かに人の歯である。
我々も女子学生がそれを拾ったところに行くと、石室の外側の黒い土の中に白いものが点々とはいっていた。
「なんでしょう、石室の脇も土の採取をしたほうがいいですね」
私が言うと、境先生も、
「もうひと踏ん張り、石室の周りの土を採取してください、今日は表層だけでいいです」
ボランティアと学生に声をかけた。
ふたたび、彼らは土の採取をはじめた。
一時間かからないうちに、石室の周りが五十センチ掘られた。
「集まった土のなかは歯だらけだ」
「これがこの遺跡のなぞをといてくれるのではないですか」
境先生は少し興奮気味だった。
まだ下には歯の入った土がある、これから石室を露出させるにも、すべての土を丁寧に採取していく必要ができた。
深さごとに歯の状態を調べ年代を特定し、遺伝子が調べられれば遺伝子調査をする。年代と歯の来歴を調べるわけである。縄文人の専門家と歯科医師も解析チームに入ってもらう必要がある。この発見はかなりセンセーションなものになるだろう。
それから毎日石室の周りの歯の入った土をほりだしていった。三日後の午後には、周りの歯の入った土はすべて取り除かれ、円筒形の石室が現れた。石室は高さが四メーターほどで、石が積み重なってできていた。やはり御影石のようだ。入口が北のほうにあったが、石でふさがれていた。
円形遺跡の周りを囲んでいた茸形の石の下には、ずいぶん欠けてはいるが、石でできた塀がでてきた。石室は石でできた塀に囲まれ、塀の上部に茸形の石が載せられていたようだ。塀の北側には途切れたところがあり、ちょうど石室の入口と一致するところで、そこから人が出入りしたと考えてよさそうだ。
塀の高さは石室より三メートルも高いもので石室を完全に隠すような形になっている。塀と石室の間に歯が埋まっていたということは、塀の中に歯を捨てたということになる。大きななぞである。
次は石室の中を調べなければならない。
遺跡の全体像がみえたところで、村の教育委員会とも協議をかさね、地元の放送局の協力を得て、内部の調査をすることになった。
石室の入口は石が積み重なってふさがれている。石を取り除いてく必要があった。しかし、機械でいきなりどかして開けると、密閉されていた空間に外気がいきなりなだれ込み、中の状態に変色を生じさせてしまう危険がある。まず中の様子を微小のケーブルカメラを挿入して中を見る必要がある。専門の業者も加え、入口の前に詰まれた石の間からケーブルカメラを入れた。
何度か挿入して調べた結果、二階建てのようで、一階は七十平米ほどの広さで、二十坪ほどになる。四十畳ほどの広い部屋である。石室の入口から広い部屋になり、壁にそって石段があり、二階にいけるようになっていることが分かった。
モニターで周りの様子を見ると、石の壁にそって椅子のように飛び出した部分がみえる。腰掛のようだ。真ん中にかなり大きな石棺の形のものが置かれており、周りに石でできた椅子が並べてあった。棺としたら回りに椅子を置くなどおかしい。何かの儀式だろうか。
二階の様子を知るため、二階部分の詰まれている石の隙間に小さな穴をあけケーブルカメラを挿入した。
二階の広さは一階と同じである。天上が高く、壁の一部には棚があって、白い布に包まれたものがきれいに並べられている。頭の中に浮かんだのはエジプトのミイラである。だが大きさは三十センチほどで、人間ではないだろう。とすると動物のミイラかもしれない。
部屋の床には広い石の台が置かれていて、石臼や、木製のものが見える。ミイラを作る作業場のような感じを受けた。
壁に文字らしきものや絵はない。壁や床の石はよく磨かれていて、入ってみないと、石の種類はわからないが、よく手入れをされている。
内部の空気のサンプルを採取し、ケーブルカメラを入れた穴はふさいだ。
そういった作業が進められているときに、歯科医師たちによる歯の解析結果が報告されてきた。おどろいたことには、すべてといっていいほど虫歯だったということである。
虫歯を石の建物と塀の間に捨てていたのだろうか。
我々はこの結果を村と県の教育委員会とともに記者会見を開いた。
虫歯に埋まっていた縄文時代の石の円筒形の建物、二階には何のものか分からないが、ミイラが納められている棚がある。そのような遺跡は日本で今まで見つかっていない。
各テレビ局はニュースとして、日本中に発信した。この反響はすごいものがあった。
文科省も本格的に動き出した。ここから第二円形茸遺跡の解析も始まった。
どちらの遺跡にも、すべてを覆う大きな建屋が作られ、その中で作業が進められることになった。特に第二遺跡の発掘も、たくさんの人が投入され、急ピッチで進められた。
第一遺跡のほうは、すでに石室が掘り出されている。建屋ができて温度と湿度の調節がしっかりできるようになったことから、中に入る計画が立てられた。遺跡が発見されて半年である。
翌年の三月の末、第一円形茸遺跡の石室に入ることになった。私と縄文時代の専門家の境先生、大学院生一人、それにNHKのカメラマンである。8Kで撮影することになったからだ。
石室の屋上に載せた小型起重機で石をどけると、中をのぞくことができた。意外と乾いた空気が顔を打った。カビ臭さもなく、我々は部屋に進んだ。
見回すと照明ランプが照らし出した壁は一万年近い歴史があるにもかかわらず、石が磨かれ、つるつるしている。おどろくほど綺麗な状態が保たれている。
壁に作りつけられた長い椅子は今では中学生が座るとちょうどいいほどの高さのものだが、縄文人にはちょうどいいものだっただろう。この部屋に縄文人が並んで腰掛けている様子を想像すると、なんだか不思議である。
中央にあった長方形の石棺のようなものは、上に蓋が乗っており、とても大きな棺といった感じである。石棺そのものは床に置かれているのではなく、同じ大きさの石の台にのせられていることがわかた。台の脚には茸のレリーフが施されている。彩色はされていない。石棺の周りには椅子があるが、よく使われたものと思われ、磨り減っている。
壁に沿ってある石段を登り、ミイラのある二階に行った。
ミイラのおいてある棚は二箇所あり、向き合っていた。高さ五十センチほどの石の棚である。白い布に包まれたミイラはどれも長さ三十から四十センチのもので、棚に立てかけられていた。
丁寧に写真を撮るようにいって、私はその棺の上の棚の白い布に包まれたものを一つだけ、密閉容器に入れシールドをした。
我々はそこで終了し、そとにでた。
石室の入口はもとのように石が積まれ閉じられた。
ミイラのような布に巻かれたものはミイラを長年研究していた寒川輝男博士の科学博物館の研究室にもっていった。寒川先生は世界中のミイラを調査してきた人である。
ミイラを開くときには私も見に行った。
寒川先生は白い布に巻かれたものを見ると
「ミイラだとしても動物ではありませんな、おおよそからだの形がわかるように、特に顔はわかるように布を巻くものですよ」
と言って気密容器からミイラをだすとエックス線透視の機械にかけた。
モニターに現れたものを見て、どうしてとこれが、と複雑な気持ちになった。
茸だ。人でも他の動物でもない、植物でもない。
「うーん、なんだ茸か、だが、萎びていない状態だ、茸をこのような状態で保存するのは相当な技術がいるだろうな、どうして茸をミイラにしたかということは遺跡の謎解きの鍵になるでしょうね」
寒川先生もそう言った。
「茸をミイラにして埋葬することもあるのですか」
「私の研究人生でそのようなものに出会ったことはありませんね、この社会では茸が相当大事な役割をしていたのでしょう、大体ミイラとは内臓を取って、干して腐らないようにしたものですよ、これは違う、中身は採った時と変わらないように保たせているものですよ、ミイラと逆です、使うために新鮮な状態でほぞんしたものです」
「この石室の回りには無数の歯が埋められていました」
「報告書は読みました、歯というものはたまに遺跡からでるものですが、一つ二つですな、ここのはすごい数だ、しかも虫歯でしたな」
「それも謎なんです」
「茸を虫歯の薬として使ったのかもしれない」
「そうですね、茸の種類の特定と、含まれるものを、茸の専門家にたすけてもらうことになりますね」
「科学博物館の茸の部門に紹介しましょうか、解析してくれますよ」
「それはありがたいです、お願いできますか、うちの大学の生態学の緑石先生が、茸に詳しいので、いっしょにおねがいします」
こうして茸のミイラの解析は科学博物館にお願いして、緑石先生が中心にはじまった。
ミイラと言えばエジプトだろう。エジプトには百いくつものピラミッドがある。紀元前2600年代から、紀元前2100年代の500年ほどの間に作られている。単純に計算すれば五年に一つ作られたことになる。ピラミッドの役割は葬られた王の魂が天に昇るため、めされるためとかいわれている。
墓の中の主人公は王だったり王妃だったり、王子だったりするが、ただの骨ではなく、ミイラになった状態で棺の中にいる。天にいっても魂のもどるところを残しておくという考えのようである。そのためエジプトではミイラを作る技術が格段に発達した。人間のかたちをとどめるべく、くさりやすい臓器を取り外し壷にいれ、体は防腐処理をして、布を巻き付けている。防腐処理をするのに使われた植物からとられた薬がマミーに近い発音で呼ばれていたことから、処理をされたものをマミー(mummy)と呼んだとある。日本語でミイラである。
エジプトでは生活をともにしていた猫や家畜までミイラにされていた。戦の道具や服飾品も一緒に埋葬された。来世の生活がすぐできるようにということだろう。しかし植物や茸までもミイラにしていない。
羊のミイラを作る石の台をエジプトに調査にいったときに見た。そのときミイラに詳しいエジプトの研究者が人をミイラにするには70日もかかると言っていた。
日本ではミイラづくりが行われていた形跡はない。断食のまま死んだ僧侶がミイラ化、いうなれば蝋化したものが発見されているが、ミイラとして作ったものではない。
日本の神道では死んだ体は重要視していない。墓は作るが遺体は別のところに埋葬して忘れられてしまう。しかしまだ神の威光が輝いていない大昔は日本でも墓、ピラミッドに相当するものがあった。支配者たちは大きな墓を作ったものである。世界遺産に登録されている古墳がそうである。古墳にはそのころの天皇などが眠っている。しかしミイラにはなっていない。縄文時代に自然信仰はあったのかもしれないが、系統だった宗教らしきものは形作られていなかったではないようだ。ともかく、八千年年もの前に布に巻かれた茸がつくられていた。ミイラでないにしてもセンセーショナルなことである。
それから一週間後、石室の二階にある棺の蓋を開けることにした。ここには本当にミイラがあるかもしれない、という想像もあった。そういうこともあり、寒川博士と助手の方にも一緒にみてもらうことにした。まず二階からだ。
二階の壁のミイラようの茸を見た寒川博士は感嘆の声を上げた。
「すごいね、形からすると、みな同じように茸かもしれないですね」
「調べるには、小型の持ち運び型のレントゲンが必要です」
助手が答えている。
「今度それを持ってこよう」
それから下にもどった。
寒川博士は石の棺を見て言った。
「これはふつうの石じゃないない塗ってある」
ただの石だと思っていた私は驚いた。
「どういうことです」
「石英が吹き付けてある」
「石英だともっときらきらしませんか」
「長い年月で曇ったのだと思いますね」
「でもなぜ塗ったのでしょう」
「中のものが答えの鍵になるでしょう」
石の棺は長さが百八十センチ、幅が九十センチ高さは六十センチほどである。
蓋をあけるための道具を持ち込んで、寒川先生の指導の元に若い人が動かした。厚く重いものと思っていたのだが、以外と簡単に動いた。ふつうの石だと思っていたのだが、内側からみると水晶で作られていることがわかった。細長く板状にした水晶をくっつけて作ったものである。
「水晶だと中が見えるが雲って見えないのは、わざわざ石英の粉を吹き付けてある」
水晶の蓋はすぐに動いた。開けてみると布に巻かれたミイラがよこたわっていた。今度こそ本当のミイラか。
「これはミイラだな、きっと縄文時代のミイラだ、縄文人のミイラだとすると貴重なものになりますよ」
寒川先生はうれしそうである。
丈は140センチほどで、そばには副葬品らしきものがいくつかあった。ということは、円形茸遺跡は墳墓でもあるようだ。
「日本にもミイラがあったのか」
「三橋先生、容器は用意してありますが、このミイラを外にだしていいのですか」
「はい、ミイラチームにお任せしますので、解析をお願いします」
「副葬品は赤く塗られた木でできた茸の形をしたものです、3本あります、太さが違います、何に使ったのでしょうね、さらに石臼の小さいものと、いくつかの土器がおいてありました」
「私の想像では、この墳墓は茸を虫歯の治療薬にした人の墓だろう。痛みをやわらげてくれる人でうやまわれていたのではないだろうかね、茸は痛み止めかもしれない」
寒川先生の言うとおりだろう。の解析も早くしなければならない。
最初の円形茸遺跡の発見から一年になる。かなり解析はすすんだ。第一円形茸遺跡の石棺の中の人物の解析はだいぶすすんだ。布に巻かれていたのは女性で、年齢は三十代後半だろうと推定された。当時で言えば老年になりかけた年である。ただ、自然のミイラで、断食僧がそのままなくなったのと同じような状態ということも分かった。内蔵はとり出されていない。人工的なエジプトのミイラとは異なり、亡くなってから自然にミイラ化した女性を埋葬したという結論になった。特筆すべきことは歯が全くないと言うことである。全部抜けている。それだけではない、ひからびた胃から歯が見つかったのである。
胃の中の歯の遺伝し解析が行われ、自分の歯であることがわかった。死んでから歯が抜かれ、胃に詰め込まれたのか、なにかの儀式の結果の可能性がある。女性が干からびた段階で、あらためて布を巻いて棺に安置したということかもしれない。
ミイラと一緒に棺にはいっていた木でできた茸の形をしたものは、長い間使われたもののようである。その女性が仕事に使ったものだろう。石臼は中に茸の破片が残っていたことから、茸を粉にするために使っていたことが明らかになった。
布の解析もされたのだが、麻のようで、茸を巻いたものと同じである。縄文時代に麻による布はつくられていたという。その中でも最も古い出土品となる。
茸のミイラに関してはなかなか解析がすすんでいない。まず茸の特定から始められたが、現存する茸に同じものはないだろうということがわかった。またレントゲン検査では石室内の茸はみな同じもののようだ。遺伝子の解析では、紅天狗茸の系統のものだろうということである。
早川さんの精力的な調査にもかかわらず、第三の円形茸遺跡は発見されなかった。
第二の遺跡の発掘は終わっており、第一の遺跡とほぼ同じものが表れた。石の塀に囲まれた円筒形の石室である。周りには虫歯が埋まっていた。室内の構造はほぼ同じ、入口も北にあった。一階には石棺があり、二階は茸のミイラつくりの作業場のようであった。
石棺の中もやはり寒川先生が調査をした。そこからでてきたものは、男性のミイラだった。この男性も死んでそのままミイラ化したもので、腹の中には自分の歯がいくつも入っており、歯はすべて胃の中にあった。
宗教歴史学をやっている立場としては、とても興味のある遺跡だが、なかなか縄文人の宗教にからめて結論を出すのは難しいことである。
生態生物学者で最初の発見者である緑石先生とはよく話すが、彼がいうには、動物は二つの基本的な本能があり、それは体の維持と子孫の維持で、体の維持のためには食べると言うことが最も重要なこととなる。そのために動物は体の中で一番堅い組織である「歯」をもつことになったわけで、虫歯になって抜かなければならなくなると、縄文人は心配して、他の歯はそうならないようにしようと心がけたはずだという。
この指摘は私にはとても重要で、彼に感謝をしているわけだが、虫歯になった縄文人はきっと虫歯にならないように祈ったと思われる。祈るには祈るものが必要である。それが茸なのではないだろうか。それを司っていた司祭などがいてもいいわけである。
この発見は世間に驚きをもたらしたことは確かなのだが、専門家のあいだで、ミイラになった人間の素性や、歯が胃の中から見つかったことの意味は、解釈がさまざまで結論に至っていない。
まだ未解決のままのことが多いが、発掘チームで議論した記録があり、この中からいつか結論が導き出されると思う。そういったこともあり、ここに議事録があるので、そのまま提示したい。
出席者は、発掘を実際に行ったチーム、この地の専門家である早川さん、歯の解析にあたった歯科大学の蒲田先生、ミイラの解析チームの寒川先生、茸の解析の中心である緑石先生、それに縄文人の専門家の境先生、地質解析チームの石田先生、宗教解析の私である。それに関係した大学の学生たちが聞きにきた。
三橋:お集まりのみなさんと、得られたデータを基に、この遺跡の役割を推察したいと思います、最初に遺跡のある場所について、地質研究チームの石田先生にご説明をお願いします
石田:一号遺跡は標高五百メーターほどの山の中腹にあります。そこの県道そのものがすでに海抜二百五十メーターですからそこからちょっと上った海抜三百メーターほどのところにあります。第二遺跡の方は隣の山の中腹で。やはり海抜三百ほどのところです。二つの遺跡を地図上で見ると直線距離だと百メータほどしか離れていません。もし林でなかったら、下の方から見ると遺跡がならんでみえるでしょう
三橋:縄文人の専門の浜田先生、遺跡の近くに縄文人の住んでいた場所は確認されているのですか
浜田:いえ、あのあたりにはありません、かなり離れている、もっと麓の日当たりのいいところにあります
三橋:歩いていけるところでしょうか
浜田:はい、ただそんなに近くというわけではありません
三橋:とすると、遺跡の石室というのは、貝塚のように人々の毎日の生活に密着していた場所ではなく、特別なときにおとづれた、または使われたとところと考えていいですね
みながうなずいた。
三橋:住居からしっかり見えた可能性があるとすると、あの遺跡は敬われていたと思います。遺跡の役割につい関係すると思いますが、世界でも珍しいことは、石室のまわりに歯が埋められていたのです、歯について鎌田先生にお話しお願いします。
鎌田:松本歯科情報大学の鎌田です、このような解析をしたのは初めてです。埋まっていたものがいつ頃の歯か、どのような種類の歯か、調べられる限りのことをしましたので報告します
鎌田医師はスライドを使いながら話を進めた。
鎌田:まず、数ですが、53万9781個でした。一番下の土の中にあった歯の年代は7から8千年ほど前のもの、上の方にあったのは6から5千年ほど前のものです。歯は今の人と比べるとすこし小さめです
境先生がそれは縄文の後期のころですねと補った。鎌田先生は続けた。
鎌田:1号遺跡の歯は82パーセントほどが虫歯や壊れた歯で、18パーセントは虫歯になっていないものでした。2号遺跡では虫歯でなかった歯が25%ほどと高く、歯の磨耗度は1号遺跡より強いものでした。
緑石:虫歯ではないのに捨てられたのは、何かで抜けたのですね
鎌田:そうですね衝撃、すなわちぶつけたりして抜けたりした可能性はあります
境:縄文人は戦いをあまりしなかったですよね、海や山での狩猟で生きていたので、そういうところでの事故でとれたのかもしれませんね
鎌田:言い忘れました。1号遺跡の歯はすべて、女性のものでした。一方で、二号遺跡のものは、すべて男性のものです。二号のほうの歯の磨耗度が高かったのは男性のものだったからだと思います。
みなの間にどよめきがおきた。
三橋:面白いですね、一号の石棺には女性のミイラが、そして、周りには女性の虫歯が埋まっていて、二号の石棺には男性のミイラが、周りには男性の虫歯、そのあたりに、この遺跡の役割が明らかになると思います。
鎌田:歯科医として、とても興味を引いたのは、縄文人が虫歯をどう考えていたのかです、縄文人の歯について全く知識がないのですが、どなたかおしえていただけませんでしょうか
それには境先生が答えた。
境:縄文人の歯の論文にあたってみたのですが、縄文人はとてもよく歯を使うので、すり減っていただろうと思います。歯周病にはなっていたようです、本州では虫歯はあったようです、北海道の縄文人には虫歯があまり見られなかったという報告もあります
鎌田:このあたりの縄文人は虫歯が多いということになりますか
境:そうですね、その傾向はあります。理由はわかりません
三橋:あのあたりの縄文人に虫歯が多く、虫歯の痛みや、虫歯そのものをマネージしてくれる人がいたとしたら、敬われたでしょうね、それで古くから,神のように慕われた人のために石室が作られた。
何人かの人がうなずいている。寒川先生が発言を求めた。
寒川:そうだとおもいます。石室のミイラについて詳しく報告しておきます、一号遺跡の人のミイラは女性、身長は百四十五センチ、紀元前三千年、今から五千年ほど前でした、二号のミイラは男のもので、慎重百五十五センチ、こちらも紀元前3千年よりちょっと古そうですが、一号の女性とたいした差はないと思います、身長は縄文人として平均的なものです。石室そのものは紀元前六千年、今から八千年前に作られています、茸形の遺跡の周りの石と同じころです。
三橋:とすると、縄文時代の初期、八千年前に石室が作られ、その周りに茸石の石垣が作られた、その頃から虫歯を石室の周りにすてた、それがたまりたまって、積もって、石室をうもれさせてしまった。
これは私の専門からの想像ですが、作られた当時は虫歯神として敬われた男と女がいた。石室をつくらせ、その中で、縄文人に痛みを抑える祈りをあたえた。抜けた歯を回りに捨てさせた、祈りだけではなく、なんらかの痛みを抑える薬などを考えることもした。何代目かの虫歯神である男女が、茸に鎮痛効果があることを見つけ、縄文人たちに処方した。鎮痛効果のある茸を見つけたのは三千年前、ミイラにされ石棺の男女かもしれません、そのあとも、後継者たちが虫歯の手当てをおこなった、そういった遺跡かもしれません。
寒川:状況証拠からしますと、三橋先生の推測は正しいかもしれません、痛みを抑える祈りの場であった石室は、三千年後に墳墓の役割が加わったということだと思います、だから祈りの場であったところに石棺があり、その二階に鎮痛剤である茸のミイラが保存されていた、ということではないでしょうか
境:石臼で茸を粉にして虫歯の痛みを抑えたわけですか。
緑石:その可能性はあると思います。ミイラの茸を科学博物館と一緒に解析したのですが、紅天狗丈に近いのですが、成分は必ずしも同じではないようで、まだわかっていません、それに何千年もの間干から微図に保存されていたのはどうしてか、まだわかっていません。今布に含まれものの解析をお願いしてあります。
三橋:紅天狗茸だとマジックマシュルームの中間ですか
緑石:マジックマッシュルームは笑い茸のなかまで、紅天狗とは違う種類です、笑い茸の成分のアルカロイド系のシロシビン、シロシンは毒性が強く幻覚、麻酔作用がありますが、紅天狗は神経伝達物質のギャバの受容体に作用するムシモールやイボテンサンをもちます、作用はやはり催眠、幻覚ですが、毒性はかなり弱いものです。ミイラの茸は紅天狗茸の仲間ですが、マジッックマッシュルームと同じ成分も持っています、
三橋:とすると、睡眠作用、幻覚作用が現存の茸よりもっと強いということですね
緑石:はい、そうです
境:マジックマッシュルームは古代から儀式に使われていて、アメリカやアフリカでは茸の形をした石がでています、日本でも茸の石は縄文遺跡からは大分でています、ただ、日本の場合に茸がどのように使われていたかわかりません、茸の石そのものは祭祀に使われていたようです
鎌田:お話を聞いていると、麻酔をかけて歯を抜くことを思い出します。虫歯が痛くなったとき痛み止めにつかったわけでしょうか
境:縄文人が歯を治療したという証拠は今まで見つかっていませんが、このあたりは縄文時代も茸がたくさん生えていたのでしょうから、偶然その作用を見つけて、使ったのかもしれませんね
三橋:遺跡は虫歯塚で、石室は治療室で、茸を利用して虫歯を抜いたところかもしれません、歯医者は痛みを除いてくれるありがたい神のような存在だったでしょう。
早川:私も虫歯と聞いたとき、抜歯を考えて副葬品がどのように関係するか、実際に同じようなものを作ってみました
彼は手に持っているものを皆に見せた。ミイラと一緒に埋葬されていた木でできた茸の形をしたものである。それに紐のようなものである。
早川:石の臼で茸をすりつぶし、それを飲ませて、意識がはっきりしなくなったら、木の茸の傘の縁で虫歯をたたく、ぐらぐらになったら、この草の糸で縛り、茸の棒に巻き付けて引っ張る
彼は動作をしながら説明した。
寒川:すばらしい、その紐は茸のミイラをまいていたものですね
早川:はい、麻の仲間から作りました
三橋:歯を抜くのに鉄器を使わなかったのは、患者の気持ちを落ち着かせる為だったのかもしれませんね
早川:そう思います、武器として発達してきた鉄器を口の中に入れられるのは怖かったのではないでしょうか
三橋:とう言うことは、やはり石室は祈りや治療の場所
寒川:そうですね茸の貯蔵所でもあり、その場で治療をした可能性がありますね、あの石英でできた石棺は磨いた水晶の板で作ったものです、はじめは透明だったでしょう、患者はその中に寝かされると、茸の薬効だけではなく、その中にはいることで、別の世界にはいった気持ちになったでしょう、外から見ていて、茸が効いてきたら、蓋をあけて、早川さんが言ったような方法で虫歯を抜いたのではないでしょうか
三橋:とすると、石棺の本来の役割は患者のためで、敬っている歯医者のミイラを中に納めるため出なかったということです
寒川:そういうことになりますね、先生がさっきおっしゃったように、最初に鎮痛茸を見つけた男女の医師ではないでしょうか、女のミイラも男のミイラも、自分の歯が胃の中にありました。それは虫歯ではなかったのでしょうか
鎌田:これも言い忘れました。石棺の中の男女の胃の中の歯も調べたのですが、虫歯ではありませんでした
寒川:ありがとうございました、そうすると、何らかの原因でなくなった歯医者である女、または男は、弟子か後継者によって石棺の中にいれられ、死んでから死の世界でものが食べられるように、木でできた茸の棒で、葉をすべて抜かれ、胃の中に詰め込まれた糖可能性もあります
三橋:それは確かに面白いですね、縄文人が死後の世界をもっていたということになり、新しい解釈です、
そのとき、緑石先生が手をあげて、発言を求めた。
三橋:何でしょう、緑石先生
緑石:今、遺伝子を解析している研究所からメイルが入りました。向こうの先生が、重要な解析をし忘れていたということです、1号遺跡の女性のミイラと2号遺跡の男性ミイラは兄弟の可能性があるそうです、それぞれ違う人が解析していたので、付け合わせてみなかったようです
三橋:としますと、歯医者というか、虫歯の治療をする家系があった可能性がかんがえられます。あの石室を使っていた家系のものですね、縄文時代でも特別な地位の者が居たということでしょうか
寒川:そうなるでしょう、縄文時代の信仰や儀式は、三橋さんの専門、話をまとめていただきたい。
三橋:寒川先生にご指名いただきましたが、何分にも縄文時代の儀式や宗教的なものはわかっているとは思えませんので、ほとんどが推測にすぎないのですが、この遺跡が見つかったおかげで新たな考えをもつことができました、
縄文人は食べる、噛むということを大事にしていたことは、前から指摘されていたことです、縄文人は海の狩人で海辺での暮らしが長かったのは貝塚でもわかることです、一方狩猟も行われていたことも知られていますが、そちらを得意としていた者達は山間で暮らすようになり、茸にも親しむようになったと思われます、茸のうまさ怖さを知り、薬として使うようになった、そのおかげで、虫歯の痛さから逃れる方法を考え出した。茸による麻酔です、発見した者は代々歯が虫歯にならないように祈りをささげていた家系の者だったのでしょう。虫歯を抜くのは儀式だったと思います。遺跡のあたりの縄文人は抜いた歯は皆同じ場所に捨てた。きっと虫歯封じの儀式などもそこで行われたのではないでしょうか。乳歯も捨てられていたところを見ると、大人になっても歯の再生を祈ったりもしたかもしれません。
さて、どうしてそれを執り行っていた二人が、生き仏のように、いきたまま治療のために使われていた水晶の石箱に入り死んだのかということです。治療の箱が棺になり、しかも、透明の水晶で患者の様子を見るものだったものに、粉にした石英をまぶし、中を見せないようにしたのかということを考えてみたいと思います、
寒川先生が二人が死んでから、布を巻いたかもしれないとおっしゃいましたが、別の可能性として、二人はどこかに幽閉され、食事も与えられずに死んで、布を巻かれた可能性や、まだ生きている間に布にまかれ、石室に入れられたなども考えられます。
彼らが何かに失敗をしたとか、悪いことをしたというものです、歯が再生をしなくて怒った地位ある人間がいたのかもしれませんが、それだと、二人同時にミイラにしなくてもいいかもしれません。理由は分かりませんが、ともかく二人は葬られ、不必要になった虫歯の治療室は終りにされたのです。
男女で歯の治療の場所が違ったということは、一緒ではまずいことがあったのでしょう、男の歯と女の歯が一緒だと、再生したときに男に女の歯が生えてくると困ると思ったのかもしれません。
ということは歯を抜く男の術者は女の術者と交わってはいけなかったかもしれません、ところが、術者兄妹でそういう関係になって、民衆から石室に入れられたのかもしれません。
そのころになると茸のことが知られ、虫歯を自分で治療をする者も出てきたことから、歯医者がいらなくなってきたということもあったかもしれません、
これは科学的な根拠があって言ったのではなく、可能性のいくつかとして、まとめさせていただいたものです、発掘された遺跡の解析は何十年もの研究のつみかさねで、やっと一部が真実だと認められるようになります。緑石先生がご家族と共にみつけられた円形茸遺跡は、専門家以上に新しい発見に寄与されているアマチュアの方々、特に第二遺跡の発見社である早川さん、そういった方々の興味と知力が研究を進展させてくださっています。これからも皆さんの助力を得て、考古学が発展することを祈っております。
そこで皆から拍手がおきた。
早川さんが手をあげた。
早川:三橋先生のお話とても面白く拝聴しました、お聞きしたかったのは、あの石室や埋められていた歯に特別なばい菌、ウイルスなどはなかったのでしょうか
鎌田:それも調べたのですが、特殊な菌は検出されませんでした。寒川先生にも真っ先に茸と人のミイラの菌について調べてもらいましたが特になかったということです
早川:ありがとうございました、もしかすると、二人が変な病気になって、閉じこめられたのではと思ったからですが
三橋:もちろんそれも可能性のひとつです、早川さんありがとうございました、それではみなさま、これでおわりたいとおもいます、これからもこの遺跡の解析にご支援ください、ありがとうございました
討論会は終わった。
ところが一年後、大変なことが起きた。
ミイラにされていた茸が、一号二号とも遺跡を覆っている建物の中にたくさん生えてきた。
緑石先生は石室にあった胞子が建物の中に入り、温度湿度が一定に保たれ、石室内と環境がおなじにしてあったため、繁殖したのではないかといっていた。
科学博物館は生きている茸が手に入って大喜びだった。
話はこれで終わらなかった。当初茸の生えている遺跡で発掘調査にたずさわっていた人、茸を研究した人に大変なことがおきた。緑石先生もそうだったが、ある日、朝起きると、みんなの歯がすべてなくなってしまっていた。
しかも病院の検査で、抜けた歯は胃袋にたまっていた。遺跡の石棺のミイラと同じ状態になったわけである。
あの茸の胞子は歯に触れると、歯槽を溶かし、痛みもなく知らない間に抜けてしまう、とても怖いものだということがわかったのである。
厚生省と環境省がミイラ茸の管理に躍起になっている。
私はあれから現場に行っていない、おかげで歯は大丈夫だった。幸い厳重な建物に覆われているので茸の胞子は遠くには飛んでいないだろう。あのあたりは立ち入り禁止になった。
石棺の男女のミイラの胃袋に歯がはいってっていたのは茸にやられたためだ。緑石先生は一つの可能性として抜歯の痛み止めに使われていた茸の性質が長い間に変化したのかもしれないと考えている。
ある日、早川さんがまとめたデータや写真をもって私の研究室にきた。
「先生しばらくです」
「いやこちらこそ、早川さんのおかげであの遺跡の解析が進みました」
早川さんはてっきり歯が全部抜けていると思ったのだが、笑顔できれいな歯を見せて挨拶をした。
「早川さんは歯大丈夫だったのですね」
「ええ、今でも、毎日あの近くで縄文の遺跡をさがしてます、先生はあれから発掘現場に行っていないのですね」
「ええ、まとめるのがいそがしくて」
「先生の歯が大丈夫だったからそう思いました」
「だけど、早川さんはなぜ歯がきれいなんですか」
特異体質で、彼を調べればあの茸の胞子から歯を守る方法がわかるかもしれないと思ったから聞いたのだ。
しかし彼は笑いながら指を口につっこんだ。
彼の手には入れ歯があった。
「総入れ歯です、実はもう十年ほど昔になりますが縄文遺跡探しをしているときに、歯が全部抜けてしまったのです、きっとミイラの茸と同じものが私の歩いたところに生えていたんだと思います」
「国に報告しないといけないんじゃないですか」
私が言うと、早川さんは入れ歯を戻して、
「お任せしますが、私はその茸を見たわけではないし、お国に言うと、茸狩りや縄文遺跡の探索ができなくなりませんか」とまた笑った。さらに「死ぬ訳じゃないし、今の入れ歯はよくなってますよ」と言った。
私はうなずいた。本当の考古学マニアだ。早川さんが暗示しているように国にはだまっていることにした。
信州原村の二つの円形茸遺跡の研究はまだ続けられている。だがまだ何も分かっていないというのが本当のところである。寒川先生は学生に捨てられていた歯の数を数えてもらっている。あそこに何人くらいの縄文人が居たのか知りたいと考えたようだ。
緑石先生は茸の生態学に興味を引かれ、原村によく調査に行く。わたしはというと、縄文人の生命感、信仰について新たな研究にとりかかったところである。
茸のミイラ
私家版第二十二茸小説集「桃皮茸、2026、269p、一粒書房」所収
茸写真:著者 東京都日野市南平 2018-9-17


