 星空文庫の作品リスト 854
星空文庫の作品リスト 854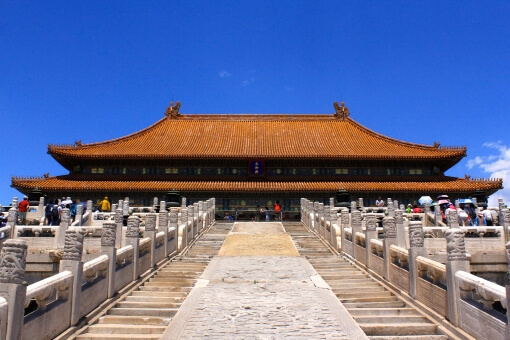
真夏の太陽が降り注いでいた森から一歩踏み込んだ先は、ひんやりとした冷たい闇だった。 固く敷き詰められた石畳に足音がやたらと響く。徐々に涼しいというより寒くなってきた。 声を低くして櫂が振り返った。闇の中に琥珀色の瞳が光る。睨まれた聡は口元を隠した。




子供の頃、「またね」と言う言葉に怯えてました。「またね」は次の日、交わした相手と続きがあるように錯覚すると知りました。「またね」は約束の言葉ではないと思いました。それは、どんな状況に置いてもです。いじめ。突然の死。いつの頃からか防衛する言葉が生まれました。「さよなら」この言葉に続きはなく、錯覚することもありません。そして自然と笑うようになってました。傷つかないために生まれた防御。そこに終わりはないのです。

夢に破れ、人生に破れた男の前に現れた死体は、浴室で静かに腐っていく。彼は死体を神様と呼んだ。まるで胸に刻まれた蝿の王だと、回らぬ頭で思う。