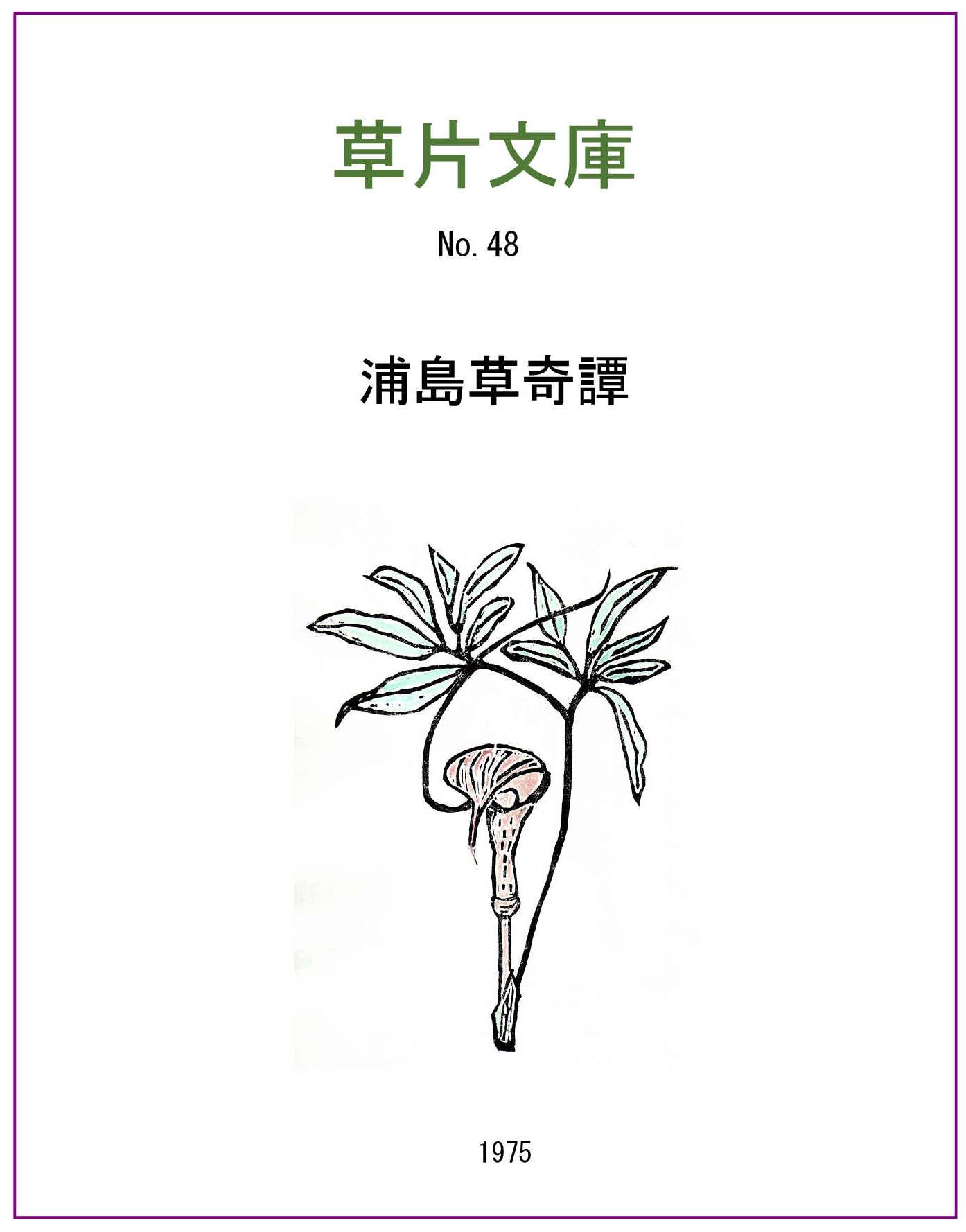
浦島草綺譚
薄木駅の近くに大きな雑木林がある。仕事場に向かう電車の窓から毎日のように見ているのだが、かならずといっていいほどなにか考えごとをしている時で、後ろを振り返り見送っている自分に気付く。
植物の絵を画く商売柄いつかその雑木林を散策し変わった羊歯でも見つけようとは思っていたがどうしてか通り過ぎると忘れてしまう。
それは8月の終わり近くの土曜日であった。新宿の仕事場から早めに切り上げスケッチブックを抱えた私は帰りの電車の中からぼんやりと外をながめていた。夏の太陽と秋の雲がくしゃくしゃにもみあっているような蒸し熱い日であった。小高い丘のふもとを覆っているその雑木林は黒っぽく熱そうに静まりかえっている。私は次の薄木駅で電車から降りた。
線路ぞいの田圃道を十分程歩いただろうか、雑木林をまじかにみるところに着いた。砂ぼこりをかぶった木立が蒸し熱そうに中に入るのを拒んでいる。
静まりかえっている薄暗い林の中をのぞき見ると、思わず身を退け反らせスケッチブックを取り落としそうになった。冷たく湿った空気が私の顔をぬすっと撫で回したからだが、それにしても外のこのぐわんぐわんとした熱さに比べてなんと冷え冷えしていることか。
林の中は背丈の高い下草で被われており道らしきものは見当たらず中に入るのを躊躇していると、ぴちゃっと弾力のある物が私の足に押しつけられた。私はよろっとよろけ、足が縺れて林の中に身をまかせていた。思考が全く空白になってしまった瞬時のことである、犬の鼻が押しつけられたのだとわかるまではかなりの時を要した。転ぶまいとして、手を不格好に振り回わしている私を茶色の老犬が上目使いで見ている。かなり大きな犬で所々薄く禿てこそいるが毛繕いは綺麗になされており、若い頃はさぞ見事なものであったろう。グレートデンに日本犬の血が半分まじっているといった感じだろうか。
老犬は姿勢を取り戻した私の脇を擦り抜けると、生い茂る羊歯の中へ後ろ姿を見せて歩いていってしまった。犬の目が黒でも茶でもなく、青っぽく、いやむしろ緑色に見えたのは空の青と羊歯の緑に惑わされたためだろう。
犬ががさがさと羊歯をかき分けていく音を聞いているうちに、この犬の後を追って行くとどこに行き着くのだろうと興味がわいて来た。犬の目的を探るなどと酔狂なことを本気に考えていたとは自分でも思えないが、私はいつのまにか林の冷たい空気の中へ踏み込んで、犬のあとを追っていた。
林の中をしばらく歩くと砂を被って灰白色を呈していた靴は茶色の地膚を現わした。回りの羊歯は思っていたより背丈があり、キクやセリ科と思われる名も知らない雑草たちも私の下半身を覆うほど成長している。
私の前を歩いているはずの犬の姿はみえない。前方でがさがさと羊歯の葉が揺れ動くばかりである。
足元から乳色の霞が漂い、私をひんやりと包む。陽の光は差し込んでいるのだが、なぜか林の中はぼんやりとしている。振り向いてみると、さほど歩いていないのにもかかわらず、入ったばかりの林の縁が霞んでしまっている。そういえば蝉の鳴き声も鳥の声もきこえない、林の中を歩けば必ず往生する蜘蛛の巣すら一つも見ることが出来ない。静かな林である。
犬は変わらぬ早さで進んでいく。かなり大きな雑木林のようだ、方向を失ったら出る道がわからなくなるのではないかと思うほどだ。羊歯をかきわけていくとそそりたつ一本のブナの木につきあたった。回りの木々よりひと回り大きく根はごつごつと地上にはい、生きもののように羊歯をけ散らしている。
その木を迂回してさらに中に進むとおやっと思うほど景色が変わった。羊歯が主だった下草が大きな笠をゆらんゆらんと揺らした浦島草の群落になった。もう花の時期は終わったであろうに、どの株にも花がついている。ここの浦島草は山蔭で見られるものよりも倍程も背が高く大きい。花が私の腰の高さにまでくるものがある。私はこの花が好きで良くスケッチをしたものだ。濃紫色の壷のような花の中から長い一本の蔓のようなひげが出ており、そのひげがやぶれた笠のような葉に絡みつきふらふらと揺れ動く様は、傘をさしてこの世に迷いでたものに似た感があり、子供の頃はお化けの草だとさわいだものである。本当は釣りをする浦島の姿からこの名が付いたようである。
犬は浦島草たちを乱すことなく進んでいくのに、私の通った後は浦島草の花が頚の骨を折られた頭のようにうなだれてしまう。この花の根には大きな薯がある。お化けのような花の様子から毒があると思い込んでいたことがあったが、本当に毒があるかどうか知らない。浦島草の仲間のまむし草には毒があると思ったが。
随分大きな群落である。どこまで続くのかと気味悪くなるほどだ。
前方の木立の陰に建物らしき物が見えて来た。歩を早めて木々の間を抜けると、古い社のある苔に覆われた広場にでた。石の積まれた礎の上の社の木壁は土に塗れ、朽ち掛けた屋根には草が生えている。石段を上がった入口らしきところは板でふさがれており、社の回りを歩いてみたが、窓もなく中に入れるような場所はなかった。木の壁は土埃にまみれ板の境など見分けがつかない。いつごろ建てられたものか想像がつかないが、かなり古い物である。不思議な社である。
社の前の立ち止まっていると、木の隙間から白い紐のようなものがいきなりでてきた。何だと思う間もなく、紐は私の首筋に巻き付いた。冷たいと思って手で払うと、するっと社に消えていった。土埃が舞い上がった。
何だったのだろう。なにかの蔓だったのだろうか。奇妙に思いながら、社の前の広場を見ると、社の向いに樹齢千年にもなるかと思われる杉の老木がそびえ立っていた。見上げると、上のほうに太い注連繩が掛けてある。明らかにここは神社の境内である。
昔はここで大事な祭りが行なわれたことだろう。浦島草神社、そんな名前がぴったりきそうな社である。
私は腕時計をみた。もう五時近くだ。薄木の駅に着いたのはお昼を少し過ぎた頃であったのに時間が経つのが早すぎる。本当なのか、そろそろ戻って背の高い浦島草のスケッチをして帰ろう。追いかけた犬もどこかに行ってしまった。
私はそう思って帰るほうに足を向けた。その時、浦島草の群落からかさかさと音が聞こえ、葉の間に茶色の耳が見えた。何時の間にやら犬より私の方が先に社に着いてしまっていたようだ。ところがいくら待っても、犬は現れない。犬の歩く音もしなくなってしまった。
私の思い違いかもしれないと、浦島草の群落に向かって歩き始めたとき、あまりにも驚いた。小さくだがあっと声をあげていた。
浦島草群落の中から、紫色のワンピースを着た丸顔のおかっぱ頭の少女が、すっくと立ち上がって、大きな黒い目で私を見た。少女は驚いた私を見ると笑った。そのまま私の前をとおり過ぎ杉の老木に向かった。
われに返り、どこからきたのと喉まででかかった時だ、少女が立ち止まり、振り向き私を見上げぐぐぐと声をもらした。
その顔を見た私は冷えたなめくじが首筋を這い上あがった。からだじゅうの皮膚が縮んでしまい足が震えた。ほほにまで鳥肌が立っていた。
少女の薄く開かれた口の中は真っ黒な虚空であった。歯がない。いや真っ黒な歯が並んでいる。お歯黒。江戸時代、お歯黒は早くても十八前後の結婚直前に行なわれ、既婚者の証しのようなものであったはずである。子供にも施したこともないわけではないらしいが、当時としても一部の階級のそれも例外的なことであったと思われる。
私はふたたび少女を見た。少女の私を見る黒い目は子どもの眼ではない。熟した女の眼だ。
少女はすっと背を向けた。折れそうに細い足を引きずって歩き始めた。林の入り口で出会った老犬の歩き方だ。似ている。犬と少女の目も。
少女は杉の老木の下にくると後ろ向きのまま、樹に向き合いぶつぶつと呟き始めた。呟く重苦しい声は地面を漂い、唸りになり木々の間に響いた。少女の両手がゆるゆると伸び、杉の幹に爪を立てた。幹の苔がむしりとられ、表面には幾筋もの爪の痕がつけられていく。少女が私のほうを向いた。胸が大きく動き、粗い息ずかいをして、のどが引きつっている。
少女の手が腹を抱えた。腹がせり出しはじめ、紫色のワンピースがぴっちりと張り付いた。少女は両足を開き、ふたたび幹にからだを向けると、腹のでっぱりをこすりつけた。いくどもいくども腹を上に下に動かし、杉の幹がぽろぽろと削り落ちた。少女ははーーあーと荒く息をはきだし、時々苦しそうにのけぞる。草の匂がぷーんと鼻を突いた。風が少し出て来た。
呆然と見ていた私はわれに帰った。
その時だった。少女の体が私のほうにむき、杉の根元に崩れ落ちた。太く波打つ日本の根に左右の足をのせ開いた。
風がふいてきた。おかっぱ頭が浦島草の花が揺れるように、右へ左へと動き始めた。
少女の頚の振りが激しくなった。ぎー、と音がした。音のほうを見ると、社の入口の打ち付けられていた板が落ち、開き戸がぎぎぎーと大きな音を響かせてあくところだった。
薄暗い社の中には、天井から垂れ下がった茶色くすすけた二本の布紐がゆるやかに揺れている。後ろになにかいると目を凝らすと、社の暗がりに茶色の老犬が毅然と座っていた。
犬は少女の姿を見ている。鼻の根元にしわを寄せ、人のように笑っている。
少女は社の中をみつめ、両足をさらに大きく広げた。少女の手が杉の根をつかんだ。うわむきにのけぞり、低い唸り声を上げ、それに和したように犬の呻き声が始まった。
犬がぐぐぐぐーとあげたうめき声は私の腹の中へぐうんぐうんとくいこんでくる。
老犬も目を閉じ、口を半ば開き、鳴き声をあげながら左右に揺れる。
少女が目をかっと見開き、弓のようにのけぞりざま、黒い歯を露にして叫んだ。ギャー。犬はそれに和して、わおーんとうなった。
老杉の幹の注連縄がずーんと上から落ちてきた。注連縄は社の前で一度飛び跳ねると太い緑色の蛇になった。
少女の両手に力が入る。少女の叫びは間断なく続く。私の腹がきりきりと痛くなってきた。立っていられなくなり、草の上にしゃがみこんだ。
老犬の腹が膨らんできた。女たちの匂があたりに満ち、草の匂とまじる。この匂はどこかで嗅いだ。そうだ浦島草の匂だ。
くっくっくと痛みを耐える少女に木立から日が差し込み、引攣る顔を浮かび上がらせた。私の下腹がずきんずきんと痛む。
蛇が少女の前で鎌首をもたげた。
犬のからだが麻痺をおこした。少女の叫びが林の中に響く。
蛇が少女の足の間に頭をいれた。
痛い。私は腹を押さえ、顔を上げた。
老木の枝が波打ち、ゆっさゆっさと揺れ、枝の擦り合う音がしいしいと津波のように私の耳に押し寄せてくる。
腹の中で何か動く。下腹の中が噛み付かれた、いたたたたた。苦しさで目を開けると、少女の両足の間に入った蛇はいない。
少女を見た。笑っている。大きなおなかを抱え、両足を前に広げ、なにごともなかったように私を見て、ほほえんでいる。
私は痛さのあまり、目をつぶって草の上にころがった。腹の中にキリが刺さった。私の意識は遠のいていった。
手がこそばゆい。目を開けるとザトウムシが手の甲にいる、足をせわしく動かし腕にのぼり、私の顔をめざしてやってくる。動こうとしてもからだが動かない。ザトウムシをにらんだ。気がついたと見え、ザトウムシはあわてて足を高く持ち上げると、草の中に飛び降りて逃げていってしまった。
空が赤くなってきた。
体が動かせるようになった。ゆっくりと首を上げ少女を見た。
少女は杉の樹の下でしゃがんだまま赤黒いものを手に抱えていた。
社の戸はもはや閉じられ、私がここに来た時と同じように静まり返っている。
杉の老木を見上げると注連縄がもとにもどっている。
少女は両手のものを抱えたままむくりと立ち上がると、私を見てほほ笑んだ。私のほうに向かって歩いてくる。ゆっくりゆっくりまるで夢の中にいる生きもののように歩いて来る。少女はまだ横になっている私の目の前に立った。裸の赤子が私に向かって差し出された。そして少女は黒い口をあけた。
「おとうさま」
私はからだを起こし、やっと声にした。
「どうしたの」
少女は赤子を私に押しつけ、
「見ていらしたでしょう、わたしが産みましたの」
私は手をさしのべ赤子を受け取って立ち上がった。
赤子は手の中で猫のように蠢いたのだが、おぎゃあと泣こうともしない。
「つれてきてくださいな」
少女はわたしに背を向け、無言のまま浦島草の群落の中へ入っていった。
わたしは紐で引っ張られるように少女についていった。
手の中にあるのは生まれたての赤子である。強く握ると壊してしまいそうだ。恐る恐る、だが落とさないように赤子を両手で抱えた。
赤子の小さな手がこそっと動く。臍の緒の切り口に黒くなった血がこびりついている。青い小蝿が赤子の顔のまわりを飛び回わる。自分の顔を近づけて小蝿をおいはらう。浦島草の花がわたしの足で踏みつけられる。首を折られた浦島草の花は死人の首のように垂れ下がる。
少女は振り返ろうともしない。やがて雑木林から出た。青空が広がっている。太陽がかんかんに照っているにもかかわらず熱くない。目の前には伸びた背の高い葦が生い茂り水の流れの音がする。川岸の葦の原のようだ。少女は自分の丈と違わらない背の高い葦をかきわけ進んでいく。わたしは懸命においかける。手の中の赤子はむずむずと動く。
黒い古屋が見えた。壁板は朽ち緑色の苔がこびりついている。
少女は古屋の中に入った。
入口から続く土間には、竈がしつらえてあり、甕に水がみたされていた。角が壊れた敷居を跨いで中に入ると、甕から水をくみ、古びて茶色になった木のたらいに満たした。七輪の上の煮立っている湯を注ぎ入れ、私を見上げて言った。
「子供をいれますの、手伝って下さいません」
とまどっている私に少女の両手が差しだされ、わたしは反射的に赤子を少女の手に委ねた。少女は赤子の両手と頚を抱え、たらいの湯の中に沈めていく。赤子は気持ちが良いのであろう、小さな口を開けて笑い顔になった。肌が次第に赤くなっていく。
「上げますわ。そこのタオルを取って下さらない」
少女は目で、土間の上の板の間を示した。茶箪笥の前に手ぬぐいがおいてある。
上にあがるとタオルをとって少女のところに戻った。
「ありがとうございます、おとうさま」
少女は私の手から手ぬぐいをうけとった。
「さーきれいきれいね」
なれた手つきで赤子を手ぬぐいに包み、はたくように水気をとった。
「お父さま、赤ちゃんを上に連れて行ってくださいな」
少女は私に赤子を差し出した。気持ちがよいのか赤子はうれしそうにわたしの手の上にのった。
少女は上に上がると障子をあけた。畳の間だった。
子どもの布団が敷かれていた。
布団の上に赤子をおくと、すぐにすやすやと寝息をたて、寝てしまった。
「お父さまにそっくり」少女は赤子にタオルをかた。
「お父さまって」
少女はわたしを見て不思議そうな顔をした。
「あなたよ」
少女の目が異様に赤く見えた。
赤子のかんだかい泣き声が古屋の中に響き渡った。
「おなかがすいたのね、おねがいします」
少女は布団から赤子をだきあげ、私の手の上にのせた。
少女は胸の釦を外してはだけると、ふくらみかけた乳房を露にした。赤く熱くなった小さな乳首から黄色い液が滲みでてきた。やがて雫となって畳の上に滴り落ちた。
少女は無言のまま私から赤子を取ると、赤子の口を乳房に近づけた。
赤子は乳に武者ぶり付くと、生まれたばかりとは思えない力で乳を吸う。
自分のからだから力がぬけでていく。どこかにいってしまいそうだ。わたしはなぜここにいるのだろう。
少女の目は赤子の顔に吸いつけられている。
「お父さま、おやかんを七輪にかけておいてくださいな」
わたしは言われるなり、すぐに土間に下りた。黒く煤け凹みのあるやかんに水瓶から杓で水を汲み炭火の上に置いた。くべられている炭は真っ赤に焼け、部屋の中が臭う。腕時計をみると9時を少し回っている。
私は天井を見た。天井板の隙間から、黒い木立の影がほのかな月の光にふらふらと揺れている。
天井の鴨居からつるされた石油ランプの光の下で、私は少女に付き添って寝ていた。少女の脇では生まれたての赤子が乳を欲しくて鼻をならし、やがて大声で泣き始める。少女はそのたびに上体を起こし、赤子を抱え上げると甲斐甲斐しくおむつを取り替え、乳房を露にする。私はみないように横をむく。疲れているにも係わらず一晩中眠りが浅く。幾度となく目があき、少女に話かけようかと思った。少女は赤子に乳を与えるとすぐに強い睡魔におそわれるとみえ、前後不覚の眠りにおちいる。おかっぱの頭がときどきびくっと動くだけである。
やがて夜も白々と開け始め天井の隙き間から見える木立が緑色に輝きはじめたころ、私は突然の眠りにおちていた。
どのくらい寝たのであろう、頭の方からかたかたと物音がきこえ、目がさめた。首を反らしてみると少女が古惚けた鏡台にむかい、横ざまに座って髪に櫛をいれている。
櫛が少女の指に吸いついているように髪の中にもぐりこんでいく。少女の手のやわらかな動きはどうだろう、熟しきった女ですらこのように完成された動きは出来まい。
「起こしてしまいましたわね」
少女は梳る手を止めることなく私の方を向くとほほ笑んだ。
私は起き上がりながら少女に言った。
「君はいくつなの」
少女は片手で五と三を示した。八歳か。
脇の布団にいる赤子がくすんくすん言い始めた。
少女は赤子を抱き上げると乳をふくませた。
「お父さま、川から水を汲んできてくださいません」
私は部屋から土間に降り、バケツをもって入口の戸を開けた。朝の光が部屋の中に差し込み、部屋の中の少女と赤子の姿が橙色の霏の中に霞んでしまう。
「川の縁はすべりますから気を付けてくださいね」
少女の声が後ろからきこえた。
私はこのまま町に戻ろうと決めていた。
外に出るとまず目に入ったのは少し離れた木の根元に横たわっている老犬だった。首をすっくと伸ばし、スフィンクスのように私のほうをみつめている。目が合った。犬の目に警戒心があった。逃げるなといっているようだった。
私は重くなった足を一歩一歩前に進め、犬の脇を通り過ぎた。犬は動こうとするわけでもなく私を見ているわけでもなかった。ただ古屋の入り口を見つめているだけである。振り返えると少女が立っている。赤子を胸に抱き犬を見ている。犬はのそりと起き上がると少女の脇に歩み寄り、いきなり少女から赤子をくわえ身を翻して芦の中に走り去ってしまった。
少女は追いかけるわけでもなく、なにもなかったように立たずみ、はだけた胸を服で覆った。
私は走った。犬を追いかけたのではない、犬とは反対の方に走った。ここから逃げる。芦の群落から雑木林の中に飛び込んだ。何も後を追って来る気配はない、しかし後を振り向くのは怖い、一心に走った。あの社でもいいどこか見たところに出ることが出来れば。
浦島草の花ががさがさと倒れていく。浦島草を踏み倒して走る。額から汗が吹き出す。息切れがして足が止まった。追いかけてくる者はいない。
その時、浦島草の茂みから少年が突然現われた。
色が透き通るように白い。青い半ずぼんから細い足がのぞいている。
少年は私を見て言った。
「母が待っています」
「君は」
「母が待ってます、急いで下さい」
少年はそう言うときびすを返して歩き始めた。
足が勝手に動いて少年のあとを歩いていた。
林の中は浦島草の匂がうずまき鼻を突く。
少年がきたところは社だった。社の入口の羽目板ははがされ、戸が開かれていた。
「母がいます」
少年は私に中へ入るように促した。
薄暗い社の中で黒い影が動いた
「お帰りなさいまし」
少女の声が私をでむかえた。
辺りが明るくなった。少年がランプに火を入れた。
「朝のお食事にしましょう」
丸いちゃぶ台の上に白い器が置いてある。中には芋が盛り付けられていた。
少女も少年も机の前に座った。
「こちらに」
少女は私を座るように促した。
「おいしいですわよ、どうぞ」
ちゃぶ台の前に座ってもどうしてよいかわからない。
「お父さまが召し上がらないとこの子もいただけませんわ」
芋を一つとった。ゆでてある芋は皮がぬるっとむけた。口にいれる。
少年も手を伸ばし、おずおずと一つとると、剥いて食べた。少女は少年を見てほほ笑み、わたしに言った。
「お父様に似ていますでしょ、この子」
わたしは意味もなくうなずく。
「これは浦島草の根ですの」
少女が言うと、少年は、
「浦島草の根は毒じゃないのですよ、まむしぐさだってね」
大人びた口調で言うともう一つ口にもっていった。
少女はわたしに向かって、
「もう召し上がりませんの」
湯を茶わんに注ぎ差し出した。
「赤ちゃんはどうしたの」
「あら、この子ですのよ」
少女は少年を引き寄せると、自分の膝に抱き上げ、少女より大きい少年を赤子のように揺すり始めた。
「おかあさん」
少年は少女を見てあまえるように体をあずける。
おかっぱの少女は体を揺すりながら歌を謡いはじめた。
「ひとつ、独寝、浦島草
ふたつ、文月、遅すぎて
みっつ、密なし、すすき蝿
よっつ、夜なべで、閻魔虫
いつつ、居着の、白拍子
むっつ、迎火、みな燃やせ」
少年の体の動きが芋虫のようにのたくり始める。
「ななつ、泣く子は、浦島草
やっつ、矢がすり、やぶれがさ
ここのつ、こくりこ、眠り草
とうは、遠吠、耳隠せ
じゅういち、数珠玉、耳飾り
じゅうに、戻るか、浦島草」
少女の膝の上では赤子が足を激しく動かし泣き声を上げた。
おかっぱの少女は赤子を揺すり、私に向かって裂けた真っ黒な口を大きく開け、ぐぐぐと笑った。
あたりが暗くなっていく。
少女の姿だけがぼうーと光の中に浮き出ている。
少女は私を見て、はーとため息をつき、真黒な口に赤子をほうり込んだ。
赤子は見る間に少女の口の中に消えていく。
少女の姿も霞んできた。
「お父さま」
少女の最後の声がきこえた。少女は小さな玉になって私の足元にころがった。干からびた浦島草の根の匂いがした。
わたしはそれを口に入れた。
目の前に二本の布紐が垂れ下さがってきた。
闇がせまってきた。眼が霞む。自分の心臓の高鳴りが首の血管を伝わり頭に響く。四つんばいになり手探りで回りの床を確かめていく。
硬いものが手に触れた。かすかな光のなかで見えたのは大きな犬の骨だ。犬の骨の前に子供の骨が一つ横たわっている。手を伸ばし、子供の頭蓋骨に指が触れると、コロンと転がった。転がった頭蓋骨が、さらにその隣の小さな頭蓋骨に当たった。赤子の頭蓋骨は埃をあげてぐずぐずと崩れた。
浦島草のげっぷが込み上げてくる。眠気が襲ってきた。手も動かず足も動かない。私は真っ暗な社の中で崩れ落ち、犬の骨の脇に横たわった。
少女と赤子と犬の骨の脇で私は永遠の眠りについた。
土埃が私の上に降り注ぎ埋もれていった。
やがて時が経ち、崩れ落ちた私の体から浦島草が芽生える。
浦島草は大きな真っ白な花をつけるだろう。
ゆらゆらと揺れながら長いべろを伸ばし、社を訪れる者を待つことになるのである。
浦島草綺譚
私家版幻視小説集「お化け草、2018、一粒書房」所収
木版画:著者


