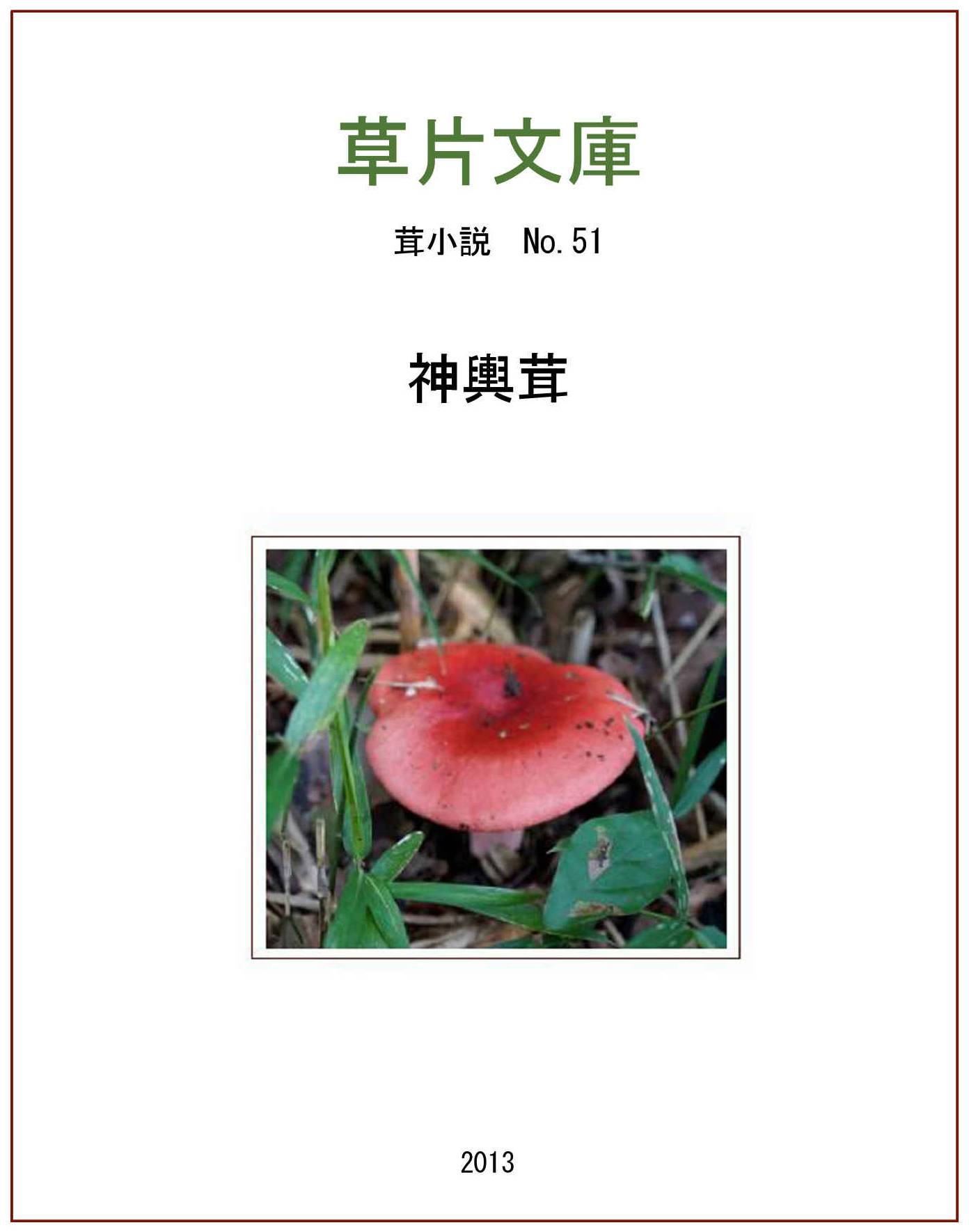
神輿茸
私の仕事場は電車を降りて、駅から歩くこと十五分ほどのところにある。首都圏から私鉄で三十分ほどの古くからの住宅地で、駅前は狭く、タクシーも常駐していない。必要ならば駅に備え付けの直通の電話で呼ぶしかない。
駅の出口は一つしかない。駅から出て踏切を渡り、道沿いに歩いていくと、コンビニと小さな本屋、不動産屋がある。そのいくつかの店の前を通りすぎると、大きな寺の塀に沿って歩くことになる。おかげで、木々に囲まれ夏でも気持ちのよい道である。寺の反対側は住宅地で、昔に開発されたところであることから、庭がたっぷりとってある一戸建てがならんでいる。
寺は奇勝寺といって、敷地はかなり広く、歴史は古いらしい。寺の角に来ると十字路に出て、左に曲がるとまた寺に沿って歩くことになる。五分もいくと、道をへだてて私のオフィスがある。道路沿いの三階建てのビルの一番上である。奇勝寺がよく見える。都心から離れてはいるが、コンピューターがあればよい仕事であり、インターネット環境が整っているので仕事に支障はなく、居心地のよい仕事場である。
オフィスでは、私とマノンと稲の三人が働いている。というより、ここは三人で立ち上げた企画、アドバイスの会社である。何のアドバイスをするのかというと、何でも屋である。さすがに科学系の企画のアドバイスをすることはできないが、一般の会社の宣伝企画をしたり、市町村のイベントの相談にのったりする事をしている。会社の名前は「素マイル」という。単純な名前ではある。われわれのアドバイスを受ければ、うれしくて自然とほほえみが浮かんでくるという意味と、いつでもスマイルをという意味と、いろいろある。もちろん、仕事場のバックミュージックはチャップリンのスマイルである。
三階のオフィスの入口を開けると机の前でコンピューターを見ていたマノンが、「蛍(けい)、おもしろい仕事がきているよ」と顔を上げた。
私の名は大邑(おおむら)蛍、美大出のデザイン屋である。
マノン、ヘーリッジはスイス人で日本の大学の文学部を卒業して、そのまま日本で就職をした。いったん大手外資系のコンピューター会社に就職したのだが、彼女には日本人の感覚の方が好きだったようですぐに会社をやめた。そのとき演劇をやっていた河綿(かわた)稲と知り合い、稲の友人である私と出会うことになった。三人とも同年齢で、会社勤めはしたくないといった人種である。意気投合してこの企画会社を立ち上げたということである。
「どんな、仕事」
「静岡の漁業組合と町がお祭りを企画していて、そのマネージの依頼よ、神輿と山車を作りたいのだそうだわ、どう、蛍、その神輿のデザイン考えない、私と稲で祭りの企画をするわ、特に稲にはお酒関係がいいかな」
なかなかいい采配である。
そこに、稲が入ってきた。今日も粋な和服姿である。
「イネ、今、ケイと今日はいってきた仕事のことを話していたの、静岡の漁港の祭りよ、神輿を造ることからすべて任してもらえるの」
「面白そうね」
稲は自分のロッカーに草履をしまうとスリッパに履き替えて席に着いた。
「それで、私はなにをするの」
「今調べたら、その町に焼酎を作っている会社があるの、その焼酎と地元名産の桜エビや魚介類と組み合わせて、祭りで売りだすの、お祭りに屋台なんて行うのもおもしろいわ」
「いいわね、でも夏ならビールかな」
「それお願いよ、ビール、焼酎で屋台、ビールは大手でもいいかもしれない。お祭りの屋台でいっぱい飲むのいいよね」
「お祭りの司会は私がやるわ、こういっちゃなんだけど、日本のみなさん外人さん大好きだもんね」
「蛍にはなにしてもらうの」
「新しい感覚の神輿を考えてもらうの、特に神社があるわけじゃないから自由ったら自由だけど、昔からの神輿の形に何か新しい特徴をくわえるのは大変よ」
「そうね、でも楽しそう、明かりをつけようか、きらきらしているのじゃなくて、しっとりとした光で」
「いいわね」稲が賛成した。
「それからね、神輿だけじゃなくて、山車も作らなきゃならないの、それも蛍、考えてよ」
マノンがそうつけくわえた。
「うん、わかった、神輿と山車が対になるような感覚でいけばいいのね」
「そう、それがいいわ」
ということで、その日は、祭りの企画の大雑把な話で終わった。
先方にそのような話をしたところ、大乗り気になり、アイデアの概略を持ってたずねる約束をした。静岡のその町といえば美味しい魚介類がたくさん水揚げされるので有名である。行ったついでに蟹でも食べてこようということで、三人そろって、遊び気分で行くことにした。
その日、帰支度をして窓から外を見ると、奇勝寺の墓地に転々と赤いものが見えた。三階のオフィスの窓はすべて寺の方をむいており、広い墓地が見下ろせる。彼岸には多くの人が訪れ、墓を洗い、花をたむけるので墓地が花畑のように明るくなる。だが、どうして菊ばっかりなのだろう、薔薇でもいいんじゃない、とマノンはよく言っている。日本人の頭の中にある古くからの習慣、固定観念はなかなかかわらない。
今見える墓には朱の薔薇に近い赤色が見える。何の花なのであろう、曼珠沙華の花より小さい感じで、赤い色がもう少し濃い。
「ねえ、墓の中が赤い花でうまっているけど、ちょっとみていかない」
彼女たちも窓の外を見た。
「ほんと、なんだろう、いってみようか」
我々はオフィスを出ると、駅まではかなりの遠回りになるが、寺の入口に回って墓地を覗いてみることにした。
未知沿いには高い石塀があることから中が見えない。少し歩くと奇勝寺の正面入り口になる。寺の庭には人の気配がしない。墓地は竹垣で囲まれており、境内とは隔離されている。中に入ることは今までなかった。
「結構広いのね」
「そうね、いつも上から見ているからわからないのね」
墓地を竹垣の隙間から見ると、黒光りする大理石や高価な石で造られた墓が並んでいる。一つの墓地は広いし墓そのものも大きく、迫力のある墓地である。みすぼらしくない墓地といった方がよいかもしれないが、あまりにも整然としているので情緒がないと感想を漏らす人もいるかもしれない。
墓地の入口に立ったときに、みんなえーという声を上げた。赤いのは花ではなかった。朱色の傘を持った茸が至るところに生えている。まだ成長を始めたばかりの茸は真っ赤で根本に壷があった。
「卵茸じゃないの」
マノンが言った。
「ヨーロッパじゃシーザーの茸と言って、おいしい茸の代表みたいなものよ」
「こんな真っ赤なのが食べられるの」
稲が不思議そうな顔をした。
「私もこんなにたくさん生えているのは始めてみた。昔すんでいた丘の上の家の近くで、夏の終わりにいくつか生えているのを見たことがあるだけよ、ほとんど毒だと思いこんでいた」
「これはバター炒めでも、シチュウでもおいしいのよ」
「でも、お墓に生えているのじゃちょっと気持ち悪いわね」
「それはそうね」
私は眺めていて、ふとよいことに気がついた。写真機を取り出して何枚か写真を撮った。
「どうするの」
「茸とクラゲの神輿をつくるの、きれいよ、赤い茸と薄青色のクラゲと、それにイソギンチャク、だしはマグロにマンボウ、大きなタコにヒラメやタイや乙姫様よ」
「はは、なんだか、築地の魚市場だね、いや竜宮城かな」
「それよ、それでいこう」
作りようによってはかなり落ち着いた古式、古色のものになるだろう。
そんな話をしながら墓地から寺の庭にもどると、門から入ってきた袈裟をきたお坊さんに出会った。
住職のようである。私たちはちょっと頭を下げると、その坊さんは立ち止まって話しかけてきた。
「お参りですか」
「いえ、向かいのオフィスに勤めている者ですが、窓から赤い花のようなものがお墓の中に見えたものですからきてみたのです」
「ああ、あの赤い茸ですね、不思議なこともあるもので、ついこの間、若い女性が葬られましてね、今時珍しくどうしても土葬にしてくれとのことで、その葬儀が終わるとまもなく茸が墓じゅうに生えましてね、たまたまでしょうけれどもね」
「そうでしたの、でも卵茸はおいしい茸なんですよ」
「ほー、食べられるのですか、だが、墓地の茸じゃ誰も食べないでしょうね」
「そうですね」
「それでは」
お坊さんは玄関に向かった。
それから一週間後、今日静岡に向かう。オフィスの窓から墓をみるとまだ赤い茸が花盛りであった。花盛りというのはおかしいかもしれないが、見た感じではその通りなのである。茸は菌類の花に相当するので花盛りでもよいのかもしれない。やがて胞子が撒かれ萎れていくのだろう。
「今日はこれから静岡だよ、準備はできた」
マノンが声をかけてきた。
「うん、楽しみよ」
稲はいろいろな屋台を箇条書きにしたものをひらひらさせた。
私も発泡スチロールでこしらえた神輿と山車を抱えあげた。
「壊さないように持っていかないと」
「そうだねえ、軽いけど嵩がある」
東京駅まで持っていくのが大変だ。なんとか新幹線に乗り込むと、静岡までは乗った気がしないほどすぐについてしまう。東海道線に乗り換えて目的の港に向かう。
タクシーで漁港の組合事務所につくと、かなりの人数の人たちが大きなテーブルの周りに座って私たちを待っていた。
「よく来てくれました」
長塚孝組合長が私たちを事務所に招き入れ、机の周りにいた人たちが立ち上がった。大きな男ばかりだ。猟師たちだ。
椅子をすすめられ腰掛けると、奥から若い女性がお茶を運んできた。
わたしはぴんときた。この子を乙姫にしよう。ここでは目立たない格好をしているがほんの少しメイクをして、着るものをかえれば、都会でも大受けするかなりの美貌の女性である。
女性は我々の前に熱いお茶をおいて、ちょっと会釈をして奥に入っていった。
長塚組合長は日に焼けた四角い顔を我々に向けた。
「面白そうなお話でしたが、具体的に聞かせてください」
マノンが全体の進行について話をした。稲が屋台の説明をすると、男性たちが、「おらがやるぞ」声を上げた。やる気が満ちてきた。
「寿司も屋台もいいな、魚はお手のものだ」
男の一人が身を乗り出した。
私は神輿と山車の説明をした。
「そりゃ、面白れえ、金はかかりそうだがな」
年寄りたちは皆喜んでいるように見えた。ところが、組合長が奇妙なことを言った。
「あの四人らの意見を聞いてみなきゃならねえかな」
年寄りたちもその言葉でちょっと気をそがれたような顔を見せた。
「どなたですか、それは」
「神輿の担ぎ手よ」
「え、子供たちが中心じゃないんですか」
「子供たちには山車を引かせるんじゃ、神輿は若いもんが担ぐ」
「干支の人とか、二十歳になった人とかいうのですか」
私が尋ねると、組合長は首を横に振った。
「あいつらの意見なんていらねえべ、重てえがっしりしたのつくるべ」
一人の男性が声を荒げると、みんなうなずいた。
組合長もうなずくと「そうだな」と、話を変えた。
「お宅の会社にお願いする費用や、祭りの準備の費用、そう、神輿や山車を作る費用、これはある篤志家の寄付によるものなのです」
「そうですか、でも一度、神輿などを作ってしまえば、その次からは町で楽しみながらできるのではないでしょうか」
私が言うと組合長は首を縦に振った。
「そうです、おっしゃるとおりで」
「それで、神輿を担ぐ四人の男性というのはどういう方でしょう」
「それですな、もう少し詳しく話しておきましょうかね、みなさん、かまわんでしょうな」
組合長は周りの人たちに了解を取って話し始めた。
「漁師の鉄火(てっか)というじいさんが貯金と家を売った金を組合に送りつけてきましてな、これで神輿と山車を作って、毎年八月に祭をやってくれということだったんですわ、三千万円ほどありました、しかも企画はお宅に頼めということまで手紙に書いてありました。さらに神輿を担ぐ四人の若手まで指名されていたのです」
「おや、なぜうちの会社を指名されたのでしょう」
「わからんですね、ともかく、すべてじいさんのお膳立てです」
周りの老人から、
「もうちょっと教えておいた方がよいのではないかい」
と声があがった。
組合長はうなずくと続けた。
「鉄火じいさんは、今、行方がわからんようになってます」
「どうなさったんです」
私は組合長の顔を見た。ちょっと陰がある。
「わからんですわ、じつは鉄火じいさんの娘さんが最近亡くなったんだわ、娘といっとったが本当は孫でな、両親は早くに死んじまって爺さんがそれは大事に育てましてな、それが不慮の事故でねえ」
「そうだったんですか、その方の話を聞きたいですね」
「ああ、警察も捜してますけど、今の居場所わからんのです、じゃが祭をしてほしいというくらいだから、そのうち帰ってくるとわし等は考えとります」
「そうですか、じゃあ、すばらしい祭にしなければいけませんね」
組合長が企画書を見て言った。
「そうですな、この企画とてもいいですわ、これで進めてもらえんかね。必要なこと言ってくださりゃ準備しますので」
「それで祭りはいつにするつもりですか、神輿を本格的に作ると一年じゃ足りないかもしれません、今年は無理です」
「来年の夏には必ずやりたいと思っとるんです、」
「一年後ですね、急いで作らせないと」
私は神輿がまにあうかどうか、ちょっと心配になってきた。
「この町にゃあ、えらく上手な木工所があるから、そこに頼めば大丈夫だよ」
一人の老人が口をはさんだ。
「そうだなあ、あそこならいいな、かならずやってくれるさね」
組合長もうなずいている。
「神輿と山車の絵図と模型を置いていきます。絵はいくつか書いておきましたから、どのようなものにするか連絡ください、そうしたら、もっと細かな図を作成します」
「そうしましょう、屋台もその木工所でつくらせます、吊るす提灯や飾りなどはデザインしていただきましょうかな」
「町にあうようなデザインを考えます」
「祭の間のイベントはもらった計画書を見ておくけど、こっちからおねがいすることもあっかもしれないが、いいかね。素人のど自慢がかいてあるが、やっぱり誰かを呼びたいね」
私はうなずいて、今時の歌手の何人かと歌謡曲の歌手何人かの名前を挙げた。
「予算はなんとかなるだろうが、だれがいいか皆に聞いてみとくわ」
「そうですね、そう言う人を呼ぶには、まず日にちも早く決めないと」
大きな方針はだいたいきまった。これからなんども足をはこばなければならない。そのあと我々はその町の温泉ホテルに一泊した。温泉にゆっくり浸かりながら三人で話し合ったが、なかなか落ち着いたいい漁港で、三人ともここの人たちをきにいり、祭りが始まればよい観光地になるという結論になった。
「でも鉄火じいさんて、どんな人なんだろうね」
「うん、お孫さんて、どうしたのかな、自殺か事件かもしれないね」
この仕事はこの奇妙な出来事をのぞけば、今まで引き受けたものの中でもかなり充実したものになりそうな予感がした。まずは予算が確保されているところに安心感がある。ともあれホテルの海鮮料理は最高だった。
その後、組合長と連絡を取り合い、町の名前を冠した漁港祭と名前が決まった。
その年の暮れ、一番気になっていた神輿に関して意外な結末を迎えた。千葉市川市の行徳から神輿そのものが組合に送られてきたというのである。あわてて私が見に行くと、昔ながらのよい作りのものだが、奇妙なことに全体が真白に塗られていた。鉄火じいさんが依頼したということで送ってきたという。相談の上、私のほうで計画した作りかけの神輿はそれはそれで時間をかけてつくり、来年はその真っ白の神輿を使うことになった。再来年以降の祭りは二台の神輿になるわけである。
神輿を送ってきた鉄火じいさんの居所はいまだに分かっていない。しかし神輿と鉄火じいさんの安否がいっぺんに片づいて、漁業組合の人たちは安堵しているようすだった。
開催日も決まった。八月最後の31日になった。準備は着々と進んでいる。計画通りに運べばかなりの話題になるだろう。
町のほうでも、町起こしのきっかけとしてかなり力をいれていた。
のど自慢にゲスト出演してもらう歌手などの選定と交渉もすでに終わっていることもあり、そう言った方面から、この企画が次第にもれ知られるようになり、テレビの朝番組に取り上げられるなど毎日が忙しかった。それでも楽しく過ぎていった。
暮れも押し詰まったある日、稲がオフィスの窓から外を眺めていて、急に振り返った。不思議そうな顔をしている。
「ねえ、おかしいよ、あの墓にまだ赤い茸が生えてるよ」
マノンと一緒に窓をのぞくと、寒々とした墓地に赤い茸が点々と生えている。
「枯れなかったのかな」
「そんなことはないはずだよ」
その日の帰り、我々は寺によった。
墓地にはみずみずしい卵茸がいたるところで元気に生えていた。
「どうしてだろうね、こんなに寒いのに」
「そうなんですよ、何度か採ってしまったんですが、次から次へと生えてくるのですよ、なにの影響でしょうね、今ではそのままにしています」
後ろからあの僧侶が声をかけてきた。前にきたときに声を交わしたお坊さんだ。
「住職の浄念です、前にもおいでになりましたな、確か九月ごろ」
「ええ、若い女性が葬られた後、生えてきたというお話をなさっていました」
「そうでした、それも不思議だったが、この冬の茸も不思議です」
住職はそう言って寺の裏のほうに行った。
「不思議ね」
その年はそれで終わった。
正月は五日から仕事が始まった。オフィスに着くとすぐコンピューターのすいっちをいれインターネットを開いた。静岡の漁業組合からメイルがきていた。今年の仕事始めも静岡の漁港祭からはじまったわけである。
屋台に魚の料理だけじゃなくて肉料理も出したいがどのような料理がいいかと組合長の長塚さんからの問い合わせだった。このごろはB級グルメが盛んで豚のホルモン焼きなどどうだとある。我々は高級な魚貝類の料理、刺身や焼き鮑をだす屋台を考えていたこともあり、B級グルメと並べるとバランスが少しばかり悪い。
稲が「いっそ、すべて和風と洋風の高級屋台にしようよ」と言った。
「そうだね、ほら、静岡の有名なホテルがあるじゃない、そこのシェフかなんか呼んで牛の鉄板焼かなんか、鳥の上等な名古屋コーチンの卵料理、単純な目玉焼きだっていいじゃない、ただしひと味違うもの」
「面白いな、他の祭りじゃ見たことない」
それでいこうということで、いくつかの候補を箇条書きにして、組合長にメイルで送った。組合長からはすぐに返事が来て、今すぐにも食べたい、それでいきましょうということだった。あのあたりのそれなりのホテルに声をかければ、ホテルの宣伝にもなるしのってくるだろう。
上等な屋台で量は少しでも普段食べられないものを立ち食いする。今までにない発想である。
マノンが窓の外を見た。
「まだ、赤い茸がたくさん生えているよ」
年が変わって墓地は薄く雪化粧をしている。その中に赤い茸の傘がぽちぽち見える。
マノンが立ち上がってわれわれを窓に呼んだ。
「ヨーロッパでも雪の中で生えているの見たことない、奇妙ね」
稲もおかしいと思ったようだ。
「秋に見たのは確かに本物だった、今のは本当に卵茸なのかしら」
「ねえ、あれ、ほら、なんとか堂とかいいうフィギアの会社があるじゃない、そこが作ったものなんじゃないの」
「うーん、あの会社なら作れるわね、でも何の目的なの、冬のお墓に赤い茸が生ええて、どうなるのかなあ」
「住職もぐるよ、きっと、噂が広がって有名になるのを待っているのよ」。
「そんな住職にみえなかったな」
そんな他愛のない話をしたが、電話がなり席に戻った。
銀座のジュエリーの店からの依頼だった。漁港祭の準備だけではなく、他の依頼もこなしていたので、かなり忙しい一年の幕開けである。
漁港祭の準備はかなり整ってきたといっても、これからが大変になる。それでも一月はまだよかったが、二月にはいってからは静岡に行くことも増えたし、コンピュータにかじりついて一日をすごすこともあった。徹夜騒ぎも何度か経験した。
そして、あっという間にその年も半年過ぎてしまった。六月になると静岡には何度も足を運び、ホテルや料理屋と最終交渉を重ね、屋台の企画を完璧なものにした。のど自慢の出演者選定も終わったし、花火屋とも打ち合わせを終えた。タイムテーブルを確固たるものにし、町長とも会い、神輿の飾りつけも終わった。ただその頃になっても鉄火じいさんの居場所はわからなかった。
七月になった。祭りの日まで一月だ。私は一週間前より近くのホテルに宿泊することにした。後の二人は三日前より合流することになった。
私は連日、漁港組合に顔を出し、組合長をはじめ町の人たちとも綿密に計画の最終調節をおこなった。県や市も応援に駆けつけるということで、そちらの関係の人たちとのすり合わせもあった。自分で思っていた以上にがんばることができた。
山車や神輿は港の近くの空いていた倉庫にしまわれている。ステージは魚市場に隣接する広い駐車場に設置された。新しく作られた屋台は岸壁の脇にずらりと並べられている。それぞれに提供するホテルやレストランの名前が書かれている。
マノンと稲も合流し、マノンはのど自慢大会の準備に奔走し、稲は屋台の出し物の調整に精を出した。こうして前日にはすべて順調におさまったのである。
八月三十一日、当日は雲一つないいい天気であった。
朝八時に合図の花火がぽんぽんぽんとあがった。
漁港関係者のほとんどの人々が何らかの役割を持つ大きな祭になっている。
我々はホテルでゆっくりと朝食をとって、それでも十時にはホテルをでた。前の日は遅くまで準備に奔走していたので、今日はむしろ楽である。祭りの実質的なマネージは漁業組合の人たちが中心である。我々は祭がどの程度予定通り進むか見守り、うまく行かないところをその都度修正しながらいい方向に導く役割である。
組合の事務所に行くと、関係者はすべて集まっていた。
我々が港の事務所に顔をだすと組合長が振り向いた。
「昨日は遅くまでありがとうございました。いい企画をもらったんで、本当によかったですな、みんな楽しんでおります」
「すばらしい祭になりそうですね、町の人たちの熱意には驚かされました」
「マノンさんには夕方五時からのステージの進行をよろしくお願いします。稲さんには、屋台たのみます。町の人が高級屋台だと騒いでますよ、たいへんです、蛍さんのおかげで、山車と神輿はみんな大喜びですわ、そちらお願いします」
その頃には組合の人たちも私たちのことを名前で呼ぶようになっていた。お互いにそうしていたので自然の成り行きである。
「山車の上の乙姫様は事務所の秋ちゃんになりました。最後まで嫌がってたのですがね、今日の朝、引き受けますと言ってくれました。秋ちゃんは鉄火じいさんの娘さんととても仲のよかったので、供養のつもりでやると言ってました」
「それはよかったです、秋ちゃんはどなたかのお嬢さんですか」
「鉄火じいさんと組んで漁をしていた洋平さんのお孫さんですよ、洋平さんは昔になくなっていますが」
「そうだったのですか、でも引き受けてもらってよかった」
「神輿と山車は四時頃から町を練り歩き、ステージの周りにもいきます。最後はまたこの漁港に戻ります」
「神輿を担ぐ人は時間通りに来てくれますか」
神輿を担ぐ四人とは一度あったが、茶髪の若者で、たいした挨拶もしなかった。
「だいじょうぶ、親がむしろよろこんどる」
「どのような人たちなんです」
「それが、わたしらも、どうして鉄火じいさんが選んだのかわからんのです、親はみんな町のそれなりの人たちですけんど、あいつらはちょっとはずれた連中でして、警察のやっかいにも何度かなっとるんですわ」
「なぜ鉄火さんはそのような人たちに神輿を担がせることにしたのでしょうね」
「うーん、繋がりはわからんです。ただ、金のあるうちの息子たちで、親はよろこんで、半纏なんかを用意してくれたし、祭りにたいへんな寄付もくれました」
「それじゃ、わたしたちは会場にみにいきます」
「よろしくお願いします、みなさんには花火大会のいい席を用意しましたし、これは屋台のフリー券です。好きなものを食べてください。寿司もうまいですよ」
「ありがとうございます」
私は魚市場に様子を見に行った。ずいぶんきれいに飾られた山車に張り子で作った海の生き物などがたくさん乗っていた。電気が入るととてもきれいだろう。乙姫様の腰掛ける長椅子もきれいな赤い布で覆われ、秋ちゃんが化粧をして薄ピンク色の着物を着て横たわると、なかなか見栄えがするにちがいない。
神輿は真っ白で、四方に小さな白い提灯がぶら下がっていた。地味だが、好感の持てる神輿である。白い神輿などどこにもないであろう、なかなかきれいだ。勇壮な様はないが、優雅さが漂っている。ちょっと洋風でもある。一体誰が考えたのだろうか。鉄火じいさんだとすると、かなりセンスのある人だ。
小さい神輿とはいえかなりの重さがある。若い男四人でもかなりの重さを感じるに違いない。
山車の周りには先導する大人たちや、引くことになる子供たちが半纏を着て集まっている。子どもたちは始まるのが待てないといった表情で動き回っている。
神輿の脇には一人の老人がいるだけで誰もいない。鉄火じいさんではなさそうだ。ちょっとお辞儀をすると、老人の方から声をかけてきた。
「鈴井といいます、企画会社の方ですね」
「はい」
鈴井さんはうかない顔をして、私のそばによって来た。
「神輿の先導を頼まれまして、今日はついて歩くことになるのですが、まだ担ぎ手が来てませんでな」
「よろしくお願いします」
「何で鉄火さんはあの四人を選んだのでしょうな、神輿とは全く似つかわしくない者たちで」
「どんな若衆でしょう」
「若衆などと呼べるものではありません、こう言っちゃ何だが、この町の悪四人組ですよ、何かあっても親が金で解決してしまうから、やりたい放題」
かなりの悪口を平気で言う人だ。
「そうですか、それで、鉄火さんは何か目的があったのでしょうか」
「うーん、わからんねえ、だけど、娘の紗英ちゃんに関係があるんじゃないかと思っているんだがね」
「鉄火さんの孫ですか」
「ああ、そうです、自殺だそうだけどね」
「そうだったのですか」
「うん、儂の想像だから、気にしないでください」
「でも、いやだったら担ぎ手に選んだりしないのではないでしょうか」
「それはそうですな、しかしねえ、この祭の費用、鉄火さんが用意したということだが、そんな金があるわきゃあないけどねえ」
「そうですか」
「まあ、この町の者にはこんなこと言えないな、さて、まだ出発には一時間ある、わしゃ家に一度けえってまたくる、近くだからね」
老人はそれだけしゃべると、そそくさとその場を離れた。神輿の先導にはあまり気乗りしていない様子である。
私もその場から離れ、駐車場に設置された舞台にいった。舞台の袖ではマノンが小柄な男の子に指示を与えている。
近寄っていくと、マノンが私に気がついた。
「蛍チャン、今日のメインゲスト、港エレジーを歌っているヒロちゃん」
ヒロちゃんと言えば若い子からおばさんまで幅広く受けている歌手だ。それにしても小柄でその辺にいる中学生のようだ」
「こんにちは、よろしくお願いします」
「ヒロです、よろしくお願いします」
やけに丁寧にお辞儀をして私をみた。なるほど誰にでもこの調子で一歩下がっているところが受けるのかもしれない。
「神輿や山車はうまくできていたわ、何にも問題ないわ、何か手伝うことある」
「こちらももうほとんど終わり、ヒロ君、とても飲み込みが早いの」
ヒロは楽団の方に音の調整に行った。
「屋台に行ってみない、もしかすると何かつまめるかもしれない」
マノンが舞台から降りてきた。
二人して屋台の並んでいる岸壁に行ってみると、いくつかの屋台はすでに準備を始めていた。まだ食べさせてもらえるほど準備は進んでいない。稲は寿司の屋台で板さんとなにやら話しをている。
「あ、二人ともきたの」
稲が振り向いた。
「あれ、稲さん顔赤いよ」
「ふふ、ここにおいしいお酒があるの」
彼女はコップを持ち上げた。
「もう飲んでいるんだ」
「飲む?」
「私は司会がある」
「あたしも山車と神輿をみなきゃ」
「そうか、残念ね、後でいらっさいね」
「やだ、もう酔っぱらってる」
「でも、稲ちゃんはいくら飲んでもずーっとその調子でしょう」
我々が話しているところに、お揃いの半纏をきた四人の若者が歩いてきた。神輿を担ぐ子たちだ。岸壁の屋台をまだやってないという顔でのぞいている。茶髪に細い腕。いかにも遊び歩いている風情の今の男の子たちである。
値踏みするような目で私たちを見て通り過ぎた。
「あの子たちかあ、神輿担ぐのは」
「そうよ」
「大丈夫かしら」
神輿の重さは大丈夫としても、四時頃出発して町中を練り歩き、その後、五時半頃、ステージに到着、一時間半歩く体力があるだろうか。
ふたたび鉄火じいさんがあの四人を選んだ疑問が私の頭の中をよぎった。まだ稲とマノンにはあの四人の素性を話していない。
「どうぞ」そんなとき、屋台の板さんが、上等なトロを握って、皿に載せてくれた。
「すみません」
私とマノンは小皿に醤油を入れると一口で食べた。口の中で中トロが、それこそとろりとシャリの中に溶け込んで舌の上に広がった。
「おいしい」
マノンも相好をくずした。
「一昨日あがった奴だ、もうちょっとおいた方がうまいかもしれないね」
板さんが今度は脂ののった金目を握ってくれた。
「おいしい、いつまでも食べていたいけど、仕事があるわね」
私とマノンはまた何か握ろうとしていた板さんの動きをさえぎった。上等な屋台は大成功となるだろう。
「ごちそうさま、またくるわ、稲ちゃん飲み過ぎないようにね」
稲はおいしそうなタコを握ってもらっていた。
うらやましいが仕方がない、その場を離れた。
マノンと分かれて、山車と神輿のところにくると、あの四人組が集まっていた。もどった鈴井さんに何か指示されている。回りには何人か手伝いの人たちがいた。
私に気がついた鈴井さんが言った。
「神輿を担ぐ連中が来てます」
四人はちょっとお辞儀をしただけですぐ顔を背けた。ずいぶん前に一度会った。
「さー一度担ぐか」
鈴井さんが若者たちに声をかけた。
四人はきびきびというより、かったるいという動きで神輿にもぐり込み、肩に棒を当てるとよいしょと立ち上がった。
「なんでえ、軽いじゃねえか」
一人が声を上げて笑った。
「軽いが、長い間担がなければならないよ」
鈴井さんが言うと、四人ともへへへと顔を見合わせた。
「こんなじゃでえじょうぶだ」
周りで何人かの半纏姿の人たちが見守っている。
「ちょっと、この中をねってごらん」
鈴井さんが声をかけると四人は歩き出した。
「もっと腰を落として神輿を上下させてリズムをとりな、声を出してね」
鈴井さんが指示をした。
「ほいさ」四人は神輿を揺らしながら歩いた。
「そうじゃねえ、ちょっと止まれや、止まって、神輿をわっで持ち上げて、しょいで下げるのをみんな一緒にやれや」
「わっしょい、わっしょい」四人は神輿を上げ下げさせた。
「そうだ、それで、次のわっしょいで歩いてみな」
「わっしょい、わっっしょい」神輿が少しまともな動きを見せるようになってきた。
「そんな調子だな、三十分後に出発しよう、初めてだから怪我しないようにいけや、怪我でもするとわしが親父さんたちにしかられちまう」
四人は神輿を置くと、取り巻きに「ちゃらいもんよ」なんて言っている。どうも家族たちらしい。
私は山車の方に行ってみた。秋ちゃんが乙姫様の格好をしてやってきた。予想に違わずきれいである。
「こんにちは」
私は声をかけた。秋ちゃんはギクッとして私の顔を見ると私を思い出したようで、堅くなっていた顔がほころんだ。予定の衣装ではない。
「きれいね」
「ありがとうございます」
「その衣装は自分であつらえたの」
「いえ、鉄火おじさんが送ってくれたのです、どこかから私が乙姫様になるって聞いたのではないかしら」
「それにしても、あなたのからだにピッタリね」
「鉄火おじさんがあつらえてくださったからだと思います、だから私の体にあっているのだと思います」
「おじさん、あなたのサイズ知ってたの」
「私、おじさんの孫の紗英ちゃんとサイズ全く同じだったの」
「あなたの友達だったときいたわ、何か不幸な目にあったそうね」
「ええ、自殺しことになってます、鉄火おじさんはそのことは話してくれませんでした、組合長さんが教えてくれたのです、おじさんは真っ赤な鬼のような顔をして言ってたそうです、秋ちゃんには絶対あんな目にあわせないって」
「紗英さんが亡くなった理由は聞いていないの」
「はい、でも、何となくわかる、自分で死んだのではないと思う、町の人は自殺したと言っているけど違うと思う」
「え、それどういうこと、殺人事件」
「結果的にはそうだけど、病気で死んだのに近いかもしれない」
秋ちゃんの目に涙が浮かびそうになった。
「あ、せっかく、乙姫様になるのに、こんな話をさせてごめんなさい、それじゃ、がんばってお願いします」
「はい、精一杯、紗英ちゃんの分もやってきます」
そろそろ出発の時間である。秋は山車の上に乗り、長椅子の上にきれいな足をさらした。私はもう一度神輿のところに行った。神輿の方が先に出発する。
行ってみるとみんなが騒いでる。
神輿をみていた小さな男の子が指さして、「茸」と言った
みると、真っ赤な茸が一つ、真っ白な神輿の屋根の上に生えている。
担ぎ手の一人が手をのばして茸をとろうとした。
「熱」
茸に触れた手を引っ込めた。
「熱いことはないだろう」
もう一人の担ぎ手が手を伸ばした。
「痛て」
同じように手を引っ込めた。
「なにやってんだ、まあ、茸なんかいいじゃあねえか、ちょっとした飾りだよ、そろそろ出るぞ」
鈴井さんが声をかけると、担ぎ手の男四人は神輿を持ち上げて、肩に担ぎ棒を当て「さっきより重く感じるなあ」などと言っている。私も興奮していたのだろう、赤い茸がなぜ生えたのか考えることをしなかった。
「さあ、行くぞ」
「よいしょ、わっしょい」
神輿は広い魚市場の中をちょっと練り歩くと道にでた。周りで見物していた人たちもぞろぞろ後をついていく。山車も子どもたちのかけ声と共に動き出した。
神輿は駐車場の脇を進んでいく。駐車場ではまだステージの準備中である。一時間半後には町を練り歩いた神輿と山車はこのステージにやってくる。
私は赤い茸が一つ生えた白い神輿を見送って、ステージの手伝いをすることにした。
「マノンどう、大丈夫」
「大丈夫よ、五時ごろには始められるわ」
楽団の練習が続いている。並べられている椅子には、もうかなりの人たちが腰掛けている。ヒロのファンや追っかけのおばさんたちが前のほうを陣取っている。
「蛍ちゃん、稲ちゃん大丈夫かな」
マノンが心配そうな顔をした。
「私、行ってみようか」
「そうして、こっちは全く大丈夫、設営や進行は漁業組合の若い人たちがとても頼りになるのよ、私は司会に専念できる、それまで暇すぎるくらい」
私は岸壁の屋台のところに行った。稲が手を振った。
「蛍、もうおなか一杯」
「稲ちゃん、大丈夫だいぶ赤い顔をしているよ」
「大丈夫、大丈夫、お魚の店だけもうオープンしてるのよ、ホテルやレストランの洋食系はもっと遅くから始めることにしたの、それじゃないと、あっという間になくなりそう、魚は捨てるほどあるから大丈夫」
「そうね、ミニステーキ、オムレツ、ハンバーグ、ビーフシチュウ、特製目玉焼き、サンドイッチか、こんな屋台、銀座の歩行者天国で出すと受けるよ」
「確かにね、中華もすごいよ、本格的な店がみんな屋台を出してくれた」
「食べきれないね」
「そう、移動トイレを増やしたわ」
「さすが稲ちゃんね」
しばらく岸壁に腰かけて休むと、ステージにもどった。
予定通り始まろうとしているところだった。マノンの透きとおった声が聞こえる。最初は若い女の子の歌である。前座だが少しは名の知れている子で、若い人たちには人気がある。
私は後ろのほうの空いている椅子に腰掛けてしばらく様子を見ていた。
出し物は順調に進んでいる。飛び入りの歌のコーナーになると、歌いたい人たちが列をなした。楽団を前に歌う機会などいままでなかったことであろう。カラオケで喉を磨いた人ばかりで、どの人たちも前座の女の子より上手かもしれない。
例のヒロという歌手が歌う頃には観客席はいっぱいである。全国から買い付けに来る車のために用意されているだだっ広い駐車場が立ち見であふれた。
私は席を譲ってステージの脇に行った。ステージと観客席は少し離してある。観客がなだれ込むのを防ぐと同時に、山車や神輿が到着する場所として空けてある。
大きな拍手がおき、ヒロがおなじみの歌を歌い始めた。
その歌が終わる頃に、神輿と山車が到着するはずである。
歌は熱狂的な声援で終わり、アンコールに彼の持ち歌を二つ披露することになった。それも終わった頃、山車がステージの前に登場した。拍手が起きた。
まだ明るいが、山車には明かりが入れられ、長いすに寄りかかった乙姫様は輝いて見えた。
あれ、と思ったのは、秋ちゃんの顔がどことなく違って見えた。それにしても、ずいぶんきれいだ。
山車は大きな拍手で迎えられたが、登場するはずだった神輿がまだこない。
マノンが「神輿はどこかで寄り道をしているようです、少しの間、歌いたいかたどうぞ」とアナウンスしている。
先ほどの飛び入りコーナーで歌うことのできなかった何人かが壇上にあがった。
後ろには本物の楽団がいる。演奏しているのは音楽大学の学生さんたちだ。それでもこのようなバックで歌う機会などそうあるわけではない。次々に歌が披露された。
最後の一人が歌い終わると同時にタイミング良く、鈴井さんに先導されて神輿が入ってきた。
私は、あっと驚いた。到着したのは白い神輿ではない、真っ赤である。担ぎ手たちは青い顔をして苦痛の表情をしている。やっとの思いで神輿を持ち上げているようだ。よく見ると白い神輿が全面に真っ赤な茸を生やしていた。神輿のあらゆるところから赤い茸が一面にでているのである。どういうことだろうか。私はこの時、奇勝寺の墓の情景が目の前をよぎった。真っ赤に染まった墓と同じだ。
神輿はよろよろしながら壇上のまんなかにきて。用意されていた台の上にのせられた。担いでいた四人は放心状態で動こうともしない。
マノンが「どうぞ前の方におすすみください」
四人をうながし、若者たちは肩をおとして観客の前に姿をさらした。
マノンの拍手をと言う声で、やっと拍手が沸きあがった。
「初めてのお神輿かつぎご苦労様でした。ご紹介したいと思います、左から旗明さん、広井進さん、若井輝男さん、工藤純さん、みなさんもう一度拍手を送りください」
茶髪の四人がお辞儀をした。
観客の拍手が終わると、マノンは「山車に乗っていた秋さんにもこちらに来ていただきましょう、山東秋さんは漁港組合で働いていらっしゃるので皆さまもよくご存じのことと思います、今日は竜宮上の乙姫様になっていただきました」と紹介した。
大きな拍手の中で秋さんが山車から降り、壇上にあがってきた。きれいだ。
ゆっくりとあがってくると、四人の脇に立った。
私はあっと思った。秋さんとは顔立ちが少し違う。さっきもそう感じたのだが。
「秋さん、ご苦労様でした、どうでした乙姫様になった気分は」
秋さんはマイクを向けられてうつむき加減で言った。
「はい、これで思い残すことはありません」
不思議なコメントである。声も秋さんのものではないような感じがする。
その声を聞いて、四人が秋さんを見た。四人はぎょっとして、青い顔になり、よろけて一人は壇上に倒れた。
そのとき神輿の真赤な茸から、もうもうと赤い煙が立ち上って四人のからだを蔽い隠した。
マノンが驚いて、
「何が起こったのでしょう、神輿から赤い煙が出て四人の担い手を包んでしまいました。きっと、神さまが四人を祝福したのでしょう」
と言った。マノンのアドリブである。
そのうち、赤い煙はだんだんと消滅し、神輿の茸もすべて消えていた。
観客はこれも余興の一つと手をたたいた。
神輿を担いだ四人はぼーっと壇上で立っていた。
「さあ、皆様、もう一度大きな拍手をお願いします」
秋さんがステージからおり、山車に乗り込んだ。これから魚市場に戻ることになっている。子供たちが山車を引き始めた。神輿も戻る予定のはずだが、あの調子では無理だろう。案の定、鈴井老人がマノンに耳打ちをした。
マノンがアナウンスをした。
「山車は市場に戻ります。神輿はしばらくここでみなさまに見ていただこうということになりました。担いでこられた方たちに拍手をしましょう」
拍手が起きた。かろうじて四人に歩くエネルギーは残っていたようだ。
「どうぞ、海岸の屋台では、今日しか食べられない、特上の料理がとてもお安く用意されております。美味しいものを存分、召し上がりください
ここで、昼間の部は終了いたします、次はグループサウンズに登場していただきます。七時より開演です。どうぞ皆様、もう一度お集まりください。八時からは花火が始まります、ありがとうございました」
マノンに対して大きな拍手が起きた。夜のグループサウンズは、青年会議所の人たちがマネージをするのでマノンは開放される。
私は魚市場に戻った。
山車がもとの位置についていた。秋さんが調度山車から降りたところだった。
「ご苦労様でした、どうでした」
「何か、はずかしくて、でも楽しかったです。町をこのように上からゆっくり眺めることができましたもの、ステージにあがったときには、なぜか私ではないような気分でした」
秋さんは白い顔をピンク色に染めて絵顔で話してくれた。
「ステージのうえでは、すーっと気分が楽になったのです。胸に何かつっかえていたものが降りてしまったような。今とても幸せな気分なのです、どうしてかしら」
「よかった、見物の人たちもきっと幸せだったのよ、秋さんのようなきれいな乙姫様をおがめて」
「まさか。でもありがとうございました、後で花火大会を見に行きます、席が近くだと思います」
彼女はお辞儀をすると事務所に帰っていった。
そこへ、老人たちが神輿を担いでやってきた。鈴井さんも担いでいる。
「おお、大邑さん、儂等が持って帰ってきたよ,あいつ等、若いのにカスカスになりおって、親の車で帰りよった、弱いやつらよ、なぜ鉄火じいさんはあいつらを選んだのかねえ」
鈴井老人は神輿をおろすと、またそう言った。
「あの赤い茸はいったい何だったのかね、町を練っているときに、ぽこぽこと生えはじめて、あの若い連中が、神輿が重い重いと騒ぎおってな、儂がちょっと持ってみたが、なんてことはない、軽いものよ、そんで、だらしないこというなってケツを押したのさ」
「ずいぶん疲れていたみたいですね」
「うーん、どうしたのかね、あんなに若いのに。薬でもやってたのかね」
「そういう人たちなのですか」
「ああ、しょっちゅう警察に注意されている、それより、あの舞台の上にわきあがった赤い霧のようなのはどうやって作りなさった」
「あれは私どもがやったんじゃないですよ」
「え、それじゃなんだったのですかな、まるで茸の胞子が舞っているようだった」
「あの茸もどうなったのかしら」
「あんたたちが仕掛けをしたのかと思っていたんだが、真赤な茸があんなに生えてくるなんてどうやるのだろうと思っていましたな、でも神輿が赤く燃えているようで迫力がありました」
鈴井さんはちょっと不思議そうな顔をしていた。
「それとな、壇上にあがってきた秋ちゃんが紗英ちゃんそっくりになっとった。鉄火じいさんの思いが乗り移っていたような感じだったな」
「私もちょっと秋さんとは違うなと思いました」
「鉄火じいさんが後押しをした祭だからな」
そう言うと鈴井さんは仲間たちの後を追った。
私はまたステージに戻った。グループサウンズが練習をしている。演歌と違って派手な音を出している。観客席は若い連中に変わっていた。始まるにはまだ間がある。
稲が少し赤い顔をしてステージ脇の椅子に腰掛けていた。私を見つけると言った。
「蛍、あの真赤な茸どうやって作ったの」
稲も見ていたとみえて、あれが私の仕業だと思っている。
「私なにもやっていないのよ」
「私はあのお墓の茸を持ってきてくっつけたのかと思った」
稲もあの墓のことを考えていたようである。
「不思議よね」
「きっと誰かがやったのね」
「うーん、わかんないな」
マノンがグループサウンズの司会者に指示をしている。素人の若い男の子に司会の骨を教えているようだ。
「あと三十分で花火大会がはじまるわ、どう、私たちの席ができているみたいだからそこにいっていない。マノンには悪いけど」
「そうね、マノンには言っておこう」
私はステージの裏に回って、マノンに先に行っていることを告げた。
稲と私は漁港のはずれの松林の前に行った。砂浜にビニールが敷かれ、桟敷が作られており、まだ誰もいない。
桟敷(さじき)の一角に我々の会社の名前が書いた札がおいてあった。座布団が三つおかれている。稲と私はその上にすわって、「疲れたわね」とお互いの顔を見合わせた。
「マノンには悪いわね」
「彼女はなれているわ、体も頑丈だしね」
「外国製だものね」
などと話をしていると、注文もしていないのに、生ビールに枝豆を添えて若い男の子が桟敷にあがってきた。
「どうぞ」
「え、頼んでいないけど」
「組合長さんから言われています。企画会社のみなさんが来たら何でも出すようにと言うことです。屋台からお好きなものを運んできます。この桟敷の担当の菅原です」
「あら、すみません。ホテルにお勤めの方かしら」
「いや、漁業組合で働いています。まだ正社員じゃないのですが」
「いつからいるんです」
「二年前です」
彼は我々の前にビールと枝豆をおいた。
稲はすぐにジョッキをとってぐっと飲んだ。
「ほ、冷えていてうまい」
私もジョッキを口に運んだ
「何か屋台からもらってきましょうか」
「そんじゃ、やっぱり寿司かな」
「はい、とってきます」
「あなたもビールもらってきて飲んだら」
「いや、仕事中ですから、今日は特別手当が出ます」
「いいじゃない、もう一人の分も早く運んできたことにしてさ、寿司もみんなの分」
「ともかく、もってきます」
菅原と言った若い子は飛ぶように屋台のある岸壁の方に走っていった。
「感じのいい子」
稲が感心しているので私も相づちを打った。
「彼に聞きたいことがあるのよ」
「なにを」
「鉄火じいさんの孫の話、何があったのかしら、あの神輿を担いだ四人と関係ありそうよ」
「その話し始めて聞くよ」
私も今日鈴井老人から始めて聞いたことである。稲にそのことを話した。
「ふーん、なにかありそうね、赤い茸も関係あるかな」
稲もうなずいている。
夜風に吹かれながらビールを楽しんでいると、菅原君は出前に刺身をいれてもってきた。ビールも三つ運んできた。
「もう、ビールもなくなっていると思って」
「気が利くわね」
稲は空になったジョッキを前に置いて、ひったくるように彼の手から新しいジョッキをとった。
「僕の分も持ってきてしまいました」
「えらい、そうじゃなきゃ、おもてなしはできないわ」
稲がおおげさに感心したようすでほめた。
「ねえ、菅原さん、鉄火という人のこと聞かせてくれない」
「なにをでしょうか、僕は新参もので、この町の人間じゃないのでよく知らないんですが」
「知っていることでいいわ」
「漁の上手な漁師さんだったようです、わからないことがあると、だれでも鉄火さんのところに教えてもらいに行くようでした」
「頑固なおじいさんかしら」
「そりゃ、頑固なところもあったようだけど、誰にでも静かに教えてくれたそうですよ、組合長なんか、鉄火さんのことを漁の神様って言っていました」
「お孫さんのことを知ってる」
「ええ、紗英さんは秋さんの仲のよい友達だったので、組合にもよく来ていましたから、きれいな人でした、僕より二つくらい上だったと思います。だから二十一歳だと思いますね」
「秋さんはいくつくらい」
「紗英さんより少し上だと思います」
「紗英さんどうしてなくなったのかな」
「誰もよく知らないみたいですよ、知っているのは鉄火さんだけのようで」
「ふーん」
「ともかく、紗英さんがなくなった後、鉄火さんは何もする気がなくなったようでした、それに珍しく、赤い顔で激しく怒っていたんです、でも何に怒っていたのか誰も知りません」
そこに秋ちゃんと同僚の女の子たち三人が桟敷に上って来た。
「あら、菅ちゃん、もう飲んでるの」
秋ちゃんの同僚が菅原君を見て寄って来た。
彼は見つかったという顔をした。
「ごめんなさいね、稲さんが無理やり飲ましちゃったの」
私が彼を擁護した。
「今、皆さんのも持ってきます、何を食べます」
「あら、いいのよ、私たちは自分でするから、今日は呑み放題食べ放題ですって、組合長さんが、鉄火さんからもらったお金は全部使うって豪快に笑ってた。菅原君も好きなもの食べたらいいのよ」と、秋さんがフォローした。
「ほら、私たち、めったに食べられないステーキをもらってきた」
同僚の女の子がビニール袋をあけて見せた。
「おいしそうですね」
「ねえ、菅原君、一緒に飲もうよ」
「でも、僕は、お客さんたちの接待役なので」
女の子たちが私と稲をみた。
「あ、企画会社の方たちでしたね、あの山車はすてきだったで、秋ちゃんが引き立ってよかった」
元気な女の子たちだ、きっと猟師さんの娘さんたちなのだろう。
「秋さんが綺麗だから山車が引き立ったのよ」
私が言うと、秋さんは独り言のように言った。
「山車に乗っている間、紗代ちゃんが傍にいるような気がして何か不思議な感じでした」
「鉄火さんの思い入れの祭りだから、後でいろいろ教えてくださいね」
私がそう言うと、組合の女の子たちは私たちの隣の桟敷に座った。
そこへ半纏姿の青年が来た。
「菅原君、これから屋台が二つここにくるからね」
「何が来るんです」
「寿司とステーキの屋台を別にあつらえてあるんだって、桟敷用だそうだよ、市長と町長、町議の人たち、小学校の校長先生たちが来るそうだ。漁業組合の人たちもくるよ」
桟敷はいくつか作られている。
秋さんに聞いた
「あの、神輿を担いだ四人の男の子たちを知ってるの」
「ええ、知ってます。今の若い人は可愛そうですね」
「どうして」
私は秋さんからそのような返事が来るとは思っていなかった。
「あの子達は、脱落組みです、というより脱落させられたのでしょうね、高校の時音楽のグループをつくっていて、綺麗な音でとてもよかったんです。私も聞いていて幸せでした。でも大学に行かなければならなかったのですね、無理だったのです。あの頃のままだったら、神輿も盛り上がっていたのでしょうけれど」
「あの赤い茸はどうしたのかしら」
「わかりません」
秋さんはうつむいた。
「紗英さんのおじいさんが、あの優しいおじいさんが、赤い鬼のようになったのです、私には分かりませんが、こういうこともあるのかと、思いました」
その話は前にも聞いた。だが秋さんの言っていることは私には分からなかった。
桟敷にはこの町の名士が集まりはじめ、漁業組合の理事長も来た。
私が挨拶すると、「来年もします、このような大掛かりなことはできないと思いますが、山車と神輿が二つあります、町の歴史の始まりです。またよろしく」
と理事長は言った。
マノンが来た。
「お疲れさん、私たち飲みはじめちゃった」
「そちらもご苦労様、結構楽しかった。でもあの神輿は想像できなかったわ、あの赤い茸の仕掛けすごいわね、それ以上にやつれた彼らにもびっくりした、あんなに疲れるものなのね」
「あれ私の仕掛けじゃないのよ」
マノンはビールを一気に飲んだ。
「え、本当、どうして茸がでてきたの」
「私も分からない」
「あ、秋さんもいるんだ」
マノンは秋さんが仲間と話をしているのに気がついた。
「ステージにいた秋さんの顔と違うわね」
「どんなふうだった」
「わからない、でも別の人の顔だわ」
「私たち何かの力に動かされたみたいね」
稲が口を挟んだ。確かに不思議な糸に絡まっているようだ。
「鉄火という人かな」
皆うなずいた。
「でももう終わったんじゃないのかな、花火を楽しんで帰ろう」
そこへ、長塚組合長が仲間ときた。
「皆さん、おかげで、とてもよい祭りになった、県の人たちもきてます、来年は県が補助をつけてくれるかもしれんですよ、今年ほどには出せなかもしれんけど、またお願いするとおもいますよ」
「うれしいです、こちらこそよろしくお願いします」
「神輿担いだやつらは調子が悪くなって家で寝ているようだ、弱いもんだ」
「来年は神輿が二つになります」
「担ぎ手はいくらでもいるから大丈夫さ、今日の花火はすごいから、楽しんでくださいよ、私は県のお偉方のとこにいかなきゃ、ほんとはここで飲みたいね」
彼は笑いながらちょっと離れた桟敷のほうに行った。
その日の花火はすばらしかった。海の上から打ち上げる花火をまともに見たのは始めてである。水平打ちという海面の上で半分に開くすごい花火も見た。決して大きな花火大会ではないが気持に残るものであった。
次の日、組合事務所で、経理のうちあわせを終え、午前中に東京に戻った。その日はそれでおわりにして、それぞれの家に帰った。
家に戻りテレビをみていると、静岡の昨夜の催しが紹介されていた。山車や舞台、それに高級屋台のことはこと細かく説明されていた。このようにして鉄火じいさんのお祭は終わった。我々にもとてもよい経験となった。
そのおかげもあり、それ以後、市や町のイベントの相談が増えた。
あれから半年が過ぎた。静岡の漁港町から、来年も祭でステージをやりたいのでマネージを頼むとも連絡が入った。ステージはマノンに頼むことで、私と稲はやることもなかった。あの屋台の味は忘れられないが、今年もいくつか高級屋台というふれこみで、かなり高い値で出すと言うことらしい。遠くからくる観光客には受けるだろう。今度は自腹で行ってもいいかもしれない。
私はある企業のイベント会場におく彫刻や絵の選定に忙しかった。稲は日本酒の醸造もとから頼まれたコマーシャルの背景や人選などをおこなっている。本人がでてもいいほど彼女の和服姿は板についてきた。
春めいてきて、オフィスから見える町の中に若草色が目につくようになってきた。
「長塚組合長から私にメイルが入ったわ、大変なことが書いてある」
マノンがデスクにくるように手招きした。
稲と一緒にマノンのPCの画面をみた。
」昨年神輿を担いだ四人が昨日病院で死にました。原因不明だそうです。神輿を担いだ後から入院していました。何かの感染らしく大学病院で調べているそうです。神輿の赤い茸も話題になったようですが、神輿を調べても菌らしきものは付着していないということでした。それよりも彼らは薬をやっていたグループの仲間だったようで、とあるマンションがアジトでした。マジックマッシュルームという幻覚を起こす茸を吸ったり、女の子に悪さをしていたとのことです、それでからだが弱っていたらしい。鉄火の親父さんの行方は今もわかりません。とりあえずお知らせしておきます」
とあった。
「それにしてもわからないことだらけね」
稲が窓から外を見て指差した。
「ねえ、救急車が来ているよ、お寺に」
奇勝寺の正門に救急車が止まっているようで赤い光が点滅している。救急車の音は一日何回も聞こえてくるので気にとめていなかったので気がつかなかった。
「あの和尚さんかしらね」
「ちょっと行ってみない」
そういうことにはあまり関心がない私ではあったが、このときはなぜかそこに行かなければならないような胸騒ぎがした。
二人も同じ気持ちだったとみえてオフィスに鍵をかけて外にでた。
三人してお寺の正門に行くと、担架の上に老人が乗せられ救急車に運ばれるところだった。あの住職らしい和尚さんが救急隊員に説明しているところだった。パトカーも来ている。
警察官が血の付いた日本刀を運んでくるところだった。
「やくざの喧嘩かしら」
マノンが言った。
「でも相手がいないわ、相手がいれば警察がもっとあわただしく動いているわ」
稲がずかずかと正門の方に近づいていった。
「どうしたんです」
と和尚さんに声をかけた。和尚さんは覚えていたようで、
「自殺したんです。お嬢さんの墓の前で」
「日本刀でですか」
「割腹したうえで、首も切ったのです」
「自殺の理由は何ですの」
「わかりません、お嬢さんの死と関係あるのだと思います。古い檀家で、先祖は偉い武将だったそうですよ、老人は漁師だったのですが、律儀な方で、お寺への寄進はきちんとなさってくださっていました」
それを聞いて、三人で顔を見合わせた。同じ思いのようだ。
「もしや、鉄火さん」
「なぜご存じなのです、工藤鉄火さんを」
私たちの背筋に冷たいものが走った
「遺言らしきものが自殺したそばにあったそうで、警察が持っていきましたから、そのうちわかると思います」
私はふらついて、マノンの肩につかまった。
和尚さんは誰かと話したかったのだろう、ほっとした顔をしていた。
「お忙しいところおじゃましてすみません」
私たちはオフィスに戻ってため息をついた。
「やっぱり、私たち、鉄火さんの計画を実行する為に選ばれたのね」
「うーん、そうとしかいえないわね」
マノンはメイルを打った。
「誰にうってるの」
「長塚組合長よ、鉄火さんがみつかったって知らせるの」
鉄火氏の遺書には紗英さんがあの四人組に無理矢理仲間に引き込まれ、薬でものまされたことが書いてあるに違いない。
秋さんは薄々知っていたのではないだろうか。秋さんは紗英さんのメイクで山車に乗ったのだ。
しかし、それも鉄火さんの気持ちがそうさせたのである。
今年の祭も必ず三人で行こう。きっと奇勝寺とは別に、あの町のどこかに、漁港組合の人たちにより、二人の墓が建てられているのに違いない。手を合わせなよう。
神輿茸
私家版第四茸小説集「茸人形、2018、234p、一粒書房」所収
茸写真:著者 東京都日野市南平 2017-9-2


