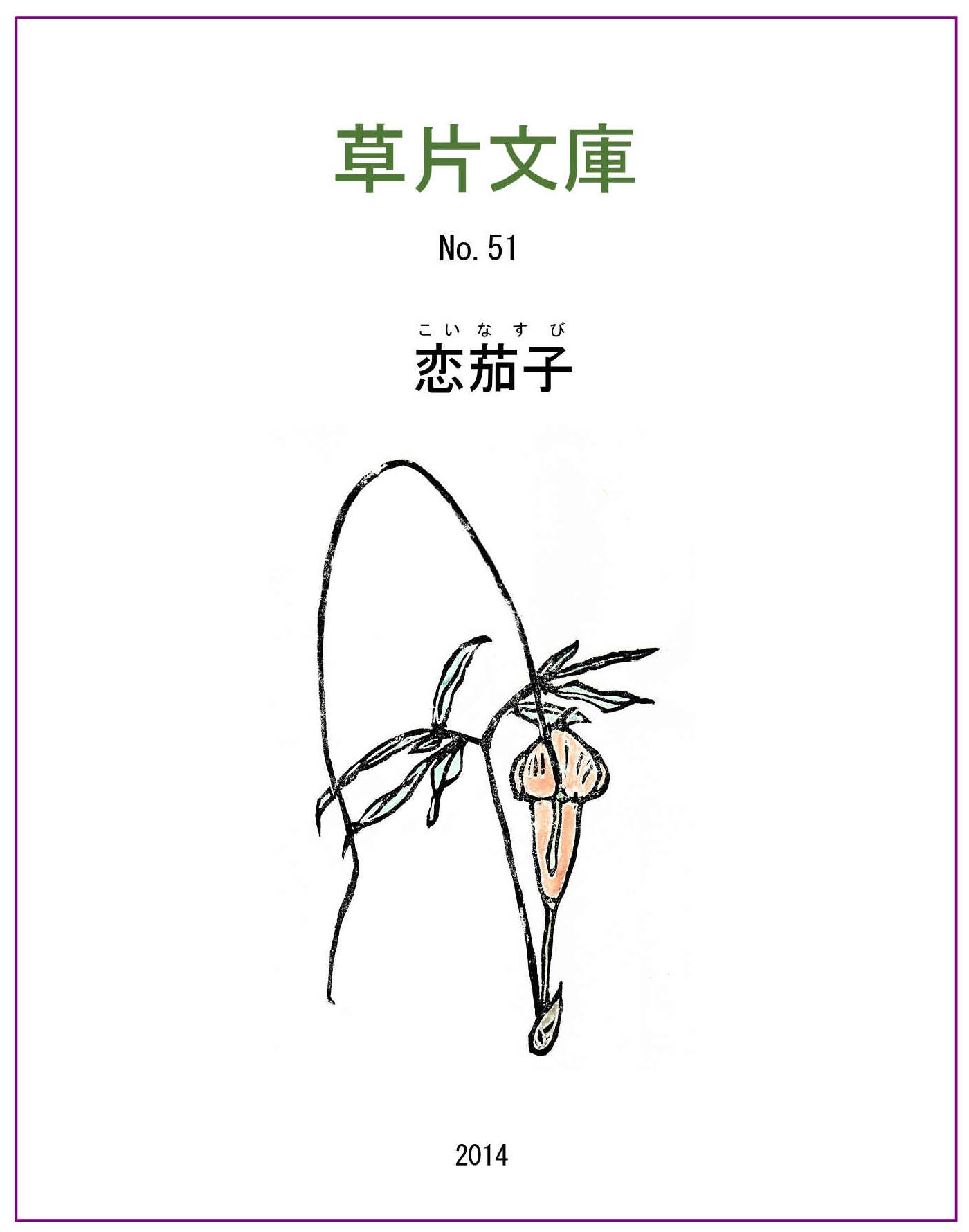
恋茄子(こいなすび)
林の中から悲鳴が聞こえる。
ぎゃあと血を吐くような声である。気持ちのよいものではない。
ここに着いたその日の夜、その声で寝られなかった。持ってきたウイスキーを炭酸で割って飲んだ。真夜中に必ず悲鳴が聞こえる。
伊豆の貸し別荘にきて三日目になるがまだ慣れない。最初の朝、別荘を管理している老人になんだろうと尋ねると、あれは鳥の鳴き声だという、白鷺の類があんな声で鳴くという。
何とも苦しそうだ。真夜中に白鷺が鳴くのだろうか。
真革神子(しんかわしんこ)は東京の大きなアパレルメーカーに所属するデザイナーである。日本画の雰囲気を洋服にうまく取り込み、若い子にも年寄りにも気に入られるデザインを考えることで重宝されている。
ここのところ疲れがたまってデザインがうまく頭に浮かばない。来年の秋のデザインを決めなければならない。仕事の疲れだけではない。男とのつまらない感情の縺れに、この年になって失恋に似た胸の痛みを感じている。
神子は十日ほど静養のため休暇をもらった。この数年働詰である。秋になろうとする今、来年初夏の新しいデザインはとっくに考え、製品もほとんど出来上がっている。マーケティング部門は忙しいだろうが、彼女はちょっと時間がとれる。
伊豆を選んだのは、単に近くて手頃なことと、この貸し別荘には掛け流しの湯があることだからにすぎない。
いくつもの別荘が海に近い小高い丘の林の中に点在している。この時期になると借りる人はいないのだろう、夜になっても明かりがつく家はそんなにない。隣の別荘も空いているとみえ人の気配はしない。
神子はスケッチブックを持ってきている。洋服のデザインを考えるのではなく、自然や植物をスケッチするためである。どこかで違うものに接しないと、固まった頭をほぐすことができない。
神子は理科が苦手であった。だから植物や動物の名前も知らない。しかし形には興味をもっていて、日本画や染め物に描かれている動物植物は目に焼きついている。和服の文様は植物が装飾的に配置されているものが多く、その絵の見事さは名の知られていない職人のものであっても驚くほどである。職人たちは生きものをつぶさに観察している。それに比して、神子は自然を見つめ、正直に表現したことがない。これは神子の欠点でもあることを知っている。一朝一夕で職人のようになれるわけはないが、休暇中に植物観察の真似をしてみようと思い立ったのである。
貸し別荘地の林の中にもいろいろな植物が生えている。敷地はかなり広く、小道をへだてて、さらに林が広がっている。その林の先には個人の別荘地があり、瀟洒な家が点在している。
幸い天気に恵まれたこともあり、午前中は林に行く道端に生えている草をスケッチした。よく見かける草もたくさんあるが、改めて見ると奇麗なものである。
蚊帳釣り草があった。これは名前を知っている。蚊帳をつかったことはないが、おばあちゃんが蚊帳釣り草の葉を丸め、蚊帳のようにしてくれたのを覚えている。よく見ると繊細で日本的なものである。神子は手早くスケッチブックに描いた。見たものを即座に絵にするのは慣れている。蚊帳釣り草の葉の先に緑色の蜘蛛がおとなしくしている。それを拡大鏡で見たように大きく描いた。
蚊帳釣り草の隣に生えている平べったい葉っぱの植物も絵になる。いたるところに神子の知らない草がいい形で生きている。
林の中にはいると、羊歯が大きな葉を広げている。奥にすすむと紫色の花を付けた奇妙な草が群れていた。破れた傘のような葉が伸びていて、根元から紫色のラッパのような花が伸びている。花の頭が壷を覆うように前にたれ、壷の中から舌というかツル状のものが伸びて葉っぱに絡み付いている。お化けのような花だ。神子はこの奇妙な草に体ごと吸い込まれていくように感じた。神子には珍しい植物に見えたが、この辺ではよくあるものなのだろう。それにしてもたくさん生えている。
神子はしゃがみこむと、念入りに、いろいろな角度からスケッチをした。
絵を描いていると、ふとこの花が自分に対し嫌悪しているように感じた。本当の自分は描かせてやらない、といった拒絶が感じられるのはなぜだろう。
何枚か絵を描き終えた神子は、改めてまじまじとこの草を見た。何か物足りない。採って帰ってテーブルの上でもう一度しっかりとスケッチをしよう。そう思った神子はこの草に手を伸ばした。
花がさっと神子の手を避けるように揺れた。
神子が伸ばした手は傘のような葉を折っていた。もう一度手を伸ばし花の根元を捕まえると折採った。千切りとった茎から血が湧き出るように見えてはっとした神子はあらためて茎を見た。青い汁が付いているだけである。
神子は花と葉を持つと、あわててその場から立ち上がった。
貸し別荘にもどると、管理人が神子の家のベルを押すところだった。
「なんでしょう」
「あ、お出かけでしたか、別荘会社のほうから近くのレストランの割引券を渡すのを忘れていたので届けるように言い付かりました、お届けにきました」
「ありがとうございます」
管理人が封筒を差し出しながら、神子の持っている花を見た。
「浦島草ですね、たくさんあったでしょう」
「ええ」
「この辺はその草が多いのですよ、だけど今年は不思議なことに、今頃盛んに咲いているのですよ、普通は四月の終わりから五月の連休のころなんですがね」
「浦島草って言うんですね、始めて見たものですから」
「都会の方なんですね、林のようなところは必ず咲いているものですよ、里芋の仲間です」
「そうなんですか」
「浦島が、釣りをしているような風情でしょう」
「それで浦島草なのですか」
「だそうですよ」
神子は改めて浦島草を見た。確かにそのような形にも見えるが、神子にはどうしても、神子に対して悪意をもっているような雰囲気を払拭することができなかった。
「どうですかこの別荘」
「静かで、周りもきれいでいいですわ」
「ちょっと距離はありますが、海岸の方にも行かれると面白いですよ、おいしい魚の店もありますよ、割引券が入ってます」
「ええ」
「用事がある時は電話ください、それでは」
そう言うと老人はもどっていった。
神子は部屋にはいると、昨夜飲んだビールの空き瓶に浦島草をさした。長いべろがふらふら揺れている。茶色の瓶に浦島草の花は何となく人間くさい。
風呂を浴びたくなった。掛け流しの温泉がついている、贅沢な一戸建ての貸し別荘である。神子のように一人で借りる人は少ないだろう。神子は着ているものを脱ぎすてると湯殿にはいった。かなり広い。
大きくはないがしっかりとした桧でできている湯船から、少し茶色がかった湯があふれている。湯をすくい体にかけ中に入った。口元まで湯の中に沈んだ。湯に味がある。塩味のある海の湯だ。
昼間からゆったりと湯につかるなどという贅沢は久しぶりである。手足を伸ばして、自分のからだを見た。不透明の硝子窓からはいる光が肌を照らし出す。マンションの電気の明かりとは違った神子のからだがあった。マンションの風呂場の中では自分のからだに自信があった。張りのある乳房、締まった腰、太目の足の付け根、いつも自分に自信をもたらしてくれるはずのものが、昼間の間接的とはいえ太陽の光にさらされた乳房やからだは、なぜか弱弱しく疲れを感じさせるものであった。この五日間で張りのあるものにしなければと気持を静めた。
湯殿からあがると、長い髪を丁寧に洗った。シャンプーとリンスはそのために東京からもってきている。髪を長くしている神子は髪の手入れを怠ることはない。その黒髪が彼女のトレードマークである。いつもはポニーテールにしているが、気が向くと、一本に束ねて背中に垂らしたり、束ねずにそのままにしていたりすることもある。仕事場ではそのような姿を見せないが、家にいるときにはその方が多い。男っ気の少ない神子であるが、その様子を見た男性は驚くほど妖艶な神子を見るであろう。
夕方まではまだ間があるので海岸まで降りた。海岸沿いの道にはしゃれたレストランやバーが並んでいた。外車が何台か止まっている。帰りは代行を頼むのであろう。
道から砂浜に降りて海を見ていると、赤いスカートに白いブラウスを着た女の子が神子の方に向かって歩いてきた。ずいぶん色の白い子で、大きな黒い目をした丸い顔立ちはロシアやそのあたりの国を連想させる。神子と同じように髪を長く腰まで垂らしている。小学校の五、六年生ぐらいだろう。
少女は突っ立って海を見ている神子の脇にくると、笑窪を寄せて大人のような会釈をした。
神子は子供が苦手である。嫌いなわけではないが、どのように付き合っていいかわからないのである。神子も少女を見て軽く笑った。
少女は神子の前をゆっくりと通り過ぎ、道を横切って林の中の別荘地へ行く道に入っていった。
少女の後姿が木々の間に消えて行った時、神子ははっと気がついた。あの少女が着ていた白いブラウスと赤いスカートは神子がデザインしたものである。近くでみれば、白い絹のブラウスには大きな夕顔の透かしが入っているはずである。赤いスカートには深紅のボタンの花が浮きでていたはずである。彼女の和に対するこだわりである。しかし、子供の服は作ったことがない。そういえば神子の前を通っていく時、あの子の目の高さは神子と大して違わなかった。神子の身長は百六十二センチである、小柄ではないが背が高いほうでもない。最近の小学生は大きい子も多い、母親が買って与えたのかも知れない。神子はすこしばかり嬉しくなった。
神子は夜寝るのがいつもは遅い。マンションでは早くても二時頃である。テレビの深夜番組を見ながらビールやワイン、気が向けばウイスキーを飲んでそれから寝る。ここにきてからは、湯に入りすこしばかり酒を飲むと眠気がおとずれる。それでもあのぎゃあと地を抜かれるような鳴き声のおかげで眠りにつくのは十二時過ぎだった。
その夜、その鳴き声が聞こえなかった。異様な静けさに逆に神子は眼がさえた。スケッチ帖を開いて、ビンに差した浦島草を描こうとしたが、鉛筆がうまく動かない。結局ウイスキー片手にテレビのスイッチをいれた。
深夜放送は若い子達が中心の番組が多い。今の子の好みや流行(はやり)を知るにはいい。しかし内容は全くつまらない。もう二時をまわっている。眠くはないがベッドでよこになろうかと、用意をし始めたとき、玄関のドアをとんとんとたたく音が聞こえた。風の音ではない。明らかに人がたたく音である。こんな夜中に管理人が来るわけはなく、気味悪さを感じていると、またとんとんと音がする。乱暴なたたき方ではない。神子はおそるおそる入り口に行き、覗き穴から外を見た。玄関灯に照らし出されて、海岸で会った少女が立っている。白いブラウスに赤いスカート、あのときのままだ。
こんな夜更けになんだろう、ほっとくこともできないと思った神子はチェーンをかけたままドアを開けた。
少女はドアが開いたのを見て顔をほころばせ、
「こんばんわ」と言った
「何かしら、こんな夜更けに」
「お姉さん、私これから、とるの」
「なにをとるの」
「悪い花だから引っこ抜くの」
神子には少女が何を言っているのかわからなかった。
「いっしょにいく?」
少女が神子の目をのぞきこむようにして言った。黒目がちの眼がきらきらしている。
こんな夜更けに出歩くのは尋常ではない。神子はまずは保護しなければならないと考えた。
「ちょっとお入りなさい」
チェーンを外して女の子に声をかけた。
「うん」
少女はすなおに肯いて中に入り靴を脱いだ。白い絹のブラウスには大きな夕顔の透かしがあった。赤いスカートには赤い牡丹の花が浮き出ている。神子のデザインに間違いがなかった。
「お名前は」
「しんこ」
神子は耳を疑った。
「しんこちゃんなの、どのような字を書くの」
「かみのこどもよ、お姉さんは」
「おどろいたわね、同じなのよ」
「そう」
「こんな夜更けにどうしたの、お父さんとお母さんが心配しているでしょ」
「寝ている」
「近くなの」
少女はうなずいた。
「夜遅く外にでて怖くないの」
「楽しいの」
「私のところよくわかったわね」
「うん、家に入るところ見ていた」
神子はどのようにあつかっていいか考えあぐねていた。
「何か飲む」
「いらない、ねえ、お姉さん、引っこ抜きにいこうよ」
「なにを」
「蛇草」
「どうして」
「悪い奴だから」
ここでこうしていても埒が明かない、蛇草とやらを一緒に探して、そのまま家に送っていった方がいいだろうと神子は判断した。
「ちょっと待っててね、用意するから」
神子はズボンをはき、ブルゾン風の上張りを羽織った。備え付けの懐中電灯を持つと家を出た。
少女の神子は神子の手を握った。
「神子ちゃん、そのお洋服、お母さんに買ってもらったの」
神子が聞くと、少女の神子はうなずいた。
「でも、大人の服だったので、お母さんが私に着れるように細くしたの」
「大人の服なのに、どうして欲しかったの」
「お花がきれいだから」
神子は、この神子が好きになってきた。
「こっちよ」
神子が神子の手を引っ張った。神子は雑木林の中に引っ張られていった。
「ほら」
小女が指差したのは浦島草だった。
「浦島草って言うんでしょう」
「蛇草って呼んでるよ」
「でも、なぜ、悪い草なの」
「嘘をついたの」
「お花が、嘘をつくの」
「蛇草は毒だって」
「そうなの」
「だけど、死ななかった」
神子は神子が何をいっているか理解できなかった。
「あの蛇草よ、嘘つき」
神子はちょっと大きめの赤っぽい花をつけている浦島草のそばによると、顔をなでるようにして、紐のような舌をいきなり引っこ抜いた。
そのとき浦島草がぎゃあと大きな声で鳴いた。いつも夜中に聞こえてくる声である。管理人は鷺が出す声だと言っていたが。
舌を千切られた浦島草の花は左右に首を降ると悶えた。切られた舌から赤い液を放った。血のように赤い汁は少女の神子の白いブラウスに赤い水玉模様をつくった。
「ふふふ」
少女の神子が笑った。手を伸ばすとのたうっている浦島草の花をひっぱった。首がすぽっと抜けると、浦島草はまたぎゃーっと悲鳴をあげた。
「ふふふ」
神子は浦島草の花をぽいと捨て、足を踏ん張って両手で根本をつかむと、力一杯引き抜いた。また、ぎゃーと声が上がった。里芋のような根が抜けてきた。
少女の神子は芋を持ち上げると笑った。
「これ、毒があんまりないの、もっと強いかと思ってたのに」
神子は少女の神子を見た。少女の黒い目が赤い。
「毒はない方がいいでしょう」
「そーを」
少女の神子は浦島草の芋をぶらぶらさせた。
「それじゃ帰る、さよなら、また一緒にきてね」
少女の神子は急に走りだすと、あっと言う間に見えなくなってしまった。
あたりは真っ暗闇となり、懐中電灯の光が打ち捨てられた浦島草の残骸を照らし出している。
木々の上にあったはずの星空が見えない。
ぞくっと身震いをして神子は懐中電灯を前にむけた。少女についてきたこともあって帰り道がわからない。周りは浦島草だらけである。今本当にここに少女がいたのだろうか。心細さと自分の頭が信じられなくなって足がすくんでいる。
かすかに海の音が聞こえた。神子はそれで救われた。海に出れば場所が分かる。音のするほうに何とか足を動かして、林の中の小道に出ることができた。
やっとの思いで自分の貸し別荘にもどることができた。時計を見ると三時前である。ということは、少女と一緒に家を出てからまだ三十分か四十分である。
神子は何がなんだかわからずベッドに倒れ込んだ。
次の日も良い天気であった。いつも九時頃に目を覚まし、ベッドの中でうだうだと堕情な時間を楽しんでから起きるのだが、その日はすぐベッドからおり顔を洗った。
神子は水を一杯飲んだ。外に出たいとなぜか急いで服をつけた。昨夜のことが夢なのか現実なのか確かめたかったのである。
朝日の差し込む明るい林の中をいくと、昨夜連れて行かれたと思われる場所はすぐわかった。細い道が一本林の中を貫いている。その道を歩いた。少ししか歩いていない。右手確認しながら行くと、浦島草の群落が見えてきた。一面に紫色の花が顔をもたげゆらゆらと揺れている。
群落の中に入っていくと、神子は草が乱れているところを見つけた。昨夜二人で入ったところに違いがない。いくつかの浦島草が倒れている。
立ち止まってのぞくと、浦島草の花が一つ落ちている。昨夜少女が折って捨てた花だ。あの子は根っこも引っこ抜いた。そこには穴があいていてどす黒いものが溜まっていた。
神子はそれを見ると怖くなった。すぐに引き返した。あの子と一緒に来たことは確かである。神子は部屋に入ると裸になって、風呂に飛び込んだ。じっとあったまっていると、昨日の夜中に浦島草を引っこ抜いて笑っていた少女の顔を思い出した。
気持ちが落ち着いた神子は、風呂から出て朝食の用意をした。
テレビをつけ、テーブルを前にしてコーヒーを飲んでいると、ニュースが目にとびこんできた。木曽の御岳が爆発したことを報じている。三千メートル級の山のわりには優しい山で登山者が多い。急に噴煙をあげたようでかなりの人が犠牲になっているとの報道である。助かった登山者の中に湧き出る噴煙を入道雲と間違えたという者もいた。それほど穏やかな山だったのに、いきなり活動をはじめた。まだ噴火は止んでおらず、火山灰に埋もれている人が救助を待っているという。熱い灰に囲まれて苦しいだろうなと神子は窓の外を見た。噴煙なんて他所事だというように朝の光の中に木々が気持ちよさそうに立っている。
食事の後片付けをして、スケッチブックを開いた。こちらに来てから描いた浦島草のスケッチが十五ページもある。ずい分描いたものだ。だが、さっき見たあの娘が引っこ抜いた浦島草の根の穴の中にあった赤黒いものが頭から離れない。
描いたスケッチがなんだか物足りない。ああ、そうかとあの根の塊がないからだ。少女の神子が引っ張りだした芋のような根である。あの固まりから浦島草が生えているところを描くと、動物に近い感じを醸しだすことができる。それがないと生きた浦島草ではないような気がしてきた。
元気な浦島草の根が見たい。今日は外には出たくないとまで思っていた神子は、そう思い立つと浦島草の群れのところにもう一度いくことにした。
別荘には塀こそないが小さな庭のようなスペースがあり、スティール製の物置が建物の脇に置かれている。借りるときに説明があったが、スコップや籠などがそろっているはずである。春は山菜採りにいいところだとパンフレットに書いてあった。そのために用意されているのだろう。物置を開けるとあった。
神子は籠と小さなスコップと花切り鋏をもって庭を出た。
林の中にはいると、浦島草の群落に行き、元気の良さそうな浦島草を選んで根本にスコップを入れた。抜こうとしたがなかなか抜けない。かなり深く掘らなければならないようだ。回りの土をかきわけ、やっとの思いで芋が顔をさした。根元をもって引っ張ると、球根のような芋のようなものがついたまま浦島草を取ることができた。ずいぶん深いところからはえているものだ。あの日の夜中にあの娘がとると、ぎゃあと叫んだが、あれは幻聴か。
たくさんの浦島草を採った。籠を持ちあげると、満員電車の人間の頭のように、奇妙な花が右へ左へゆらゆらそろって揺れる。この図柄はちょっと面白い。写真に撮っておこう。首だけ動いているようで薄気味の悪いものだ。
神子は別荘に戻ると、水を入れたバケツに浦島草をつけた。花をすべて同じ方向に向け、写真を撮った。気味悪さもあるがユーモラスでもある。何枚もの写真を撮った。これをもとにデザインを考えると、面白い服が作れそうだ。
写真を撮り終わった浦島草はそのままバケツにつけたままにした。
その夜中、キュウキュウという声で目が覚めた。子犬が鳴いているような、動物の子どもが鳴きあっているような声である。外から聞こえてくるのではなさそうだ。
時計を見ると二時を少し回っただけである。寝付いたばかりだ。野生の動物が別荘の屋根裏などに住み着いていることはよくあることだ。ヤマネやリスが入り込むことが多いらしく、ここの別荘のパンフレットにも写真が載っていた。動物好きにはたまらないのだろう。そういった動物の子どもでもいるのだろうか。
キュウキュウという鳴き声がやんだ。もう一度、目をつむったそのとたん、ぎゃあといつもの大きな叫び声が聞こえ、神子は完全に目が覚めてしまった。
またぎゃあと叫び声があがった。
キュウキュウという鳴き声も再び聞こえてきた。
起きあがると、キュウキュウという声の主を探した。キッチンに行くと声が大きくなった。明かりのスイッチをいれると、バケツの中の浦島草の花が揺れながらキュウキュウと声を上げている。顔をそろえていたのに、今はあちこちを向いて、どの花もキュウキュウと鳴いている。
花に顔を近づけてみた。べろの付け根あたりから聞こえてくる。筒状になっている花の奥からでている。鳴く花とは珍しい。
そんなに大きな音ではないが気にはなる。神子は外に出すつもりでバケツを持つと、玄関の戸を開けた。
開けたとたん神子は心臓が飛び出すかと思うほど驚き、バケツを取り落としそうになった。
「神子ちゃん、今日も行ってきたの」
玄関の前に、少女の神子が根っこのついた浦島草を持って立っていた。
少女はうなずいた。
さっきの大きな叫び声はこの子が引っこ抜いたからだ。
「お姉さんも、採ったんだ」
「ええ、昼間に行ったの、この花をスケッチしようと思ったから」
「採ったとき泣き叫んだでしょう」
「いいえ、何も鳴かなかったわ」
「それじゃあ、つまらないねえ、弱虫のやつを探さないと」
言葉が乱暴だ。
「弱虫は泣くの」
「そう、それが楽しいじゃない、ふふ」
少女の目がきらきらした。
「でも、水に差したこの花達が、キュウキュウ鳴くの、うるさいの」
「そうよ、切り口が痛くなってきて、我慢強い花も置いておくと鳴くの、めそめそとね」
「神子ちゃん、こんな夜更けに、お母さんとお父さんが心配するわよ、早く帰ったほうがいいわよ」
「お姉さんに、これをもってきたの」
神子が差し出したのは、真っ白な浦島草の花であった。
「白いのね」
「珍しいの、弱虫だけどね、あげる、水に差しておくと面白いわ」
少女の神子は白い浦島草を神子に押し付けると、
「おやすみ」と、走って行ってしまった。
神子はほっとすると家に入った。玄関に置かれたバケツの中の浦島草が,キュウと鳴いて静かになった。
白い浦島草の花は奇麗だ。瓶にさすと緑色の傘をさした色白の女性が立っているような風情になった。
神子は写真を撮ってベッドに入った。
朝、神子が目をさますと部屋の中が靄っていた。なんと蒸し暑い日であろう。台風がくるのだろうか。しかし天気は良いようで、窓から見える景色は明るい。
神子は湯につかり、朝食の準備を始めた。今日もスクランブルドエッグをつくり、ソーセージも炒めた。買っておいたフランスパンは少し古くなっている。スライスすると電子レンジで焼いた。
テーブルにつくと、焼いたパンにソーセージと卵をのせてかぶりついた。なんだか食欲がある。
テレビをつけると、昨日起きた御嶽山の爆発を映していた。硫化硫黄やガスのせいでなかなか救出が難しいらしい。山はまだもくもくと煙を吐いている。
ふと、テーブルの上の浦島草を見ると、真っ白な花の奥から白っぽい煙のような靄が立ち上っている。蒸気のようにも見えるし、白い粉のようにも見える。
テレビの中で黒っぽい灰にまみれた下山者がインタビューに応じていた。頭を守って何とか下山できたが、背中には石が当たった痣がたくさんあると言っていた。山頂の山小屋は灰に埋もれている。まだ中に人がたくさんいるらしい。
生きている限り何が起こるかわからない。コーヒーカップをテーブルに置いたとき、テレビのスクリーンが白く靄った。テレビカメラにまで噴煙がせまったのかと思ったが、もう別のニュースに変わっている。
いきなりとても気持ちのよい匂いが漂ってきた。食欲が増すような香である。どこからだろうと見回すと、匂いのもとは白い浦島草のようである。
もっと何か作って食べよう。神子は冷蔵庫を開けると卵を二つとりだした。今度は目玉焼きを作ろう。手際よく作ると、もう一度フランスパンをレンジに入れた。コーヒーをもう一度いれ、二度目の食事を始めた。朝はあまり食べない神子にとって初めての経験である。
パンにバターを塗った。ふと手を伸ばし、白い浦島草の花を瓶から抜き取ると、パンと一緒に口に入れた。とてもよい香りが口中に広がり、頭の中がすっきりしてきた。
コーヒーを喉に流し込むと、いたく満足した。なんだか不思議な満足感だ。
空気が湿っぽく熱い。神子はいきなりキッチンで着ているものを脱ぎ去ると、風呂場に行き、風呂にもう一度飛び込んだ。
気持ちがいい。うっとりして窓をみた。スリガラスを通して太陽の光が浴槽を照らしだしている。神子は手足を伸ばした。乳房がぴんと張りつめている。細い足先が桧の肌に触れると体がしびれるように気持ちがよくなった。
寝てしまいそうだ。
目を閉じた。
急に日が翳ったようだ。浴槽が暗くなった。どんどん暗くなる。
目を開けると、窓が黒っぽくなっている。まさか火山灰じゃないでしょう。と思っていると、あっと言う間にガラスが真っ黒のもので覆われてしまった。暗い。
電気をつけなきゃと思ったが、神子はあまりにも湯の中が気持ちよく、動きたくなかった。風呂場の中は脱衣場に点いている電灯の明かりでどうやら見える。
自分の口の中から白い浦島草の香りが漂ってくる。神子は自分の吐く息に酔いしれた。目を瞑り上を向いてふーっと息を吐いた。目を開けた。天井が見えた。その時、がしゃっという音とともに天井から白い腕が突き出された。
腕の先の手は風呂場の中で何かを探すように動き回り、浴槽の中で伸ばしていた神子の左足をつかんだ。神子があっと声をあげた。神子は勢いよく天井に引き上げられ、神子の頭が浴槽の湯の中につかった。うわー、神子が叫んだ。さらに天井にもちあげられ、裸のまま逆さ吊りになった。神子は手をばやばやさせ、自分の長い髪が束になって床に向かってたれた。両手を振り回して裸のまま暴れまわった。あまりの痛さに「ぎゃーっぎゃー」と大声を上げた。
腕はそのまま神子を持ち上げ、天井を破って神子を外に引きずりだした。
逆さのまま裸の神子は涙を流しながら前を見た。
大きな少女の目が神子の目の前にあった。
「ふふふ」
少女が神子の足を持ち上げると神子は裸のまま揺れた。
「一番弱い蛇草だわ」
少女は裸の神子を逆さのままつるして自分の家に帰った。
少女は神子の首をねじりとると、髪の毛を引きちぎり頭だけにした。
首のない神子のからだはすてられ庭先に転がった。
「この蛇草、来年はどんな花が咲くのかな」
少女の母親が声をかけた。
「神子、新しい浦島草見つけたの」
「うん、コイナスビっていうの」
「可笑しな名前なのね、来年は楽しみね、ケーキと紅茶の用意できましたよ」
「はーい」
少女は植木鉢に水をやると家にあがって、キッチンに走っていった。
恋茄子(こいなすび)
私家版幻視小説集「お化け草、2018、一粒書房」所収
木版画:著者


