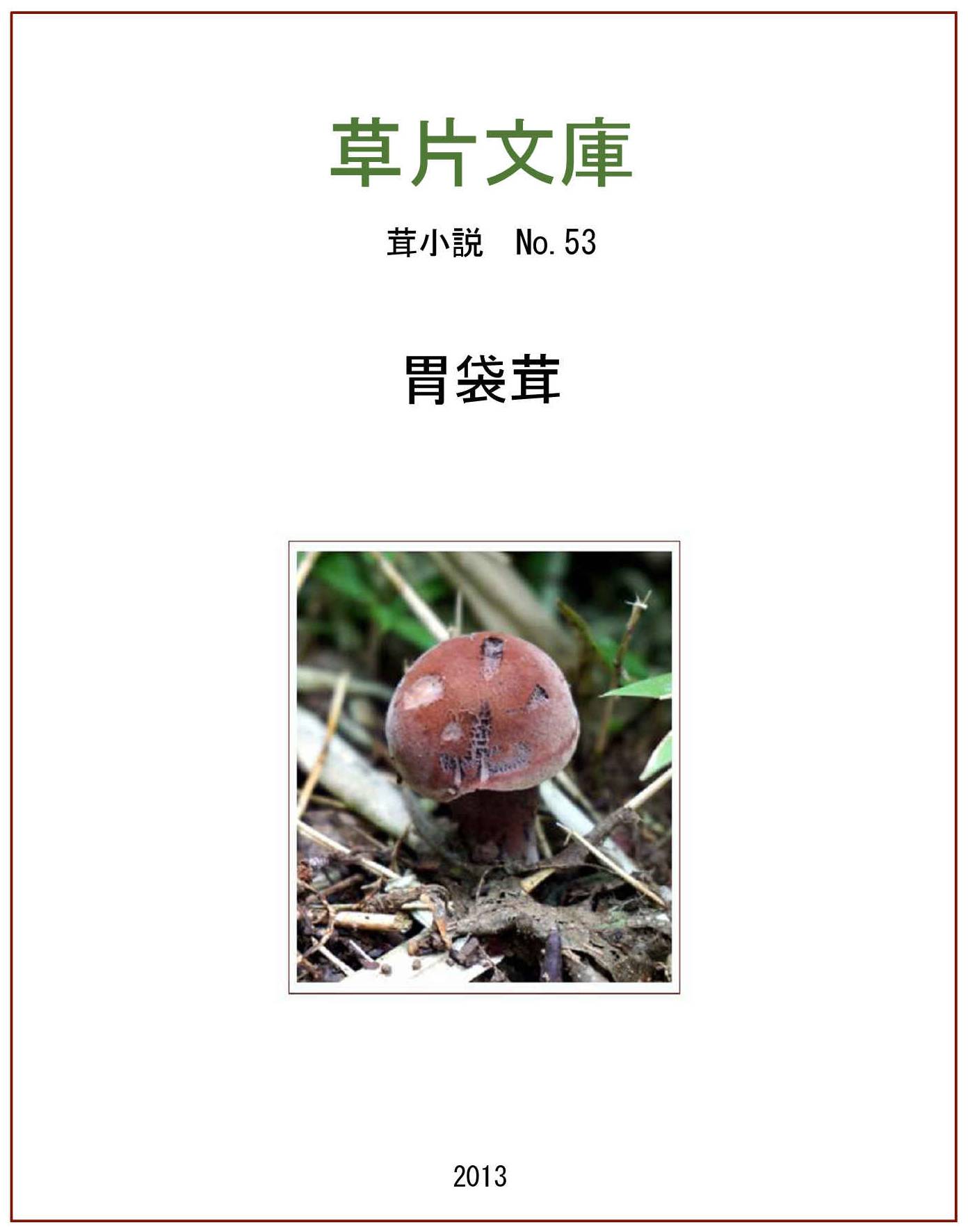
胃袋茸
秋田の山奥の地野居(ちのこ)村にある県営病院に赴任して一月が経つ。僻地ともいえるところの病院にしては設備が整っており、MRI、CTはあるし、各種の検査機器などは、都内の国立病院に匹敵するほどそろっている。
村人は全部で八百人たらずにもかかわらず、ベッド数は百近くあることから、患者は他の町の人のほうが多い。
専属の医師も十名おり、非常勤が十名とこれも格段に多い。そのようなこともあり、山一つ離れた町の鉄道駅からバスが走っており、病院ができたことはこの村にとって大変な活気をもたらしたのである。病院に隣接してこの村唯一のコンビニもある。
「おはようございます」
診察室にはいると、いつものように看護師の阿部絹美が明るい声で挨拶をしてきた。
「おはよう、今日もいい天気だね」
真夏の空気は寒い地方であろうとやはり暑い。ただ湿度があまりなく、東京のような蒸し暑さは感じられない。
「先生、今日はずいぶん患者さんが多いようです、ここのところ胃の具合が悪い人が多くて、こんなに良い天気が続くのにおかしいですね」
「ほお、いつもは少ないのかね」
「ええ、この村の人は内臓が丈夫で、特に胃の病気を持つ人は老人でも少ないんですけど」
「君はこの村の生まれかい」
「いいえ、山形よりの湯沢というところです」
「ああ、あの美人の多いところ」
「あら、昔はしらないけど、今はそんなことはありませんよ、若い人たちがみんなきれいになって、美人は東京の方が多いと思います」
「そんなことは無いさ、メーキャップで東京の女性はみんなお人形さんみたいだよ、まあ、どうでもいいんだけどね、それで今日、私は外科かね内科かね」
「今日は両方お願いします」
私は自分を外科系の医者だと思っているが、消化器、泌尿器、産科と何でもこなすことになっている。救急医を前任病院でやっていたせいもある。
初診担当の先生は長年の経験を持つかなり年をとった先生である。私など比較的若手は新しい技術を得意とすることもあり、それなりの専門医として患者を診ている。そういうことで、胃カメラや喉頭カメラ検査などの予約患者が多い。
今日来院予定の患者のカルテが机の上に積んである。いつもは他の先生から回された患者なのだが、今日は初診の患者が多いといわれた。
午前中に診る患者の数は二十四、五人のようだ。
最初の人から簡単に目を通していくと、血圧、心臓などが半数、腎臓系が残りの中の半数、それ以外はリウマチや関節炎である。自分のところには阿部君のいう胃の悪い人ははいっていなかった。
九時が診察開始時間である。最初に入ってきたのは赤ら顔の男性で、まさに血圧が高そうである。案の定、身体がふらつくということで測ってみると、血圧は二百近い。これでは身体が大変である。今まで降圧剤を服用していたらしいが、もう少し強い薬を出した方がよいであろう。
「お酒が過ぎているんじゃないのかな」
私がそういうと、その患者は首を横に振った。
「先生、ここのところ、胃がもたれて食欲が落ちているし、あまり酒が飲めないんだ、あんなにたくさん飲んでいたのがだめになっちまった、どうしてでしょうなあ。胃を悪くしたことなど今まで一度もないんだが」
「それじゃ血圧が上がったのはなにか他のことが原因なのかな、いつもと違うことをしたんですかね」
「なんもしとらんですな」
「ちょっと、そこに横になってください、お腹をみましょう」
腹が少し膨張気味である。表面に触れてみると少し堅い。胃、小腸、大腸、を少し強く押してみる。胃にしこりがある。レントゲンを撮るか胃カメラのほうが正確な判断を下せる。
「胃カメラを撮りましょうかね、明日、朝九時にこれますか」
胃カメラの操作だけは自信がある。患者は肯いた。
「それでは明日原因がはっきりしてから、薬を出します」
次の老女は曲がった親指を私の前に突き出して、痛くてたまらないと訴えた。リウマチである。これは膠原病の一種で自己免疫疾患でもある。まだ原因が特定されていない。外に悪いところもなさそうで、いつもの薬に痛み止めを加えた。
三番目は郵便局員で、風邪を引いて休んできたという。喉をみると赤く腫れている。だが、待っている間に測ってもらった結果では熱はない。外を回る仕事でもあり、暑さに疲れた面もあるのであろう。喉に消毒薬をぬり、風邪の一般的な注意を与え、薬を出すことを言った。
郵便局員は立ち上がりかけて、「胃の具合も悪いんです」と言った。
風邪を引くと自律機能全体が低下するし、ウイルスが胃の働きを直接弱めることもある。
「すわってください、下痢をしていますか」
「いえ、下痢はしていないけど、胸のつかえが強くて」
腹部の検診をした。最初の人のように胃が膨張してしこりがあった。念のために胃カメラをのんでもらった方がよいだろう。明日の九時半にきてもらうことにした。
阿部君が言ったように、胃が気になる患者が多い。なぜだろう。
次は小学生であった。カルテをみると小学校三年生、喘息が小さい頃からある。気丈にも親がついてこない。
「偉いね、一人で病院にきたの、発作が起きたの」
「いつも一人で来ます、喘息は大丈夫だったけど、お腹がきついのできました」
「痛いの」
「痛くはないけど」
ズボンをとってもらってお腹をみた。胃の部分がぽこっと膨らんでいる。手で触るとかたい。
「なにを食べたの」
「いつものごはん」
「どんなおかずだったの」
「ハンバーグと、キノコの炒めたもの」
「おいしかった」
「うん」
特におかしなものを食べた様子はない。
「うんちはでたの」
「うん」
「おならはでるの」
「でない」
「確かに、お腹が堅いね、薬をあげるからお母さんに渡してね、薬を飲んで、お腹のものをみんな出してしまおう」
「うん」
「それでも直らなかったら、明日、お母さんと一緒にきなさいね、薬をもらって帰ってね」
「はい、ありがとうございます」
少年は丁寧にお辞儀をしてでていった。阿部看護師に胃レントゲンの予約をさせるように指示した。
女性が入ってきた。
カルテをめくると産婦人科のものである。阿部看護師に聞いた。
「ご本人が内科でみてもらいたいというものですから、いつもは産婦人科で月経痛の薬をもらいにきています」
ということだった。女性がそれを聞いてうなずいている。
「それで今日はどうなさいました」
女性はお腹をさすりながら、訴えた。
「お腹が苦しくて」
「張っているのですか」
うなずく彼女に診察台に寝るように言った。
「お腹を触診します」、手だけ服の中にいれ腹を押した。
「確かに張っています、しかも胃にしこりがある、何かいつもと違ったものを食べましたか」
「いいえ」
「胃カメラを明日しませんか」
「はい」ということで、女性には消化剤をだした。
その後の三人の患者は慢性の肝臓疾患と鼠径部リンパ節の腫れ、それに喉の腫れであった。次にきた患者は青い顔をした老人であった。もう九十五にもなるのに一人暮らしのようだ。老人は歯の抜けた口を曲げ意外とはっきりした口調で言った。
「たたられた、儂はもうだめだ」
「どこがおかしいのですか」
「腹じゃ、たたられている」
こういう患者には細かく聞いても同じようなことしか言わないのが常である。まず血圧を測るといって手を取ると、おとなしく自分でシャツをまくって細い腕を私の前に置いた。
カフを巻いて聴診器を腕に当て、空気を入れると血流の音を聞いてみた。上が129で下が70である。問題は全くない。
老人がしわの寄った顔を前に突き出して黄色い目で私を見た。
「わしゃ、もう長くない」
「血圧が正常です、なかなか死ねませんよ、あと少なくとも二十年は生きる」
私は笑いながらそう言った。
「いや、だめだ、ほら」
老人はシャツをズボンから出すと腹を出した。胃のところがぽっかりと膨らんでいる。いままでの患者と同じ症状だ。胃腸の伝染病がはやりはじめたのだろうか。
「死神が腹に巣をつくりおった」
「ちょっと触らせてもらいます」
ずいぶんかたくてごろごろしている。
「朝ご飯食べ過ぎたりしませんか」
「いや、いつもとおなじじゃ、飯はたくさん食わん」
「この硬さは気になります、しらべたほうがいい」
「ごっつい死神が腹でふんばっとる、もうだめじゃ」
「死神のくすりなんてないですよ、なぜここにきたんですか」
「そうじゃった、すまんことで、もう少し胃をすっきりしたい」
「わかりました、胃のすっとする薬を出しておきます、ただ、胃カメラで調べましょう、あしたかならずきてくれませんか」
私は少しきつめに言った。
「ほんとうに死神を追い出してくれますかな」
「いいですよ、明日きてくだされば胃の中になにがあるか見ることができます」
「そりゃ面白れえ、死神の顔を見ることができる」
「それでは受付で予約を入れておいてください」
老人はうなずいて診察室をでていった。こういう老人はよくいるものだ。
二人に一人はお腹の調子がおかしい。最後の一人を診察し終えると、阿部看護師が言った。
「実は私もお腹が張っておかしいんです」
「君のカルテはあるの」
「はい、婦人科の方にありますからもってきます」
「お通じあるの」
「あります」
「薬欲しいくらいかね」
「それほどでもありません」
「それじゃ、カルテいいよ、明日胃カメラでみてあげよう」
「はい」
「すると、明日の胃カメラは何人になったのかな」
「十五人です」
「午後を考えるとその倍ということになるな」
「そうですね、でも先生、明日非番じゃないですか」
「そうだけど、やることもないし、胃カメラだけならそんなに大変じゃないから」
「えらいことです、先生は胃カメラがとてもお上手だと聞いています」
「それぐらいしか得意なものはないんだよ」
私は笑って手を洗うと、白衣をぬいで食堂に降りた。いつもの先生方がもうテーブルを囲んでいる。カレーの食券を買うとカウンターでだした。定食も悪くないが、時としてカレーだとかシチュウを食べたくなる。
白い米にたっぷりとかけられたカレー、なかなかいい匂いである。トッピングが面白い、今日はキノコが数種類、もこっとカレーに埋もれている。ご飯の上がごつごつとしている。なんだか今日の患者のお腹のようだ。地元で採れた奴だろう。カレーの中身が唐揚げだったり、白身の魚だったりすることがある。カレーの味は昔懐かしい味で、東京のしゃれすぎた味よりも私にはあう。
カレーをのせた盆を持って先生方のテーブルについた。
「おそかったね、患者さん多かったの」
部長が声をかけてきた。眼科の先生である。
「ええ、胃の張った人が多かったですね、ちょっとおかしな張り方をしていました。ごつごつする感じで、何かができているようです、伝染じゃなければいいけど」
「そういえばうちの患者でも、胃の調子がどうもというのがいたな、内科にかかりなさいと言っておいたけどね」
整形外科の先生がそういうと、産婦人科の先生も、
「妊婦の中にお腹の調子が悪い人がかなりいましたよ」と言った。
「何か悪い菌でもこのあたりにはびこってできものがでたのかな」
「明日、何人かに胃カメラをのんでもらうことにしましたので、それでわかるでしょう」
「そりゃありがたい、でも先生非番でしょう」
「そうですが、かまいませんよ」
「助かるな、明日、そういう患者がきたらまわしていいかな」
「いいですよ」
「申し訳ない、でも胃カメラをうまく操れるのは先生くらいしかいないからな」
明日は一日中、胃カメラとお付き合いだ。
食事が終わって、みんなと休憩室に行こうとしたときである。
院長がわざわざ食堂にまできて私にちょっとと声をかけた。
私は周りの人に先に行ってもらって、院長先生のところにいった。
「先生、警察からなんだが、外傷のある死体が山の中で見つかったそうだ」
「え」、事件のようだが、自分に関係があるのだろうか。
「このあたりでは今まで生々しい事件などなかったのだけどね」
この村では家を開けっ放しで買い物にいくなど当たり前である。この地に赴任した時にまず驚いたことである。院長は続けた。
「どうも外で殺されてこの村で捨てられたらしい、近くに検死できるような場所がないので、この病院で検死してくれないかということです。先生は東京で救急医であったし、検死の経験もおありだと聞いていたので、立ち会ってくれないかということです。午後の診察は外のものに割り振りますのでお願いしますよ」
検死官は警察に所属する医師などの職種であり、私に資格はないが、解剖して死因を確かめることならば医師の私にもできるし、そういう現場には何度か行っている。
「はい、わかりました」
「二時頃に救急車で運ばれますので、地下の霊安室の隣の部屋を用意しておきます、手伝いに看護師を一人つけるからよろしく」
院長はそういうと離れていった。
「なにかあったのか」
同僚が興味深げに聞いてきた。
「うん、検死をやれということらしい」
「事件らしいな、この村ではないことだね」
「そうらしいね」
この同僚は関西の大都市から赴任してきた外科医である。
遺体は解剖用の台で白い布を被されていた。
一度会ったことのある村の駐在さんの一人がしゃちこばって、
「先生、よろしくお願いします、こちら県警の警部さん」と私に紹介してくれたのは色の黒いごつい顔のいかにも警部といった感じのひとである。警部のとなりに、色の白いひょろんとした若い人がいた。
「先生、記録はこちらの刑事にやらせますから、先生はみたてを言ってください」
そこに看護師の阿部が緊張の面もちでやってきた。何をするのかわからなかったのであろういつもの白衣のままである。
「阿部君、解剖用の白衣を手術の準備室から借りて着てらっしゃい、ゴム手もつけてくるんだよ」
「私なにをするのでしょうか」
「僕の解剖の手伝いをしてもらうだけだから大丈夫だよ、早く着代えてきてください、すぐ始めるから」
彼女はあわてて出ていった。
「急なことですみませんね」
警部が彼女の後ろ姿に向かって言った。
「とりあえず、外見からお願いします。そのままですので、着てるものから記録していかなければなりません」
若い刑事は意外となれた様子でかぶしてある布をとった。
女性だった、まだ二十歳ほどであろう、顔の左側に土が付いているだけではなく擦り傷があるのは乱暴に捨てられたためだ。
花模様のブラウスに少し短めの緑色のタイトスカート、このあたりの町ではあたり前の通勤スタイルである。靴はなかったようだ。肌色のありふれたストッキング。
刑事はそんなことを言いながら丹念に記録を取っていく。
左側の顔の擦り傷について、死んだ後にできたものだと言及しておいた。刑事も気がついたようで黙ってうなずいた。
動かすことなく首から頭にかけてねじれ具合をみた。
「首を絞められ、ひねられていますね」
「はい」刑事はそれもわかっていたようだ。思ったより経験豊富のようだ。
「顔の様子からすると、瞬時の犯行のようだ、相当腕の力のある犯人ですね」
刑事は頷きながら私の言ったことを細かく書いていく。
「さて、動かしてみますがいいですか」
「はい」刑事はビニール袋を何枚も用意している。
なかなか細やかな刑事である。脱がしたブラウスを袋に入れ状態を書き込んだ紙を一緒にする。そんな作業を繰り返し、女性の裸体が露わになった。かなり美容に金をかけている。陵辱された跡もなく、身体自体に損傷はなかったが、胃が異様に盛り上がり、ごつごつした感じである。
そのことを刑事に言うと、
「食べてすぐに殺害されたわけでしょうか。死亡時刻がはっきりしますね」
そう切り返してきた。その通りである。この被害者はみた感じでも朝食後あたりに殺害された可能性が高い。
「そうですね、解剖してみましょうか」
やっと阿部が支度を整えてもどってきた。
「遅くなりすみません」、すると裸にされた被害者を見てぎょっと立ち止まった。
「いや、ちょうどいい、これから解剖するから手伝ってほしい、必要があったら、臓器を切り出すが、その必要はほとんどないと思う」
そう言って私はまず口の中などを詳細に調べ、その後、胸部を開いた。肺は当然のこと縮んでいるがこれといった所見はない。心臓も同じである。胸郭の内部にはなにも留意点はなかった。
腹部を開くと、外部からもわかったように胃だけ異様に膨らんでいた。十二指腸にしろ大腸にしろ特にかわりなく、食べてすぐの状態であることが見て取れた。
なにを食べたのか切り開く必要があるだろう。胃は取り出さずそのまま切開した。
そのときのぞき込んでいた刑事も阿部も、もちろん私も、「え」と、驚きの声を上げてしまった。警部もその声で覗き込んで驚いている。
ぱくっと開いた胃の中に真っ赤なものがごろごろと入っている。
「なんですこれは」
刑事が私に聞いたが見た通りで、首をかしげるほかなかった。
胃の中には真っ赤な茸が詰まっていたのである。無理に胃の中に茸を詰め込んだとすると、歯や口腔に残遺物がないのでその可能性はない。となると自分で飲み込んだとしか考えられない。そのことを言うと、刑事は聞き返してきた。
「朝食にこんなに大きな茸を飲み込むということがあるのでしょうか」
至極まっとうな質問である。
「茸に噛んだあとはありませんね、飲み込むのは苦しいでしょうね、全くできないわけではないでしょうけれども、無理といっていい」
「おかしなことですね、なぜ殺す前に茸を飲ませたのでしょうね」
「いや、自分で飲み込んだとすると、この殺害事件と茸と必ずしも関係があるとは限りません、犯人を捜すヒントの一つにはなるでしょうけど」
「あ、そうか、先生のおっしゃるとおりだ」
「私は茸ことはわかりませんので、一部は凍らせて、一部はホルマリンに漬けておきます、専門家に見てもらってください」
「はい、手配はします」
「阿部君、すまんが、これを胃ごと保存したいので、大きな瓶を探してきてくれないか、おそらく手術室にある、それに茸を凍らせておくのでタッパーのようなもの」
阿部はほっとしたように飛び出していった。
「刑事さん、写真を撮っておいてください。その後、胃ごと切り取って、中からこいつを取り出します」
「はい」、刑事は先ほどからすべて自分でやっている。首にかけたカメラで内臓ばかりではなく作業すべてを記録に撮っている。万能刑事だ。
「お願いします」と、刑事が合図をしたので、私は食道の下端部と胃を切り離し、十二指腸と胃の間を切って、トレーの上に載せた。切り開いたところから、ピンセットを使って茸を取り出したところ、根本でつながっている三つの茸がでてきた。刑事はまたびっくりした。
写真をお願いします。刑事はあわててシャッターを押した。
「こういう状態のものだと飲み込めませんね」
「胃の中にはどのようにして入ったのですかね」
「一つの可能性は、胃の中で育ったということです」
「あ、そうですね」
刑事は納得したような顔でうなずいているが、そんなことがあるはずはない。
次から次へと茸が固まって出てきた。数えてみると八十いくつかになる。
「茸は凍らせて置きます、あとアルコールにもつけて保存しておきます。残りは胃に戻してそのままホルマリンにつけます」
「はい、そうしてください」
阿部が台車にいくつかの瓶をのせてもどってきた。
「ありがとう」
私は茸の入った胃をいれた。あとでホルマリンをいれる。数本の茸をタッパーと小さな瓶に入れた。ビンにはあとでアルコールをいれる。
「警部さん、この村は茸がとれるので、茸に詳しい人がたくさんいます。どうでしょう、その人たちにこの茸を見せてみたらいいと思いますが」
「そうですね、われわれは、すぐに戻らなければなりませんので、あとで保存された茸や臓器をとりに来させます。茸はすでに数えてありますので、戻していただければ、お使いになってかまいません。駐在にも言っておきますので」
遺体はとりあえず警察の専用車がくるまで安置所であずかり、茸の名前や取れるところなどは駐在さんと一緒に調べてみることにした。
このようにして、奇妙な遺体の検死は終わった。
その夜、村の集会所に茸に詳しい人が集められた。そういった点は駐在さんの顔はたいしたものである。私はアルコール漬けにした茸をもって集会所に出向いた。
駐在さんがみなに病院の医者であることを紹介してくれた。そこで、事情があって出所は言えないが、茸を鑑定してほしいことを伝えた。駐在さんは私の手から茸の入った瓶を受け取とって輪になって座っている老人たちの中においた。
黒みがかった赤い茸を見てみんな首を傾げた。赤い茸はいろいろあるが、これは見たことがない。と声をそろえて言った。
「卵茸は白い壷が根本にあるし、もっと茎が細い、紅天狗茸は壷がないがやはり柄が細い。茎まで真っ赤な茸は外にもあるが、この茸のように松茸のようなずんどうではない」
集まった中に、中学校の先生で植物学をやったという人が「このあたりは茸の宝庫だから、新種などまだまだたくさん見つかるでしょう、ひょっとすると、これも新種じゃないですか」と言うと、
「そうだなあ、こんなんは儂は見たことがねえ」と茸採りの名人が言った。
「厳空(がんくう)じいさんは知ってるかもしれん」
別の老人が言うと、その中学校の先生が、「私が呼んできましょう、車で来ているから」と立ち上がった。
「厳空じいさんて誰です」
「昔茸卵(じらん)神社の宮司をやっていた男で、もう九十五に近い一人暮らしの老人です。秋になると、茸取りが始まる前にその神社で茸開きをおこなって、それから山にはいるのです」と駐在さんが標準語で話してくれた。
「それじゃ、みなさん、病院からビールとつまみが届いています。厳空さんがくるまで、いっぱいやってください。」
集まった人たちがこっちを見てお辞儀をした。院長の配慮である。病院はそれが村の人たちとの繋がりになることをよく知っている。何かの時には協力してもらう必要があるからである。
私も輪に入った。ビールをつがれた。
「この村にはよう、茸のいろいろな話が残っているがよ、中にゃ、おっそろしい話もあるだよ」
頭に鉢巻をした髭だらけの老人が欠けた歯をのぞかせて私しに話しかけてきた。
すると周りの人も話をやめて老人の話を聞きはじめた。
「あの、茸卵神社はよう、最初に建てられたのは数百年前だったらしいがよ、そのときは茜神社といわれたんだ、大きくはないがとてもきれいな神社だったそうだよ。
ある時な、村の庄屋の息子がよ、隣町の侍の娘っ子に惚れちまってよ、孕ましちまったんだ。どっちもよ、純情だったということらしい。
侍の親はよ、特に男親はよ、世間体が悪いと、位が上の侍だったで、庄屋の息子を捕らえちまった。それに、何とか許してくれとやってきた庄屋の両親を切り殺しちまった。
それだけじゃない、庄屋の息子と自分の娘をたたき切るといきまいた。やはり、母親は何とか自分の娘は助けたいと、離縁して娘を引き取るからとたのんだそうだ。ところがその侍はよ、捕らえておいた庄屋の息子に毒の茸を皿に盛り上げ、それを食ったら娘の命は助けてやると、二人が逢瀬を重ねた茜神社に連れて来たそうだ。酷いことをしたものさね、庄屋の息子は本当に惚れていたのだね、娘の命が助かるならと、茜神社の中で毒の茸を食ったそうだ。そしてな、悶え苦しんで、血だらけの茸を吐いて死んだそうだ。それでその娘は母親の実家に母親とともに戻ることができた。茜神社はそれいらい茸乱神社と言われたそうだ。それが、いつかは知らんが茸卵神社となったそうだ。茸狩が始まるときには必ずお参りするようになったのだよ、毒にあたらないようにな」
その老人の話が終わってふと見ると、中学校の先生がやせ細った老人を従えて、私の後ろに座っていた。
「先生、巌空さんです」
やっぱり病院に来た老人だ。お辞儀をすると「こりゃ、朝にゃ世話になりました」老人も頭を下げた。午前中に診察に来てたたりだと騒いだ老人である。
老人は皆の前に置いてある茸をゆびさした。
「こいつは話にあった猛毒茸だ、この茸は普通のところにゃはえんでよ、どうしたんじゃ、悶えもたしという名前で呼ばれていたこともあるが、わしゃ本当の名前は知らん」
出所を言うことはできない。
「どんな毒でしょう」
私が聞くと、「名前の通りじゃで、悶え苦しんで血を吐いて死ぬ」とだけ答えた。
「やはり、たたりじゃなあ、なにがおこるか心配じゃが」
厳空老人はそれから黙りこくってしまった。
しばらく話が続いたが、それ以上の情報は得られなかった。東京の茸の専門家に見てもらわなければ本当の名前はわからないだろう。
明くる朝、非番でもあり、ゆっくりと起きて朝食の用意をした。久しぶりに目玉焼きをつくり、トーストを食べながら新聞を開くと、昨日の殺人事件のことが地方版にかなり大きくのっていた。しかも犯人はすでに捕まっていた。別れ話がこじれて、首を絞めて殺し、車で村に運んで捨てたということである。犯人と被害者とも隣町の住人であった。ということは胃に詰まっていた茸は事件とは全く関係のないことのようである。かえって薄気味の悪い展開になってきた。
胃カメラの予約は九時からにしてある。病院に行くと院長に呼び止められた。
「昨日はご苦労様でした。助かったと警察から連絡がありました。茸の件は別物なので警察としては追求する予定はないとのことでした。検死の場を提供しただけだから、病院としても関係しないことになります。」
院長は外出の格好をしている。
「今日は非番なのに胃カメラをやってくれるということでどうもありがとうございます、僕は県のあつまりにでます」そう言って出かけていった。
支度をして室にはいると、阿部看護師が用意をして待っていたので声をかけた。
「昨日はご苦労さま、初めてで大変だったろう」
「ええ、でも、もう犯人もつかまってよかったですね、あの茸はなんだったんでしょうか」
「さっき院長から言われたよ、警察も茸のことにはかかわらないようだよ、我々も忘れたほうがいいような雰囲気だった」
「そうですか、でも気味が悪い」
「そうだね、個人的にははっきりさせた方がよいような気がするけどね」
「患者さん来ているのかな」
「ええ、もう何人か待っています」
「早いけど、始めようか」
阿部看護師が最初の人を呼びに行った。
入ってきたのは昨日診た少年と母親だった。
「どう、お腹の具合は」
少年ではなく、母親の方が答えた。
「薬はきちんと飲ませたのですが、まだお腹が張っていると言いまして」
少し膨らんでいるお腹を押した。確かにまだ堅い。
「お腹は痛いことなかったかい」
少年は首を横に振った。
「ガスが溜まっているわけでもなさそうだし」
理由はよくわからない。
「レントゲンを撮ってからまた来てください、そんなに時間はかからないから」
少年と母親は阿部看護士から指示書を持ってレントゲン室に行った。
次に入ってきたのは赤ら顔の年輩の男であった。昨日、最初に診た患者である。
「どうですか、調子は」
「変わんねえです」
それじゃ。用意してください。着衣のままでもいいが、ある程度リラックスしてもらうため、シャツの上から白衣のようなものを着てもらい、台に横になってもらった。
「鼻は詰まっていませんね」
「へえ、大丈夫です」
細い管状のものを喉から入れるのであるが、げえっとなってしまう人が多いので、私は鼻から入れることが多い。いつも軽い局所麻酔を使う。
食道は綺麗である。カメラが食道の噴門部を通り胃にはいると、画面が真っ赤になった。一瞬出血かと思ったが、よく見ると死体の茸と同じもがはいっている。
阿部看護士がモニターの画面を食い入るように見て、自分のほうに顔を向けた。彼女も気がついたようだ。軽くうなずくと彼女は録画のボタンを押した。
自分で映像を見ようとする患者も多いが、この男はあまり見たくないようで横を向いている。ありがたい。
操作をしても胃カメラが胃の中の方に進んでいかない。私はすぐに引き上げた。
「胃そのものは問題なさそうです」
私は平静を装って患者にそうつげた。そう言うしかない。
「ただ、少し胃が張っていますね、下剤と胃がすーっとなる薬をだしておきますが、明日もう一度来てください。もし、調子悪くなるようなことがありましたら、すぐに病院に連絡して下さい」
男はすこしは安心したようだ。礼を言って検査室から出ていった。何が起こっているのだろう
次は妊婦さんである。モニターが見えないよう位置で、胃カメラを操作した。女性も同様で、胃の中には真っ赤な茸が詰まっていた。阿部看護師もどうしましょうという顔で私を見た。
「赤ちゃんは順調そうですね、胃にまだ不消化なものがたまっています、しばらく薬を飲み続けてください、様子がおかしくなったらすぐきてください」
そう言って返した。
少年がレントゲン室からもどってきた。母親は心配顔である。私はレントゲン室からとどいている映像を見た。少年の胃にいくつもの固まったものが見られた。明らかに茸である。映像に色こそついていないが、赤い茸に違いがない。
「少し胃が荒れているね、それで張っているんだろう、すっきりする薬をだしておくから、あまり気にしないで普通に学校に行って、普通に食べてかまわないよ、だけど、もし何か変わったことがあったらすぐに電話してください」
少年と母親にはそう伝えた。
すべての患者の胃には真っ赤な茸が詰まっていた。まず院長に報告して、胃から茸を取り除く方法を考えなければならない、そもそも胃に茸が生えるなどということがあることが不思議である。どうしたものか。それにもう一つ気がかりなことがあった。
「阿部君、あのおじいさんこなかったね」
「厳空さんですね、来ませんでしたね」
阿部君には昨日の茸の専門家の集まりのことは言っていない。
「先生なにが起こっているのでしょう怖いです、私も胃の具合が悪いんです、先生見てください」
阿部絹美は真剣な顔で言った。昨日そういっていた。
「そうだった、用意して」
私は阿倍の鼻から胃カメラを入れた。本人にはモニターがよく見えるようにした。
カメラの先端が食道、噴門を通りこすと、ピンク色の綺麗な襞が目に入った。
「ほら、茸はない、大丈夫だよ」
阿部はうなずいて喜んだ。
「ありがとうございます」涙ぐんでもいる。
もしやと思って聞いてみた。
「君、子供じゃない」
彼女ははっとして、「調べてもらいます」
と出ていった。
院長に相談する必要がある。院長が帰ったら話そう。そこで思い出したのが茸卵神社のいわれの話である。宮司の厳空さんの胃にもあの茸があるのだろう。本人はそれを知っていて病院に来た。彼に聞くのがいい。駐在の高橋弘巡査に電話をいれた。
「巌空さんと茸のことで話をしたいのですが、一緒に言っていただけませんか」
「先生、私も行かなきゃいかんと思っていました、あの茸は厳空さんにはわかるとおもいますよ、今すぐでもいいですか、車で病院にいきます」
「大丈夫です、お願いします」
駐在さんも気にしていたようだ。それから十分もたたないうちに駐在さんの運転するパトカーが病院の駐車場に到着した。
「先生、やっぱり何かあったかね」
私がパトカーの助手席に乗ると聞いてきた。
「ええ、今日診たたくさんの患者さんの胃の中にあの茸がはいっていたんです」
「ええ、村の人の胃の中にあの茸が入っていたんですか、大変だ」
「厳空さんが昨日病院にきたんですよ、おなかが調子悪いって、それで今日胃カメラをする予定だったがこなかった、きっといの中には茸がある」
「そりゃあ、大変だ」
高橋巡査は茸卵神社にパトカーをとばした。
神社の隣の厳空じいさんの自宅に着くと、巡査はよく知っている様子で戸を開けた。
部屋の中を見ると、じいさんは酒瓶をわきにおいて飲んでいた。
「じいさん、お医者さん連れてきたでよ」
「巌空さん胃カメラ検査に来ませんでしたね」
じいさんは私を見ると少し驚いた様子だったが、
「すんません、胃のすっとなる薬、少しはきいたですよ」
頭を下げて、座っている後ろの茶ダンスから茶碗を二つ取り出し酒をついだ。
「あがってくだせえ」
私たちは部屋にあがり、彼の前に座った。
「おらは車だで飲めねえ」
高橋さんは地元の言葉になった。
私は一口飲んだ。辛口のいい酒である。
「これはおいしい、飲んだことのない味だ」
「先生は酒がわかりますな」
巌空老人が笑顔になった。
「それは、秋田の酒に毒消し茸を浸したもので、みな旨い言いよりますな」
「先生が聞きたいことがあるいうでお連れしたんだ」
「言わずともわかるだ」
老人はまた酒を飲んだ。
「胃袋茸のことじゃろう」
「胃袋茸ってなんでしょう」
「先生が、このあいだみんなに見せた茸だ」
「どこで採れるのです」
「ふふん、血の中じゃよ」
「地の中ですか」
「ちがう、俺たちの赤い血の中に生えるんじゃ」
冗談としか聞くことができない。何かのたとえか。
「先生に胃カメラで見てもらった連中の胃の中にゃ真っ赤な茸があったろうに」
私はうなずいた。
「わしの胃の中にも詰まっておるわ」
「胃に生える茸なんて信じられないんですよ」
「怒り茸じゃよ、話してやろうかのう、この村の伝説じゃよ、昨日も誰かが話しましたじゃろう、だがな話がちがうのよ」
駐在さんも身を乗り出した。
「聞かせてくれや、庄屋の娘の話じゃないのか」
「この村に伝わっている話は本当じゃねえ、庄屋の息子が侍の娘に惚れたんじゃねえ、庄屋の娘が侍の息子に襲われ、はらまされたんだ、娘はその侍に子供をおろすように毒キノコを食べさせられて死んだ、というのが本当なんだ。しかも庄屋の両親兄弟とも賊が入って皆殺しよ。それからこの村はさびれていったんだ。
侍の息子は母親の里に隠れて大きくなり儂の先祖となったんだ。儂は宮司になってから神社の本尊のある部屋の隠し戸から、その顛末が書かれた紙をみつけたんだ。そいつはあの庄屋が書いたものだと儂は思っとる。恨みの言葉が行間から浸み出していた。この神社はあの庄屋の肝いりで建てたのだから、庄屋は神社の中をよく知っていたのだろう。自分の身に何かが起こることを感じていて書いたものをここに隠したのだろう。そのあと賊に殺された。
先生、先生は今の学問を修めた医者だ、遺伝子のことは知っておいでじゃろ、化学物質だと科学は教えておるでしょうに、じゃがな違うんだ。遺伝子そのものが生き物でな、生き物は個体と個体の関係があるように、遺伝子にも遺伝子との関係があり、遺伝子の怨念は別の人間の遺伝子に乗り移る、侍の息子の遺伝子に庄屋の怨念が潜んだんだ。だからわしの遺伝子の中にもおった、今年は庄屋の娘が殺されて五百年、胃袋の遺伝子が暴れて茸を作り出したんじゃ、信じられんじゃろ」
私はうなずいた。
「信じなくてもよいわ、じゃが、患者の胃の中に、真っ赤な茸がごろごろしていたのは見たじゃろ、本当に茸があったじゃろ、あんなところに生えることが説明できるかね、できないじゃろ」
これもうなずくしかなかった。
「だけど、厳空さん以外の人の胃になぜ茸ができたのでしょう」
「ほれ、いったじゃろDNAの中に怨念がある。そいつ等もどこかで儂と同じ血がながれているんじゃ」
「患者たちの胃の茸をだしてやらないと」
「だいじょうぶ、明日になれば茸は消える、五百年後にわしに復讐すれば、すべて消えるのじゃ」
厳空じいさんは自分のコップに酒をついで一気に飲んだ。
「本当にうめえ酒だ、先生もつきあってくれや、よう駐在、あんたも飲めや、パトカーおいて帰るか、代行に頼めや」
老人は私と駐在さんに酒をついだ。院長には明日相談しよう。
「ほいじゃ、呼ばれるか」
高橋巡査もコップを口に運んだ。この村にも代行があるのだろうか。
「パトカーは大丈夫ですか」
「大丈夫ですだ、家内に電話すれば、あいつの車で若いのを乗せて来てくれる、こういうことはよくあるんです」
「この村さ住んでみなせえ、すぐ酒で、飲むのをことわりゃ、相手の気が悪くなる」
「巌空じいさん、何の茸をいれたのかね、こんなに旨くなるなら、俺も漬けよう」
「便所茸だ、」じいさんはわれわれが来る前から飲んでいる。だいぶ酔っている。いつまで付き合わされるかわからない。
「私は明日の診察があるので、この辺で」
「そおかあ、先生ありがとよ、明日にゃみんな解決だ」
「今かかあ呼びますで、おくらせます」
駐在さんが電話をすると、奥さんが近くの若い人をつれて車で迎えに来てくれた。
次の日の朝早く駐在さんから私の携帯に電話があった。
「厳空じいさんが死んじまいました、今、じいさんのところに寄ったら、布団の中で息してなかった、救急車の手配をしたので、すぐにそちらに行くだ。よろしくお願いしますだ」
私はあわてて着替えをして病院に駆けつけた。まだ救急車は到着していなかった。
それからまもなくである。救急車がつくとあわただしく人の動く様子があり、私の診察室にキャリアーが運び込まれた。厳空じいさんだった。
エビのように丸まって息絶えていた。
救急隊員が報告した。
「現場ですでに心肺停止の状態でした」
駐在さんが入ってきた。
「先生、昨日あれからずいぶん飲みまして、じいさんが眠いというので、寝かしてから、家内に電話して来てもらったんだが、そんときゃ、全く異常がなかったと思いますがね、寝息立てとったから」
私はうなずいた。
死んだ老人の顔は苦しげではあったが満足の表情も見えていた。自分の死の時刻を知っていたのである。それは苦痛を伴ったとしてもある意味で幸せである。その苦痛を乗り越えれば死という、なにも感じない世界が待っている。厳空じいさんは何百年もの前の怨念に、DNAに組み込まれていた怨念に殺されたのである。科学の世界にいた私にとって、生涯忘れることのできない出来事になるのだろう。
「心臓梗塞でしょう」
私は一番近いと思われる死因を言った。
「先生、解剖しなくてよいのでしょうか」
高橋さんが聞いた。
爺さんの死体の胃を触ってみた。やわらかくへこんでいた。
「ええ、解剖しても同じでしょう、そのままでいいでしょう。死亡診断書は書いておきます」
私はその場を去った。
その後、あの日胃カメラをのんだ患者たちの胃から茸が消滅した。
厳空の死がDNAの中にあった怨念を消滅させたのである。患者たちは侍の血を引く者たちだったのだろうか。調べればわかることだろう。
殺された隣町の娘も血を引くものだったのかもしれない。この町に捨てられた時、まだ息があって、そのときに茸が胃に生えた可能性もある。町に渦巻いていた怨念である。
病院の資料室にまだ残されていた、殺された女性のホルマリン漬けの胃袋から、赤い茸は消えていた。茸だけの入れておいた瓶からも消えていた。
庄屋の怨念が作り出した胃袋茸は、侍直系の厳空老人を死に至らしめ、怨念をはらした。その死は呪いを解き放ったのである。
腹が立つ。昔の人は怒ることをそう言った。それはDNAに潜む怨念が胃袋茸を生み出すことに他ならなかった。現代の生命科学はそのメカニズムを解き明かすにはあまりにも未熟である。
胃袋茸
私家版第四茸小説集「茸人形、2018、234p、一粒書房」所収
茸写真:著者 東京都日野市南平 2016-6-26


