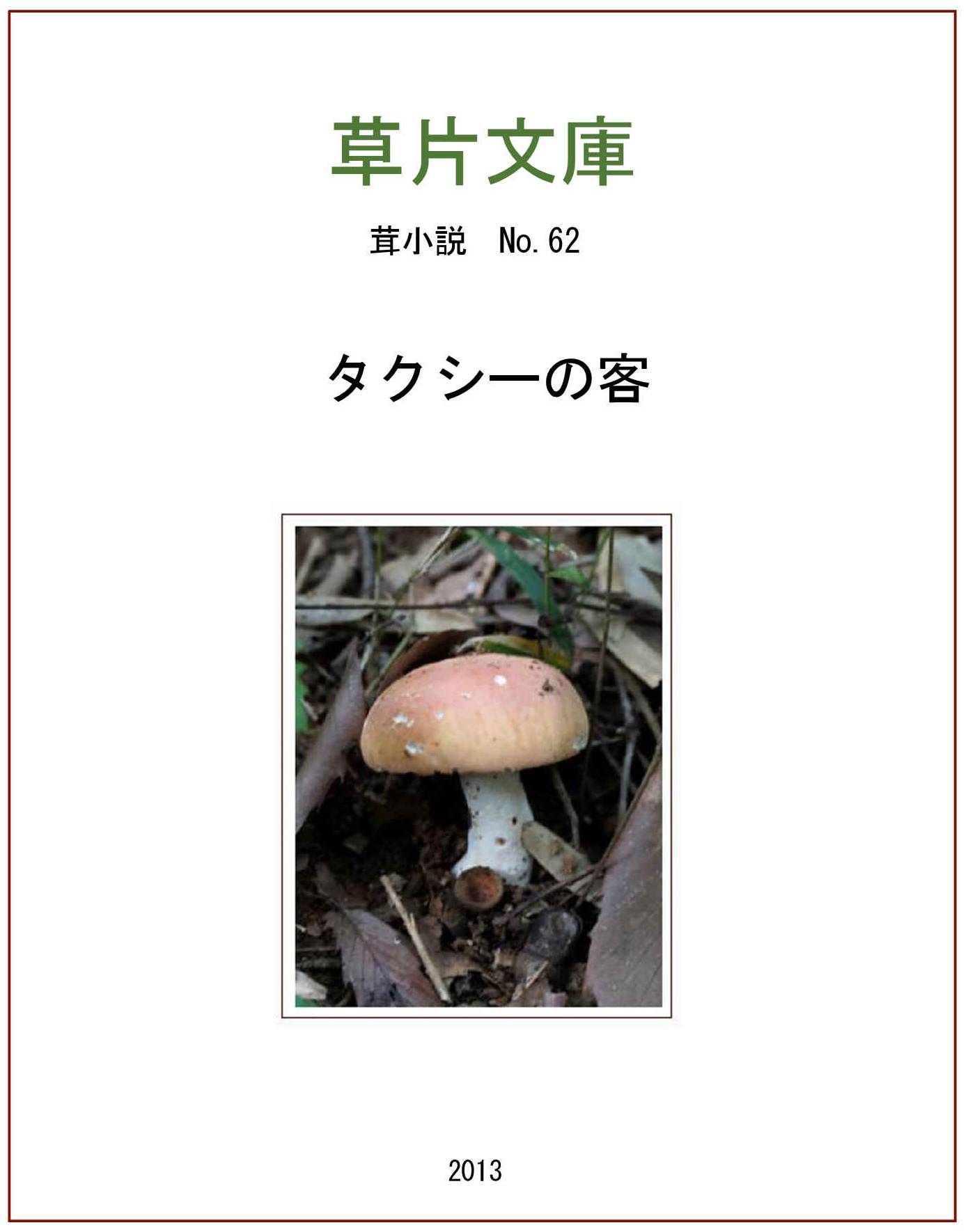
タクシーの客
おかしな噂が巷に広がっている。
それは東京ではおなじみの新宿のタクシー会社、Aタクシーで起こっていることである。
Aタクシーの運転手が口々に言うのは夜中に乗せた客がみんな茸をかじっているというのである。必ず三人で、三人とも茸を手に乗ってくるという。
私はA社にインタビューにいった。
一人のタクシー運転手がこのような話をしてくれた。
「あれは、赤坂見附のあたりで拾った客だったな、夜の一時ぐらいだったろうか、男が手を上げていたんで止まったんだ。男二人と女一人だった。三人で乗り込んできて新宿のマンションを指定されたな。そんなに遠くない。行き先を言うと彼らはリラックスした様子でクッションにもたれかかった。飲んでいるようではなかったね。女は美人と言うほどではないが、愛嬌のある、まあかわいい顔の色白の子だった。オフィスレディーといったピンク色のスーツを着ていた。男はおさだまりの紺のスーツに白いシャツ、一人は紺のネクタイ、一人はループタイをしていた。
車を出してほとんどすぐだったかな、何かどこかでかいだような匂いが車の中をただよってきた。なんだろうとバックミラーを見ると、三人とも手に茸を持ってかじっていたんだ。松茸の匂いだった。松茸の形に似せたお菓子でも食べているのだろうかと、興味はあったが、何もきかずに車を走らせた。
十分も走ったかな、またバックミラーを見ると、女の手から茸が足元に落ちるところだった。女は「あ、おとした」と足元を見て小さな声で言っていたよ。男たちはもう最後の一口をもぐもぐさせているところだった。
そこで車がマンションについた。彼らはそのまま料金を払って降りていったよ。
それで車を出してちょっと先で止めたんだ。車の中に落としたものを拾うためだよ。次の客に迷惑になるからね。拾ったら本物の松茸だった。しかも生の。けっこう大きかったから買うと数千円するものだよ、かじった跡があって口紅が付いていた。いい匂いだったが道に捨てちまった。しばらく窓を開けて走ったよ。それでも次に乗せたお客さんが、このタクシーは松茸の香りをつけているのかいと聞いたよ。その客には前に乗ったお客さんが松茸を持っていました。と言っておいたけどね、生でかじっていたのは奇妙だね」
次は別の運転手の経験である。
「あれは一月ほど前のことだったな、品川駅の近くで三人組の客を乗せたよ、全部男だったな、酒の匂いもしないし、こんな遅くまで仕事が大変なんだなと思ったね。三人ともネクタイをぴちっと締めて、紺の背広姿だったね、行き先は新宿だったよ。お互いに話もしないし疲れているんだと思ったね。しばらく走ると、紙袋をかさかささせる音がして、バックミラーを見たら、三人とも袋の中に手を入れて、赤いものを取り出すとかじりだしたんだ。周りに車もあまりいなかったから、ちらちら見ていたら赤い茸のかたちのものだった、ぽろぽろかけらをおとしながら食っていたよ」
「匂いはしましたか」
「特になかったね、お菓子かと思ったけど、客が降りてから客席の床をはいたら、生の茸のかけらがあったね」
「そのお客さんの様子はどうでした」
「三人ともうまそうに食っていたな、こっちが腹が減ってきてね」
「運賃はきちんと払ったのですね」
「ああ、一万円札出して、お釣りの小銭の部分はいらないって、気前がよかったね」
「調査に協力、ありがとうございました」
というような次第だった。
女性のタクシー運転手も遭遇したそうである。
「一週間前よ、夜だったわ、いつも夜勤はしないんだけど、その日は休む運転手が多くて、できたらでてくれと言う連絡があったの、それで子供たちに食事の用意をして、二時間ほど寝たかしらね、九時からでたのよ。高田馬場から早稲田の間を走らせていると、女の子が三人手を挙げて私を止めたわ。あのあたりは学生さんが遅くまで飲んで帰れなくなって車拾うのよ。特にけばけばしくもなく、ジーンズの子とワンピースの子、それにショートパンツの子だったわ、よくおしゃべりをしていて、乗り込んでからずっと話していたわ、だけどしばらくすると急に静かになったので、バックミラーで見ると、女の子たちが何か手に持って食べてたの。ああそれでおとなしくなったんだなって思ったの。でも奇妙よね、白い茸をかじっていたのよ。形は松茸のようだったけど、松茸の匂いはしないし、でも確かに茸だったと思うわ。
三人は食べ終わると、『おいしかった』とハンカチで口を拭いていたわ。お行儀はよかったわね」
「どこまで乗ったのです」
「新宿よ」
次はもう七十に手がとどくというベテラン運転手の話である。
「ありゃあ驚いたね、両国で夜中に乗せた客が俺のタクシーに乗ると、いきなり腹減ったと言って紙袋を取り出して、その中から茶色い茸を取り出すと、ムシャムシャ食い始めたんだよ。乗せたのは三人だったね、一人は若い関取で、大きいからだで乗れるか心配だったが、ほら俺の車は古いタイプで、大きいからよかったね、それにあとの二人は痩せた小柄な女の子だったよ、だから乗れたんだよ、うん、その女の子も関取からもらってかじっていたよ。きれいな顔をした女の子たちだったからよく覚えているよ、ファンなのかね、関取はもてるね」
「どこまで乗せたのです」
「新宿だったよ」
ここまでの調査で、共通点をまとめてみよう。まず客は三人、男女の組み合わせは同じではない。乗せた時間は一様に深夜。客を降ろしたところは新宿である。新宿といっても広いが場所は一定ではない。客は茸を生でかじっていた、これは先に記したもの以外に十人の運転手から聞き取りをおこなっており、それを含めた解析結果で、誰が見ても、おかしな出来事といわざるを得ない。
これをどのように整理したらいいか。そう、私がなぜこの噂に興味を持ったのか話をしなければならない。私は文化人類学の学徒である。新宿というところ、多くの人が知るところであるが、昔は野っぱら、そこに人が住むようになったが、いうなれば関東の野蛮人。そこに武士がやってきて、ようするに鎌倉に幕府が開かれ、江戸という場所にはまだ確たる文化はなかったが、江戸城ができてからは、日本代表の、立派すぎるほどの町が形成された。江戸の隆盛期には百万の人間が暮らしていたのである
そうなるまでに昔からいた動物たちはどうなったかを調べたのである。狸や狐、兎、鼬や鼠、様々な動物が迷惑を被って、人に場所を空け渡したのである。しかし鼠は家に入りこみ人の生活にスタイルを合わせたが、兎や鼬は人の住みかに住んでしまうほど自分たちに自信がなく、すなわち怖くて自分たちから人の住居から離れていった。それでも鼬などは人が飼っている鶏の卵を盗んだりするくらいの度胸があった。それでは狸はどうか。この動物も人の住まいのかなり近くに居を構えたのである。今の世の中でも特に狸は人に依存したような生活を平気でする。一方、こわがりの狐はかなり人とは距離をおくようになった。それでも意外と人の近くにいる。
みなさんはご存じだろう。狸も化かす、狐も化かす。というのが大昔から流布している噂話である。何か失敗したり、みっともないことになると、狸に化かされてやっちまったよと狸のせいにするのである。
その視点でタクシー運転手の証言を再度検証してみよう、運転手が言ったことだけからすると、何か失敗してそれをごまかすために、このようなことを他人に言うことはまずないだろう。
このインタビューは断った上で録音させてもらっていたが、録音を止めた後のオフレコの話がいくつかあり付け加えておく。
最初のケースの松茸の件は、客が降りた後、車の中に落ちていたのは、食べくずと落としてしまったかじりかけの一本だけではなく、一本丸ごと大きな松茸が落ちていたそうである。袋から落ちてしまったのだろう。運転手は家に持って帰り、家族で楽しんだそうである。おそらく一本、一万円もしそうなものであったと言っていた。
二番目のケース。お釣りはいらないと二千六百円のところ、三千円を受け取った。後で金を数えなおしてみると、二枚の千円札と、一万円札一枚だったことがわかったが、それはそのままにしてしまったということであった。
三番目の高田馬場から乗せた女の子三人組のケースでは、その後で乗った客が、これが落ちてましたよと渡してくれたのが、まだほとんどつかっていない口紅だったそうで、今の学生はこんな高級なものを使うのかと驚いたそうである。その女性運転手は、落とし物として届けることをしなかったそうである。
最後の高齢者の運転手のケースでは、関取の手ぬぐいが落ちていて、名前のはいっているものだった。相撲はあまりみていないので顔は知らなかったが、調べたら有名で人気のある力士だったということである。お宝だと喜んでいた。
ということで、彼らには何となく、やましいことをしたという気持ちが隠れている。といって、そんな話をわざわざでっち上げる必要もないわけで、むしろこのことを私に話さないほうがいいくらいであり、彼らの話の信憑性を否定するまでには至らないのである。
ところがなにかしっくりこないのは、同じタクシー会社でしか起こらなかった点である。朝でかける前か終わってからか、一息つくとき、仲間の誰かがそんなことを言い出して、それがそれぞれの運転手に話をこしらえる元となった可能性である。
いつも人と接しているタクシーの運転手は、人間を見る目に関してはよく鍛えられていると考えてよい、観察眼はあると推測される。もちろんそうでない人もいるだろう。それにしても彼らに見間違いはなかったと信じている。
こんどは茸を食べた三人の客の降りた場所について考えてみよう。すべて新宿である。ただし場所は違う。
運転手たちは記録もあるせいか、降りた場所の記憶はしっかりしたものだった。それを新宿の地図にプロットしてみた。十四ほどのプロットを線で結んでみた。するとほぼ三角になった。
三角の空間を見ていくと、真ん中あたりに神社のマークがある。どのような神社なのだろうか。調べてみることにした。
授業のない土曜日の夕方その神社を訪ねた。
昔に建てられたアパートや民家が数件、マンションが二つ近くにある。まだたばこ屋が残っているような懐かしい雰囲気の漂う地域である。その一角に、植えられた大きな桜の木に覆われて神社があった。石の土台に囲まれたおよそ五十坪ほどしかない、ちいさい神社である。
数段しかない石段をあがって木でできた古びた社のところに行った。汚れた千羽鶴が扉の脇に吊りさげられている。扉の前には賽銭箱があり、その脇に萎れた花がさしてある牛乳瓶と皿があった。皿にはご飯粒がいくつか固まってついていた。おにぎりなどが供えられていたようだ。
だが狐がいない。稲荷神社ではない。扉の中を覗くとお地蔵さんである。石で彫られたもので顔がはっきりせず崩れそうな地蔵である。白間神社と賽銭箱に消えそうな字で書かれている。いつごろ建てられたのか社の周りを見てもヒントになるような記載はない。地蔵で神社だ。神仏習合そのものだ。
境内からでて,石段の下から見ると、狭い境内にいくつもの木が植わっている。入口付近の桜の木以外はすべて実のなる木であることは特記すべきか。自分にわかるものとして柘榴、無花果、枇杷、柿、棗、グミ、栗だろうか。
猫が一匹道を曲がって神社のほうにやってきた。その後ろからエプロンをかけたおばあさんが歩いてくる。牛乳ビンにさした花をもち、反対の手にはお稲荷さんが三つのった皿がある。や
私が立っている前を、お辞儀をしながら通り過ぎ、石段をあがると、社の扉の前の古い牛乳瓶と新しい花の入った牛乳瓶を取り替えた。お供え用の皿に持ってきたお稲荷さんを三つのっけて手をたたいた。猫が足にじゃれている。
私はおばあさんが石段をおりてきたので呼び止めた。
「すみません、ちょっとお話をいいですか」
「なんですかね」
お婆さんは年の割には若い声で答えた。
「いつもお花と、お供えものを用意されるのですか」
「うん、土曜日の夕方にね」
「花とお稲荷さんですか」
「うん、おにぎりだったりもしますけどね」
「どうして土曜日の夜なんです」
「いつでもいいのだけど私の習慣でね」
「ご飯粒が皿についていましたが、誰か食べるのですか」
「明日の朝にはなくなっているね、なにが食べたかわからないけど、きっとカラスだよ」
「なぜ、三つお供えするんですか」
「そりゃ、三匹に感謝してですよ」
「三匹って」
「このお地蔵さんはね、三匹の狸に感謝して建てたものなんだよ」
「え、狸」
「狸なんざ、私が若い頃はごろごろいたもんですよ」
「狸に感謝すると言うと、謂われがあるのですね」
「それは昔の話で私も爺様に聞いたのだけどね、まだこのあたりが草に覆われていたときの頃ですよ、近くの庄屋さんの生まれてすぐのお嬢さんが拐かしにあいなすってな、身代金を支払ったにもかかわらず戻ってこなくてね、七日たっても見つからない、もうだめだとあきらめようとしたときに、どこからともなく現れた狸がお嬢さんがくるまれていた布端をくわえていてね、これはと思った庄屋さんが狸の後をついていくと、草むらの中で二匹のタヌキがお嬢さんを暖めていたですよ、おそらく乳も飲ませたのだろうということでした」
「それでそのときからこの地蔵さんはあるのですね」
「ええ、もう二百年になるんじゃないかね、その庄屋さんが神社を建てて、社には地蔵をいれて、食べ物を毎日供えたということですよ」
「神社に縁のある方ですか」
「いや、私の先祖はそんな金持ちじゃないけど、庄屋さんには世話になっていたからこの地蔵をお守りしていたのでね、それで昔から私の日課なんですよ、今ではお供えは土曜日の夕方だけだけど、くるだけは毎日きていますよ、健康にいいんですよ」
「このお地蔵さんの由来を書いたものでもあるのでしょうか」
「さあ、私はそういうものを読むような人じゃないからね」
「どこかに書かれたものを持っている人はいないでしょうか」
「このあたりの人はもうみんな新しい人でね、いないね、区役所にでも行けば何か分かるかもしれないよ」
「そうします、ありがとうございました」
「あ、あとね、私が知っているのは、このあたりは玉といってたそうよ、由来はよくわからないけど、その狸たちは三匹とも白子で、真っ白だったそうなの、お地蔵さんも真っ白に塗ってあったらしいのよ、それでこの玉にある神社は「しろたま」から「た」ぬきして、白間神社と言うようになったと、おじいさんが言ってたわね、ほんとかどうか分からないけど」
「え、それは面白い、ありがとうございました」
それからおばあさんは振り向いて言った
「そういやあ、これもおじいさんから聞いたんだけど、狸は茸ご飯のおむすびが一番好きだったということですよ、これもどうしてだか知りませんけどね」
「あのー、Aタクシーをご存知ですか」
「ああ、あのタクシー会社ですか、庄屋さんの末裔がやってるんですってよ」
こう言うとおばあさんは猫と一緒に帰っていった。
私はため息をついた。これで解決したような気がしたのである。
タクシーの客
私家版第四茸小説集「茸人形、2018、234p、一粒書房」所収
茸写真:著者 東京都日野市南平 2016-7-3


