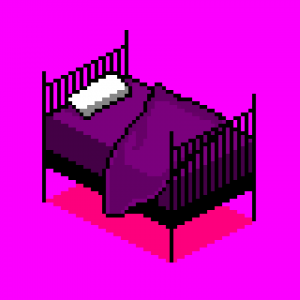猫の恋
猫の恋
その日は朝から糠雨が降っていた。
もう葉桜の時季だというのにす――っと背筋が冷える。雨垂れが窓ガラスに打った点描に、薄灰色に烟る町並みはどこか不気味に歪んでいた。
終業時間を迎えてPCの電源を落としたわたしは、保育園に通っている息子のお迎えに行く前にひと息つこうとインスタントコーヒーを淹れた。リモートワーク様々だ。
コーヒーをすすりながら夕食のメニューをどうしようかと冷蔵庫の中身を確かめていると、窓の外から赤ん坊の泣き声が聞こえた。
耳を澄ますと、赤ん坊にしては野太くて濁声だ。水滴の点描画を透かして猫の影がちらりとよぎる。
どうやら恋の季節が過ぎても婚活をあきらめきれない独り身の猫がお見合い相手を探しているらしい。
最近見た深夜のバラエティー番組で結婚相談所が取り上げられていたが、人間も猫も大変なのはお互い様だなと笑ってしまった。
コーヒー一杯ぶんの休息は瞬く間に過ぎ、わたしはレインコートを羽織ってビニール傘を差すと自宅を出た。
保育園は自宅から大人の足で十分圏内の距離にある。息子が歩けるようになるまではベビーカーを使っていたが、四歳近いいまでは難なく徒歩で通園できるので助かっている。
自宅と保育園の中間地点に位置する児童公園の脇道を歩いていると、雨音に紛れて猫の鳴き声が聞こえてきた。先ほど見かけた猫だろうか。
鳴き声が近づいてきた。公園側の植え込みがガサガサと揺れている。
わたしは立ち止まり、周囲を見回した。
息子が赤ん坊のころ、この公園は野良猫の溜まり場だった。近所に住む老夫婦がこっそり餌をあげていたらしい。しかし、ほかの住民からの苦情が役所に入った結果、老夫婦は餌やりに現れなくなり、自然と野良猫の姿も消えた。
ふと、冷たい雨の中いもしないお見合い相手を探し続ける猫が憐れになった。
わたしは植え込みのほうへそっと声をかけた。
「ここにはほかの猫はいないよ。雨も降ってるし、今日はあきらめて明日違う場所で探してみたら?」
鳴き声がびたりと止んだ。
植え込みの下に黒い猫の頭が垣間見えた。
「風邪引かないようにね」
軽く手を振ってその場から立ち去る。
保育園に到着すると、顔なじみのママ友と娘さんに行き合った。
「こんにちは!」
息子より一歳上の娘さんが人懐っこい笑顔で挨拶をしてくれる。
これが息子だと下を向いてもじもじしているだけだ。おとなしくて気のやさしいわが子だが、将来がちょっと心配だ。
「こんにちは」
「雨でいやんなっちゃいますね。今日は自転車?」
「うっかり牛乳切らしちゃったから帰りにスーパー寄ろうと思って」
ママ友が苦笑まじりに答える。
彼女とは子どもが保育園に入る前、地域の子育て支援センターからの付き合いだ。
旦那さんが仕事でしょっちゅう留守にしているので、ワンオペで育児をしている。実家は離れた地方にあり、ご両親も頻繁に手伝いには来れなかったそうだ。
ちょうどそのころシングルになり、離婚のいざこざで実家とも疎遠になっていたわたしは彼女に親近感を覚えた。
支援センターやお互いの家でよくいっしょに遊んだが、娘さんが入園した彼女は支援センターにあまり顔を出さなくなった。わたしも実家との関係が修復し、保活や復職の準備に追われて慌ただしくなり支援センターから足が遠退いた。
彼女とはそれっきりになるかと思っていたが、息子の入園先が娘さんと同じ保育園に決まったことで再び交流を持つようになったのだ。
最近、ご両親が古くなった実家を引き払ってこちらへ転居してきたらしい。実家が頼みのワンオペ育児という境遇や、むやみやたらに踏みこまず、ほどほどの距離感を保ってくれる人柄のおかげで気楽な付き合いが続いている。
「それじゃあ気を付けて」
「ありがとうございます。また明日」
「ばいばーい!」
電動自転車のチャイルドシートに乗った娘さんがレインカバー越しに手を振る。
それに手を振り返し、わたしはママ友親子を見送った。さて、息子を迎えにいかなければ。
「ママ!」
保育園の玄関でリュックを抱えて走ってきた息子を抱き止める。
「今日は粘土で上手に猫を作っていたんですよ」
若い保育士の先生がにこやかに教えてくれた。
「ねこさん、早くおうち来ないかなー」
近ごろの息子は猫の動画を見ることにハマっていて、すっかりわが家にも飼い猫がやってくると決まったような気分になっている。
わたしは曖昧な笑みを取り繕い、先生へ挨拶するよう促した。
「せんせー、さようならー」
「はーい、さようなら。気を付けてねー」
「ありがとうございました」
レインコートを被った息子と手をつないで保育園をあとにした。息子は長靴で億劫そうに歩きながら、猫を飼うならふわふわな黒猫がいいと力説している。
児童公園の脇道に差しかかったとき、わたしはぎくりとして立ち止まった。
「ママー?」
不思議そうな顔をする息子が道の先を見ないように抱き寄せる。
脇道の中間地点あたりに黒いゴミ袋のようなものが打ち捨てられていた。糠雨に濡れそぼったそれの周囲には赤黒い水溜まりが広がっている。
……車の通りが少ない道だが、運悪く轢かれてしまったようだ。痛ましい姿から目を逸らし、わたしはわざとらしい声で息子に言った。
「うわー、大変! 道のむこうに大きな水溜まりができちゃって通れなくなっちゃった!」
「えー! どうしよう!?」
「今日は公園を通り抜けて帰ろう。いつもより歩くけど大丈夫?」
「んー、だいじょーぶ」
息子は猫の死骸には気づいた様子はなく、のんびりと頷いてみせた。
脇道に背を向けて公園の中に入る。息子と声を合わせて『あめふり』を歌いながら家路を急いだ。
帰宅するとそのまま浴室に直行する。バタバタと入浴を終えたら、息子は湯上がりの麦茶を飲みながらタブレットでYouTubeを見はじめ、わたしは夕食の支度に取りかかる。
息子はお気に入りの猫の動画を再生しているらしく、リビングから猫の鳴き声が聞こえてきた。
にゃあ、にゃあ、みゃお、みゃお……あぉーん、あぉーん。野太い雄猫の鳴き声にビクッと肩が跳ねた。
包丁を動かす手を止めて息を殺すと、雄猫の求愛の声が家の外で上がっている。
あの死んだ猫以外にも婚活中の猫がいたのだろうか。雄猫の声は家の周囲をぐるぐると回り続けている。
奇妙な薄ら寒さを覚え、わたしは顔をしかめた。なんだか、死んだ猫の声に似ていないか?
「ママー、お茶のんだー」
息子の声にわれに返る。
「こっちに持ってきてくれる?」
「はーい」
包丁をまな板に置き、息子からコップを受け取った。
不意に息子が瞬き、リビングの窓のほうを見遣る。
「ママ、これ、ねこさんの声?」
「……たぶん、そうかな」
「ぼく、ねこさん見たい!」
息子はパッと窓辺へ駆け寄った。とっさに追いかけて、遮光カーテンを開けようと伸ばされた手を捕まえる。
「やめて!」
思わず強い語気で叫ぶと、息子は目を真ん丸にして硬直した。
短く息を吸いこみ、次の瞬間にはわぁッと泣きだした。
「ごめん、ごめんね。びっくりさせちゃったね」
しゃくり上げる体を抱きしめ、わたしは窓から遠ざかった。
その夜、猫の声はひと晩じゅう家の周りをぐるぐると歩き回っていた。
朝陽がのぼって聞こえなくなり安堵したのも束の間、遮光カーテンを開けて窓の下に目を向けたわたしは悲鳴を上げた。
まるで捧げ物のように地面に置かれていたのは、血まみれの雀の死骸だった。
なんとか息子を保育園に送り届けて自宅に戻ると、雀の死骸を新聞紙に包み、さらに黒いポリ袋に入れてごみ集積所に捨てた。
仕事部屋に駆けこんでPCを起動させる。熱いインスタントコーヒーをすすって胃が温まると、ようやく混乱が落ち着いてきた。
死んだ猫があとをついてくるなんて、陳腐なホラー小説のような錯覚だ。
「気のせい……気のせいよ、きっと」
それから猫の声は夜ごとに響くようになった。
夜明けまで家の周囲を徘徊し、窓の下に小動物の死骸を残して消える。
猫が見たいと言ってカーテンを開けようとする息子をなだめすかして寝かしつけても、鳴きやまない猫の声が神経をすり減らし、わたしはすっかり不眠に陥った。昼間は猫の声が聞こえてこないので緊張がゆるむのか、猛烈な眠気に襲われて仕事が手につかない。
息子は保育園で「おうちにねこさんが来た!」としきりに話しているらしく、お迎えに行くたびに先生たちから「猫を飼われはじめたんですか?」と尋ねられる。怒鳴り散らしたい衝動をぐっと堪え、「野良猫が家の敷地をよく通るんです」と愛想笑いでごまかす。
送り迎えの際、公園横の脇道は徹底的に避けた。猫の死骸がどうなったのか確かめる勇気など持てなかった。
猫の声に悩まされるようになって五日目。その日も、朝から糠雨が降っていた。
頭の芯をぎりぎりとねじられているような痛みに吐き気がする。
「きょうもねこさん、来てくれるかなー?」
無邪気な息子の声すら忌々しく、わたしは普段の自分なら眉をひそめるような口調で息子を急かして自宅を出た。息子もわたしの不機嫌を感じ取ったのか、黙って手を引かれて歩いている。
保育園に着いて息子を送りだすと、途端に頭痛がひどくなった。
思わず玄関先にうずくまって呻いていると、ママ友の声に呼びかけられた。
「大丈夫ですか!?」
のろのろと目線を上向けると、ママ友と娘さんが気遣わしげに顔を覗きこんできた。
「顔が真っ青ですよ。どこか具合が悪いんですか? 先生にお願いして中で休ませてもらったほうが――」
わたしは首を横に振った。目尻に浮いた涙が転がり落ちる。
「でも……」
ママ友はしばらく逡巡し、「ちょっと待っていてください」と言って娘さんを連れて園舎へ駆けこんでいった。
数分後、ひとりで出てきたママ友はそばにしゃがみこむと背中をさすってくれる。
「何か、あったんですか?」
労りのこもった問いかけに堪えていた感情が堰を切ったように溢れだし、わたしは咽び泣きながら五日間の悪夢について打ち明けた。
ママ友は辛抱強く耳を傾けていた。
「……大変でしたね」
話を聞き終えたママ友のひと言に、わたしの涙腺はいよいよ壊れてしまった。
赤の他人の彼女が一切否定せず、わたしの気持ちを受け止めてくれたことが嬉しかった。実家の両親なら、「そんなものは気のせいに決まっている」「女手ひとつで働きながら子どもを育てるなんて、あんたにはやっぱり無理よ」「浮気ぐらい目を瞑って、離婚なんてしなければよかったんだ」とぐちぐちとわたしを責め立てるに決まっている。
関係が修復したといっても、つまるところわたしが黙って両親の言い分を聞き流しているに過ぎない。息子のことはかわいがってくれているし、困ったときには助けてくれる。
だが、本当は、ずっと苦しかった。
離婚の原因は夫の背信だ。妊娠中から息子が産まれたあとも、残業や休日出勤と嘘をついて複数の女と浮気をくり返していた。
「子どもができてから、俺にやさしくなくなっただろ。いつも疲れてるかピリピリしてるかで、俺が何言っても怒るじゃん」
息子のことなど見向きもせず、それこそ子どものようにふてくされた顔で自分の行いを正当化しようとする男に、愛情という水は涸れ果てて心は砂漠と化した。
おそらく、あのときわたしという人間はいちど死んだのだ。
夫に裏切られ、両親にも受け容れてもらえず、赤ん坊の息子を抱えて暗い海を漂流しているような絶望感に苛まれていた。
海へ身投げせずに生き延びられたのは、味方のいない孤独に共感してくれたママ友のおかげだった。気持ちを立て直し、純粋に息子を愛することができるようになった。
わたしと違ってご両親と円満な彼女に対する嫉妬が微塵も芽生えなかったのかといえば嘘になる。だが、ご両親が近くに引っ越してきて以前よりも雰囲気の和らいだ彼女や娘さんを見ていると、心からよかったと思えるのだ。
えずくように泣き続けるわたしを支えながら、ママ友は彼女の自宅に連れていってくれた。
リビングに通されて温かい焙じ茶を出される。わたしと違って、ママ友はコーヒーや紅茶よりも日本茶を好む。亡くなったおじいさんの影響だと聞いたことがあった。
焙じ茶をひと口すすると、雨で冷えた体が芯から温まるようだった。
「祖父から聞いたことがあるんですけど……」
ママ友が静かに切りだす。
「猫は家に憑くんです」
「家に憑く?」
「猫は死ぬところを見せないって言うでしょう? 飼い猫でも野良猫でも、死骸を残して死んだ猫に情を寄せるとその人の家に憑いてしまって成仏しないんですって。だから昔は、猫の死骸は三つ辻に埋めて、家までついてこれないようにわざと迷わせたそうです」
「じゃあ、あの猫はうちに憑いてしまったってことですか!?」
いまの自宅は両親の伝手で安く借りている借家だ。古いけれど日当たりのいい二階建ての一軒家で、わたしも息子も気に入っている。
「わたしたちが出ていかなきゃならないの……?」
呆然と呟くと、ママ友はひたとわたしを見据えた。
「まだ間に合うかもしれません」
「本当ですか!?」
「猫が死んだ日から今日で五日目ですよね? 初七日を過ぎていなければ、死骸を三つ辻に埋めれば家から引き離して冥途へ送りだせると思います」
仏教の考えでは、死者は死んだ日を一日目と数えて七日目に三途の川のほとりにたどり着くという。つまり、七日以内に猫の死骸を三つ辻――三叉路へ埋葬して弔えば家への帰り道を見失うという寸法だ。
「でも、三つ辻って……どこの?」
「なるべく遠い土地がいいと思います。心当たりはありますか?」
「心当たり……」
離婚前、夫と暮らしていた家が脳裏をよぎった。あの家は三叉路に面していたはずだ。
「あります。結婚していたころに住んでいた家の近くなんですけど……他県で、この町からは車で一時間以上かかるから……」
「なら、そこへ行きましょう。車を出すので、六日目……明日の昼間に猫の死骸を回収して、お迎えまでには戻れるように」
「今日じゃだめなんですか?」
正直、今夜もあの鳴き声に耐えられる自信がない。縋る思いで尋ねると、ママ友は険しい面持ちで首を横に振った。
「たぶんその猫はお宅に留まっているから、いったん引き離さないと。ひと晩留守のように見せかけて、あなたが家を離れたと思いこませるんです」
「ど、どうやって?」
ママ友はしばし迷った様子を見せたあと、そろりと口を開いた。
「冗談に聞こえるかもしれないんですけど……私の家系……というか、亡くなった祖父の家が、代々特殊な家業を営んでいたんです。悪いものを遠ざけたり、身を隠したり、そういうことが得意で」
「えっと……霊媒師や拝み屋みたいな……?」
「先祖は修験者崩れだったそうです。何代か前からは山守をしていたんですけど、祖父の遺言で家業を廃することになりました。ただ、私は祖父からいろいろと隠形について聞きかじっていたので、多少の心得はあります」
わたしはまじまじとママ友を凝視した。
不思議なほど彼女が虚言を吐いているようには見えなかった。おんぎょうという耳慣れない言葉を取り扱う口調は、こちらまで平静になるほど落ち着きを払っていた。
ママ友は真摯に身の上を打ち明けてくれたのだと信じられた。わたしは居住まいを正して頭を下げた。
「よろしくお願いします。どうか、助けてください」
「はい」
ママ友はしっかりと頷いた。
それからわたしたちは、今後の計画について打ち合わせた。
まず、今夜はお泊まり会という名目でママ友親子がわが家へ泊まりこむ。息子を連れてホテルに避難したらどうかと提案したが、下手にわたしたち親子が動くと避難先までついてくるかもしれないというリスクのため却下となった。
ママ友の隠形でわたしたち親子を猫から隠し、自宅から引き離す。朝まで待って子どもたちを保育園に送ったあと、ママ友の車で猫の死骸を目的の三叉路まで運んで埋葬する。
六日目の夜もママ友親子に泊まってもらい、隠形で七日目の朝までやり過ごす。七日目の朝までに声が聞こえなければ、猫は道に迷って戻ってこられなかった……という結果になる。
子どもたちは二日間お泊まり会をすると説明すれば、大喜びで疑問にも思わないだろう。
打ち合わせを終えて帰宅する間際、ママ友が古いお手玉をひとつ差しだした。
「お守り代わりに持っていてください。中に小豆が入っているから魔除けになると思います。うちの娘も守ってくれた実績付きです」
お手玉を受け取ると、手の中で小気味よい音が鳴った。
縮こまっていた心がやわやわと広がっていく。わたしはお礼を言ってお手玉をポケットにしまった。
自宅へ戻ってスマホを確かめると、上司からの着信が何回も入っていた。
急いでかけ直し、頭痛がひどくて寝こんでいたため連絡ができなかったという説明ととも謝罪した。
上司は苦言を呈しつつ、「最近Zoomでも具合悪そうだなって心配してたんだよ。こっちは気にせず、しっかり休みな。お子さんの面倒も見なきゃだろ?」と明日までの有給を許可してくれた。わたしはスマホ越しに頭を下げた。
通話を切ってソファーに身を投げるとたちまち意識が遠ざかり、夢も見ずに熟睡した。
目が覚めたときにはすっかり昼を回っていた。
空腹を覚えて冷凍の炒飯をレンジで温める。食事を済ませて市販の痛み止めを飲むと、頭痛が和らいだ。
簡単に掃除機をかけたり、洗濯物を片付けたり、客用布団を出したりしたりと動き回っていると、あっという間にお迎えの時間になった。
糠雨はあいかわらず降り続いている。ママ友とはお迎えのタイミングで待ち合わせをしていた。
保育園に着くと、登山用の大きなリュックを背負ったママ友が待っていた。
「旦那のなんですけど、買い物や泊まりがけの外出に便利で重宝しているんです」
「へえ、いいですね。キャリーバッグと違って両手が空くから、子どもと手もつなげるし」
「そうそう!」
ママ友の笑顔になんだか普通のお泊まり会をするような気分になってきて、つられて頬がゆるんだ。
先生に連れられてやってきた子どもたちは二日続けてお泊まり会と聞いて大興奮だ。はしゃいでいる息子は猫の声のことなどすっかり忘れているようだった。
賑やかに家路をたどり、夕食は早々にデリバリーを取って済ませた。
食後に子どもたちがお絵描きやブロックで遊んでいる中、ママ友が外につながる戸口や窓にお札のようなものを貼っていく。
「それは?」
「摩利支天の真言を書いたものです。祖父の家で信仰していた仏様なんですけど……陽炎の化身で、実体がないので捕らえられず傷つけられない、隠形の力を持っているんです」
まるでホラー映画の撮影を見学しているような気分だ。
そうこうしているうちに遊び疲れた子どもたちが夢の世界へ旅立った。家じゅうが静まり返り、ひたひたと雨音が染みこんでくる。
ふと寒気を覚えて身震いすると、ママ友がカーテンを閉め切った窓へ視線を向けた。
「来た」
そのひと言にぶわっと鳥肌が立った。
……あぉーん、あぉーんと、赤ん坊の泣き声のような、野太い濁声が聞こえてきた。
思わずママ友を見遣ると、彼女は口元に人差し指を当てて頷いた。
事前の打ち合わせで、猫の声が聞こえているあいだは沈黙を貫くよう念押しされた。猫の声に応えるようなそぶりをわずかでも見せると隠形が解けてしまうらしい。
猫の声はいつもどおり家の周りをぐるぐると歩き回っている。
ママ友がささやくような小声で何かを唱えはじめた。短い呪文じみた言葉を一定のリズムでくり返している。
猫が威嚇するように低く唸った。小動物の死骸の置き場所である窓のガラスをガリガリと引っ掻く音がする。
わたしは両手で口元を押さえ、必死に悲鳴を飲みこんだ。ママ友は擦過音と唸り声が聞こえる窓を睨み据え、淀みなく呪文を反復する。
……目の錯覚だろうか、彼女の体からゆらゆらと湯気が立ちのぼっているように見える。
違う――湯気ではなく、陽炎だ。
無色透明な炎がママ友を包みこんで揺らめき、輪郭を不定形にぼやけさせている。
わたしは息を呑んだ。
自分の両手からも陽炎が立ちのぼっていた。リビングと続いている和室に敷いた布団の中で眠りこんでいる子どもたちからも。
熱さはなく、春の陽射しに照らされているように暖かい。
三十分ほど経って擦過音が止んだ。
猫の声が悲しげに響き渡る。わたしの気配がわからなくなったのだ。
鳴き声は窓の下をうろついていたが、とうとう雨音に溶け消えた。
――わたしを探して、猫が家を離れたのだ。
全身から力が抜ける。どっとため息を吐きそうになって口を引き結んだ。
ママ友は呪文を唱え続けている。まだ油断はできないのだ。
借り受けたお手玉を握りしめ、わたしは人生ではじめて心から神仏に祈った。
摩利支天様、摩利支天様、わたしたちを隠してください。わたしと息子の平和を脅かすものを退けてください。
どうか、どうか、助けてください――
ふっと目を開くと、カーテンの隙間から仄白い光が射しこんでいた。
ぼんやりとソファーから身を起こすと、和室から出てきたママ友がほほ笑んだ。
「おはようございます」
「……おはよう、ございます。あの、猫は……?」
「無事にこの家から離れたみたいです」
わたしはへなへなと脱力した。
「子どもたちも無事ですよ。まだ寝ています」
「よかったぁ……!」
ワッと涙が溢れだした。
ママ友は隣に座り、えずくわたしの背中を撫でさすってくれた。
「ひとまず安心ですね」
「あっ、ありが……うえぇ」
年甲斐もなく大泣きして顔がべしょべしょになる。ママ友はカーテンを開けると窓の下を覗きこみ、わたしを手招いた。
「今日は何も置いてないですね」
「本当だ……」
窓の下に悪夢の残滓は見当たらなかった。草葉の上で朝露がきらきらと光っている。
「子どもたちを送りだしたら、猫の死骸を回収しにいきましょう」
ママ友の言葉に涙を拭って頷いた。
子どもたちを起こして騒々しく支度を済ませ、保育園へ送っていく。
ママ友の自宅へ車を取りに戻り、公園横の脇道に駐車した。
降車する前からママ友は呪文――摩利支天の真言だそうだ――を唱え、わたしは無言で彼女のあとに続いた。
……猫の死骸は雨ざらしのまま横たわっていた。
ママ友がさっと古い毛布を広げて猫の死骸を覆い隠す。毛布には油性マジックで真言が記されていた。
猫の死骸を毛布で包み、車のトランクに運びこむ。
ママ友は運転席、わたしは助手席に座ると、あらかじめ設定しておいたナビを起動させた。目的地まで一時間半足らず。
緊張感と腐臭に満ちた車中にママ友の真言だけが聞こえる異様なドライブ。ノンストップで走り続け、やがて車窓を流れていく景色に既視感を抱く。
短くてつらい結婚生活の記憶がよみがえり、俯いてくちびるを噛んだ。
予定どおりの時間に、産まれて間もない息子を抱いて逃げだした町に到着した。
四年という月日は、町並みを様変わりさせてはいなかった。それが余計に息苦しい。
住宅街の中を進んでいくと、かつてのわが家が見えてきた。結婚してすぐに購入した新築の一軒家だ。
離婚協議中、慰謝料として明け渡すと夫に言われたが、出産のためにわたしが入院している最中に女を連れこんでいた家なんてだれが住みたいと思うだろうか。結局、いまは夫がローンを返しながらひとりで暮らしている。
ママ友は家が見える距離の細い路地に車を停めた。
あたりに人気はなかった。わたしたちは帽子とマスクで顔を隠し、猫の死骸を車から運びだした。
最近の戸建てらしく、夫の家は塀も門もない。三叉路に面した敷地には容易に侵入できた。手前の駐車スペースに夫の車はないので、予想どおり仕事に出かけているのだろう。
玄関脇の植栽は手入れしていないらしく伸び放題だった。持ってきたスコップで植栽の根元を掘り起こす。
ある程度の深さまで掘り進めると、穴の中に猫の死骸を横たえた。無心で土を被せていく。
十分あまりで埋葬を終えると、わたしたちは短く合掌した。慌ただしく車に戻り、ママ友がエンジンを入れる。
サイドミラーには夫の家の玄関先が映りこんでいた。植栽が揺れて、小さな黒い影がずるりと這いだす。
影は三叉路の手前で動けなくなったように静止した。車が路地を出ると、サイドミラー越しの景色が後ろへ流れていく。
住宅街を抜けてしばらくしたころ、ママ友が帽子とマスクを脱いだ。窓を開けて車内に残っていた腐臭を散らす。
絶えず真言を唱えていたママ友は激しく咳きこんだ。あらかじめ用意しておいたミネラルウォーターのペットボトルの蓋を開けて手渡す。
「ありがとうございます」
風邪を引いたような声をお礼を言い、ママ友はペットボトルを呷った。
「はあ……」
ママ友は息を吐きだし、バックミラー越しに目が合うとほほ笑んだ。
「最後まで気づかれなくてよかったです。明日の朝まで油断はできませんけど、大丈夫だと思いますよ」
ママ友の言葉に、わたしはシートに深く体を預けた。「よかった……」
「狙いどおり、三つ辻に惑わされてくれたみたいですね。あのままあきらめてくれたらいいんですけど……」
わたしは帽子とマスクを外した。
窓から吹きこんでくる風を浴びて新鮮な空気を吸いこむ。
「もしも猫があきらめなかったら――」
ママ友の目がちらりとわたしへ向いた。
「どうなるんでしょうか?」
「さあ。あてもなく彷徨い続けるのか……別の家に憑くのか」
ママ友は穏やかな笑みを浮かべた。
「いずれにせよ、もう関わりのないことですから気にしないほうがいいですよ。悪いものから逃げ切るコツはさっさと忘れることです」
「……なるほど」
サイドミラーに映る自分の顔も、ママ友と同じ笑みを仮面のように被っていた。
「そうします」
「ぜひそうしてください。そうだ、お迎えまで時間がありますから、どこかでランチしていきませんか?」
「いいですねぇ! 実は前から気になっていたカフェがあるんです。でも、子連れだと入りづらそうで……」
「じゃあそこに行きましょう。住所ってわかりますか?」
「ちょっと待ってくださいね。ええっと――」
わたしはスマホでカフェの住所を検索した。
スポンジに水が染みこむように、ママ友のアドバイスにすんなり納得できた。
守るべきものは息子であり、そして平穏な生活だ。夫の浮気が発覚してからずっと腹の底で渦巻いていた鉛色の感情が窓のむこうに広がる五月晴れの空へ飛んでいく。
ああ、なんて爽快な気分だろう。
悪いものをまとめて捨て去り、わたしは声に出して笑った。
ママ友とのカフェランチを楽しんだあと、二日目のお泊まり会はつつがなくお開きになった。
わが家の周辺で再び猫の声が聞こえることはなかった。息子はしばらく残念そうだったが、ママ友親子といっしょに子連れオーケーの猫カフェに出かける話が持ち上がると気にならなくなったようだ。
保育園からの帰り道、公園横の脇道を歩きながら息子とおしゃべりする。
「ねこさんのお店、どんなねこさんがいるのかなー?」
「楽しみだねぇ」
息子があっと声を上げた。
「ママ、見てー! ねこさん!」
小さな指が指す先には薄汚れた白猫がいた。
一瞬こちらを見るが、すぐに走り去る。
「行っちゃったあ」
「きっと猫さんもおうちに帰るんだよ」
「ぼくとおんなじー!」
愛おしい笑顔に、わたしは心から笑い返した。
「そうだね。ママといっしょにおうちへ帰ろう」
猫の恋